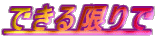
「では、一品の宮にして頂きましょう。」
「へ?なに?いっぽんのみや?」
「はい。神子様を一品の宮にして頂けば所領が与えられますので…。」
「ちょ、ちょっと待って藤姫。しょりょうって?」
「神子様所有の土地ができて、そこから収入を得られるということですわ。これまでそうして頂かなかったことの方がおかしいのです。ちょうど良い機会ですので、一品の宮に…。」
「ストップ!その話はストップ!」
あかねは藤姫の前で必死に両手を振った。
ここは土御門の屋敷、藤姫の局。
あかねはある相談事があって藤姫のもとを訪れていた。
そして、その相談の結果が今の藤姫の発言だ。
あかねを一品の宮に。
よくよくそれがどういうことなのかを聞いてみればとんでもない話で、あかねは慌ててそれこそ当然とばかりに手続きしかねない藤姫を止めたのだった。
あかねはよくここを訪れて藤姫と楽しく語らうこともあるから「ストップ」の意味は藤姫も心得ているらしい。
すぐに口を閉ざした藤姫はあかねに小首を傾げて見せた。
「土地をもらえるとか、なんていうか、それ、凄いことなんじゃ…。」
「それは確かに、一品の宮には皇族の方しかなれませんので…。」
「こ、皇族?!」
あかねは卒倒せんばかりに驚いた。
皇族しかなれないものにしてもらうなんてとんでもない。
「当然ですわ。神子様は皇族の皆様よりもいわば尊いお方です。」
「尊くないよ!普通だから!」
「ですが、神子様、一品の宮となれば神子様のお悩みも即解決…。」
「しても違う悩みが増えちゃうから!」
「そうですか…。」
残念と藤姫がうなだれてもあかねにここを譲る気はない。
それでなくても左大臣家の養女にしてもらってとんでもなくいい生活をしているし、頼久は実家の力を使うことができるから生活に困ったことなど一度もない。
ひょっこりこっちの世界へやってきた女子高校生には過ぎた生活を今でもしていると思っているのに、これ以上なんてあかねにとってはとんでもないことだった。
「私はね、ちょっとしたお仕事がないかなって思っただけなの。」
「仕事…。」
「ほら、食器を洗うとか、料理をちょっと手伝うとか、そういうことでお金もらえないかなって。」
「それは…頼久に知られたくはない、ということでしょうか?」
「そう!そうなの。頼久さんに贈り物がしたくて…。」
「では、わたくしが神子様に差し上げるのも…。」
「ごめんね、それもダメ。」
「やはりそうですか。そうなりますと…。」
「藤姫じゃ無理?」
「はい。神子様にご紹介できる仕事となりますと、思いつきません。」
「そっか…。」
やっぱりだめかとうなだれて、あかねは溜め息をついた。
こうなる予感はしていたけれど、やっぱりだった。
この京では元いた世界のようにすぐにアルバイトをすることは不可能なのだ。
特にあかねは身分というものが高すぎるらしくて、ちょっとお皿洗いで自給をなんてことはありえないらしい。
これはどうしたものかとあかねは落ち込んでしまった。
「それに、神子様がそのような仕事をすることを頼久も喜ばないと思いますが。」
「そう?」
「はい。源氏武士団の若棟梁の妻がそのような仕事をしているというのは聞いたことがございません。頼久は許すと思いますが、許しはしても心配でしょうし…。」
「そっか、そうだよね。」
誰よりも自分のことを大切に思ってくれている夫のことだから、藤姫の言う通りだろうとあかねはすぐに納得した。
「でも、どうしても頼久さんに何か甘いものを贈りたい日があって…。」
「ばれんたいん、でございますか?」
「藤姫、覚えてたんだ。」
「はい、何やら茶色い菓子を贈る日と以前にも神子様が張り切っておいででしたので。ですが、菓子となりますと…。」
「うん、高価なのは知ってるの。材料だけでもすごく高価だって後から聞いて驚いたし……。」
「手作りするにも材料は必要ですわね。でしたら、材料をうちの者に採取させては…。」
「それだ!」
「そう致しますか?うまく集まるかはわかりませんが…。」
「ううん、そうじゃなくて、私が取りに行けばいいんだよ!」
「はい?」
「木の実とか、蜂蜜とか、何か甘いものが採れるかも。イノリ君なら知ってそう!」
「神子様…。」
「相談にのってくれて有り難う、藤姫。」
あかねは良いことを思いついたと張り切って藤姫の局を飛び出した。
もともとこの京の女性からは想像もつかないほど活発なあかねだ。
きっと有限実行、イノリを供に京の中を食材求めて散策するのだろうと予想して藤姫は考え込んだ。
これはこのまま放っておいていいものだろうか?
いいはずがないというのが結論で…
藤姫は一つうなずくと文を書き始めた。
「なあ、あかね。」
「なに?」
「考えてることはわかるけどな、やっぱやめた方がいいんじゃね?」
「あ、イノリ君忙しかった?」
「そうじゃなくて。オレは全然大丈夫だけど、心配、すんじゃねーの?頼久とか藤姫とか。」
「それは、頼久さんには内緒にしてるから…それに二人ともイノリ君が一緒なら心配はしないよ。」
「いや、まぁ、オレはちゃんとあかねを守る気ではいるけどな…。」
そういうことじゃない、とイノリは髪をかきまわした。
藤姫はともかく、頼久はそういう意味ではなくいたたまれないのではないだろうか?
すっかり成長したイノリにはここのところ、頼久の気持ちもだんだんとわかるようになっていた。
「どうしてもあかねが見つけないとダメなのか?その、何か甘いものって。」
「うん。」
「って言ってもなぁ…。」
イノリにも甘いものに心当たりがないわけじゃない。
確かに山の幸の中には甘みがあるものもある。
たとえば栗、柿、桃などがそうだ。
夏なら花の蜜だって甘い。
けれど、この時期にそんなものが山になっているわけがなかった。
それでもあかねはどうしても探すと言う。
あかねの気持ちもわからないではない。
なんだか大切な行事だと言っていたし、それは大切な人のために必要なものだと言われればイノリも協力したいのは山々だ。
それでも、協力していいことと悪いことがあるということが今のイノリはわかる。
あかねの望みをかなえることは確かに必要なことかもしれないが、それ以上に必要なのはあかねの安全を考えることだった。
「あかね。」
「なに?」
もう少しで京の都の外へ出るというところでイノリはあかねを呼び止めた。
やっぱり帰ろうとうながすためだ。
だが、イノリは自分がそんな説得をする必要はなかったらしいと気付いて苦笑を浮かべた。
道の向こうに大きな人影を見つけたからだ。
「どうしたの?イノリ君。」
「あそこ。」
あかねはイノリの指差した方を見て息を飲んだ。
ゆっくりとこちらへ歩み寄ってくるその人影はどんどん大きくなって、そしてあかねの目にはっきりとその姿が映った。
京の人間にしては珍しいほどの長身、従えている長い髪、腰の太刀、そしていつまでたってもドキドキさせられる端整な顔。
間違いない、今あかねの方へと歩み寄ってくるその姿は頼久のものだった。
「神子殿。」
「頼久さん……。」
あかねはその名をつぶやいただけで何も言えなかった。
頼久がこんなところにわざわざやってきているということは、自分が何をしようとしているかはもうばれているに違いないわけで…
目の前に立って深い溜め息をつく頼久の姿を見て、あかねは今までの元気はどこへやら泣きそうな顔でうつむいた。
「イノリ、すまなかったな。」
「いや、オレはいいけど…頼久、あんまあかねを怒るなよな。あかねも考えがあってやってんだ。」
「承知している。気遣いすまぬ。」
「んじゃ、オレはもう行くな。」
軽く手を振ってイノリはすぐに駆け去ってしまった。
あかねはお礼も言えなかったと思うとますます悲しい気持ちになって、視線が下へ下へと向いてしまう。
そんなあかねの手をとって、頼久はあかねの屋敷の方へと歩き出した。
「あの……怒ってます、よね、頼久さん……。」
「は?」
「へ?」
思わぬ頼久の答えにあかねは思わず視線を上げて、隣で目を丸くして足を止めた頼久の顔をじっと見つめた。
「いえ、怒ってはおりません。」
「でもさっき、凄く呆れたみたいな溜め息…。」
「あれは、神子殿がご無事であったと安堵しただけです。怒ってはおりません。」
「ごめんなさい、心配かけちゃって…。」
「いえ、イノリが一緒と聞いてはいましたので、大事はないだろうと思ってはおりましたが、己がお側にいられぬとなるとどうしても落ち着かず、私の方こそ申し訳なく。」
「頼久さんは何も悪くないです。私が勝手に頼久さんに贈り物がしたくて…。」
「甘いもの、でしたか。」
「あ、覚えててくれたんですか?」
「はい。それに、さきほど友雅殿より事情を聞きましたので。」
「友雅さん?え、なんで?」
「藤姫様が心配なさって、私に話すことは神子殿の本意ではないので友雅殿にこっそり神子殿を警護して欲しいとお頼みになったようです。友雅殿は自分が警護するよりは私に事情を話したほうが良かろうとはからってくださいました。」
「そうだったんだ……私、なんかみんなに迷惑かけてばっかり…。」
「そのようなことはありません。皆、ただ神子殿を大切に思っているというだけのことです。お気になさらず。」
「最初から頼久さんに材料をそろえてくださいってお願いすればよかったんですよね…。」
「そうはなさらないからこそ神子殿とも思いますが、これからはそのようにして頂ければ私がなんなりとそろえてご覧にいれます。」
「有り難うございます。来年からそうします。」
苦笑しながらそう答えて、あかねはとぼとぼと歩き出した。
色々考えてはみたけれど、結局、みんなに迷惑をかけただけで終わってしまった。
こんなバレンタインにしてしまって、大好きな旦那様も呆れたに違いない。
心優しい人だから、怒りさえしないけれど…
「神子殿。」
「はい?」
「本日がその、甘いものを異性へ贈る日ということでよろしいでしょうか?」
「あ、はい、そうです。色々探しても何も見つからなくて…これから材料集めるのも無理ですよね…ごめんなさい、何もできなくて。」
「いえ、その……でしたら是非、頂きたいものがあるのですが。」
「はい?」
頼久がこういうことを言い出すのは珍しい。
あかねは一瞬驚きながらも、珍しく夫が欲しいというものなら何でも差し出そうという気構えで頼久を見つめた。
「なんですか?頼久さんの欲しいものって。」
「その……神子殿のお時間を頂きたいのです。」
「時間、ですか?」
「はい、今宵一夜と明日の一日を。」
「そんなのいくらでもあげますけど…いつものことじゃないですか。」
「いえ、本日頂くのは甘いものでもありますので。」
「へ…。」
見ればすっかり顔を赤くしてあかねから視線を逸らせている頼久にあかねは小首を傾げた。
欲しいのは自分の時間、だけれど、それは甘いものでもある…
よくよく意味を考えて、そして結論にたどり着いてあかねは顔を真っ赤にした。
「わ、わかりました!」
頼久が欲しがっているのはあかねと二人の甘い時間という意味だ。
それに気付いてあかねは首まで真っ赤になった。
今宵一夜がついたということはそういうことだろうとさすがのあかねにも察しがつく。
「おや、その分だと頼久は言うべきことをちゃんと言ったのかな?」
「友雅さん!」
二人が真っ赤な顔で並んで屋敷へ戻るとそこには友雅の姿があった。
楽しそうな笑顔で迎えた友雅の相変わらずの艶やかな姿に頼久の目が自然と鋭くなる。
「頼久さんがあんなこと言うなんておかしいと思った。友雅さんが入れ知恵したんですね?」
「入れ知恵とは人聞きが悪いね。まぁ、少々教え諭しはしたが…。」
「お気遣い感謝いたします。これより我らは屋敷の内にて夕餉に致しますので、お引き取り下さい。」
横から口を出したのは頼久だ。
このまま居座られてからかわれたのではたまらないということだろうと見当をつけたのか、友雅はクスッと笑みを漏らすとゆっくり歩き出した。
「そうだね、これからは二人で甘い一時を過ごすといいよ。邪魔者は退散するからね。」
「あ、友雅さん、有り難うございました。」
「いやいや、礼なら心配してくれた藤姫に言いなさい。」
「はい。」
あかねが友雅に頭を下げれば、友雅は軽く手を上げてそれに答えて去っていった。
いつもながらの颯爽とした歩みにあかねが微笑を浮かべていると、頼久がその腕をとって屋敷の中へと導いた。
いつもの屋敷、いつものあかねの局。
けれどそこには何故かとてもいい薫りが漂っていて…
「これ…。」
「友雅殿でしょう。」
部屋の隅には香が焚かれている香炉が一つ。
その香炉がまだ温かいことを確かめて頼久は苦笑を浮かべた。
この京で憧れぬ女性はないとまで噂される少将殿はこのようなところまで気配りが行き届いているらしい。
「さすが友雅さんですね。こういうことさせたらたぶん京で一番。」
「私が行き届かぬことをご存知だからでしょう。」
「頼久さんはそれでいいんです。だって、私より気配りできる旦那様なんて、私の方がちょっと居心地悪いです。」
「神子殿…。」
優しく微笑みかけてくれる妻の小さな体を頼久はそっと抱き寄せた。
この京の女性の誰もが憧れるという身分高き男性よりも自分の方が良いと言ってくれる人。
そしてこの世で最も尊く、最も高貴で、大切な人。
できうる限りの力をもって自分への想いを伝えてくれようとした人。
頼久は腕の中の小さな温もりが自分にとってどれほど大切で愛しいものなのかを噛み締めながら、そっとその唇に口づけを落とした。
この行為が許される存在が自分だけだということに心の底から感謝しながら。
管理人のひとりごと
バレンタイン企画、頼久さん京版バージョンでございます!
今回もあかねちゃんは一人で頑張ってますよ(笑)
イノリ君がちょっと成長してましたなぁ。
あとは頼久さんも成長してます(笑)
だって怒らないもの(’’)
まぁ、心配はしてるけど(^^;
これは治りません(w
そして少将様は今回もステキな登場と退散。
管理人は実は少将様好きだな、たぶん(’’)
ブラウザを閉じてお戻りください