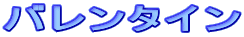
天真は仏頂面でソファに座っていた。
何故かというと朝からずっと部屋中が甘い匂いで満たされているからだ。
天真の視界の端ではああでもないこうでもないと3人の人間が右往左往している。
これも朝からずっとだった。
「おい、お前らそろそろ昼だぞ。昼飯くらい作らせろって。」
「お兄ちゃん外で食べるか何かとるかして!今無理!料理とか絶対無理!」
「ごめんね、天真君、今本当に無理!」
「あかねちゃん、よそ見してると型からあふれるよ!そっちはボクがやるから湯煎の方をお願い。」
「うん!」
ちょっと声をかけただけでこのありさまだ。
そう、あかね、詩紋、蘭の3人はバレンタインデーにプレゼントする手作りチョコレート作成の真っ最中なのだ。
しかもこれがもう3日も続いている。
明日はバレンタインデー当日だというのにこの3人はまだああでもないこうでもないとチョコレートを作り続けているのだ。
おかげで天真はもう胸が悪くなるほど甘い匂いの中での生活を余儀なくされていた。
「大丈夫!お兄ちゃんにもちゃんと義理チョコあげるからね!」
「…いらねぇって…。」
匂いだけでさんざんなめにあっている天真は小声でそうつぶやいてみたが、必死になって作業している3人の耳には届かない。
どうしてチョコレート一つで3日にも渡る大騒ぎになるのか天真には全く理解できないのだが、蘭に言わせるとそれが乙女のロマンなのだそうだ。
よくよく話を聞いてみれば、メインはあかねが頼久に渡すチョコレートだという。
あの神子殿バカに今更愛の告白をするために手作りチョコレートを作るあかねもあかねだが、たとえ石を渡されたって笑いながら食べそうな相手にそんなに気合入れてチョコレートを作らなくてもいいだろうと天真はつっこみたくてしかたがない。
もちろん、そんなことを言おうものなら妹からどんな罵りを受けるか知れないので黙っておく。
「あとは、これとこれを飾りに乗せるでしょ、こっちはココアパウダーをふりかけてね。」
「了解!」
元気よく返事をしたのはあかねだ。
情けないことに、この3人の中で手作りチョコレート作成の陣頭指揮をとっているのは詩紋だった。
お菓子だろうと料理だろうと詩紋が一番うまいのは変わらない。
「洋酒きかせすぎってことない?これ、けっこう匂うんだけど。」
「頼久さんは大人だから大丈夫だよ。ね、詩紋君。」
「うん、少しお酒がきいてるくらいの方がたくさん食べられると思うし。」
「張り切ってたくさん作っちゃったからなぁ…多いかな?」
「大丈夫、頼久さんなら死んでも全部食べる!」
張り切って断言する蘭にあかねは苦笑した。
「やっぱり少し減らそうかな…。」
「ボクはせっかく作ったんだから全部プレゼントした方がいいと思う。あかねちゃん凄く頑張ったし。それにチョコレートはそんなに簡単に腐るようなものでもないし、冷蔵庫に入れておけばしばらくは楽しめるし。」
「そっか、うん、無理しないでちょっとずつ食べてもらうね。」
嬉しそうに微笑みながらチョコレートに最後の飾り付けをするあかねを眺めて天真は苦笑した。
他の男のために一生懸命になっているあかねを見るのは、まだ少しだけ悲しい気もするのだが、相手があの頼久では天真としてはあがきようもない。
それに何より、あれだけ京で頑張ったあかねが今こうして幸せそうにしているのは天真にとっても嬉しいことに違いないのだ。
天真がそんな複雑な思いであかねを見つめていると、テーブルの上に放ってあった携帯が鳴った。
着メロなど設定していないので音だけでは誰からかわからず、携帯を手にとって初めて天真は深い溜め息をついた。
表示されていた着信者の名前は…
「なんだよ、お前が俺に電話って。」
『今、不都合か?』
電話の向こうから聞こえてきたのは今はあまり聞きたくない声だった。
そう、天真を真の友などと恥ずかしい呼び方で呼ぶ相方、頼久だ。
「不都合、じゃねーけどよ…しばらく昼飯食えそうにねぇし…。」
『ん?』
「いや、こっちの話だ。で、なんの用だよ、お前が俺に電話って。」
『うむ…。』
返事だけして話し出そうとしない頼久の様子に天真はなんともいえない嫌な空気を感じた。
もともと寡黙な男だし、無駄な話はいっさいしない性質でもあるが、それにしても今の沈黙はあまりに重たい。
しかも頼久の声はどことなく苦しげだ。
天真は何やらどうしようもない相談を持ちかけられそうな、そんな気配を感じた。
できることなら今すぐ電話を切りたいくらいだ。
「あ、天真君、もうすぐ終わりそう、もうちょっと待っててくれたらお昼ご飯作るけど、待てる?」
「うっ…。」
電話の向こうで頼久が何か話し出そうとした気配を感じたその瞬間に台所からあかねの声が聞こえた。
もちろんばっちり電話の向こうの頼久にも聞こえたはずだ。
「天真君?あ、ごめん、電話中だったんだ。」
「いや…待てる…。」
「あ、うん、じゃ、何か作るね。」
あかねが楽しそうにそういうのを聞いて天真の額に汗が浮かんだ。
明らかに電話の向こうの気配が何やら不穏だ。
『天真。』
「ん?」
『神子殿はそこにいらっしゃるのか?』
「いるにはいる、が、いないことにしておいてくれ。」
『…それはどういう意味だ?』
「どういうってそのままの意味だ。あかねはお前に自分がここにいることを知られたくないんだってよ。」
『……。』
「どうした?」
『…では、ここ数日神子殿が忙しそうにしておいでだったのは、お前のところに通っていたからなのか?』
「そうだ……ってお前、まさか…。」
『何がまさかだ?神子殿はお前のもとに通っておいでだったのだろう?それを私には知られたくないと、そういうことなのだろう?』
「……お前の相談ってそれかよ…。」
あかねに相手にしてもらえないと愚痴の電話をかけてきたらいしこの相棒はどうやら明らかに何か誤解しているようで、天真は深い溜め息をついた。
『神子殿は…お優しい故に…。』
「いいか、今から説明するが大きな声じゃできねぇから耳の穴全開にしてよーく聞け。」
『今更なんの説明が…。』
「いいから聞け。聞かないと本当にあかねかっさらうぞ。」
『……。』
「あのな、明日なんの日だ?」
『なんの日?』
「やっぱな、あかね、お前に何も話してないんだろ。で、お前みたいな朴念仁は全くわかってないだろうが、明日はバレンタインなんだよ。」
『あぁ…。』
「あぁ、じゃねぇよ、おかげでこっちは毎日死ぬほど甘い匂いでもうボロボロだ…。」
『なんの話だ。』
「あかねはお前に手作りチョコレートを渡したいっていうんでここで蘭と詩紋つき合わせて3日間、ずっとチョコレートの研究してんだ。いいか、これはここだけの話な。お前は明日、何も知らなかったふりして感動してチョコレートを受け取れ。そのためにあかねは3日ずっと頑張ってんだからな。」
『そうか、そういうことであったか…。』
「そういうことであったんだよ、まったく、俺の身にもなれってんだ…。」
『お前は甘いものは嫌いなのか?』
「…嫌いじゃなくても3日もチョコレートの匂い嗅がされ続ければ嫌いにもなる…。」
『私は神子殿のお作りになるものの薫りならば…。』
「あああああ、もうわかった、わかったから切るぞ。これ以上話してたらバレる。」
そう言って天真は一方的に電話を切った。
台所で昼ごはんの準備が終わりそうだったからだ。
昼ごはんの支度に集中していたらしいあかね達に気づかれずに電話を切ることができた天真は深い溜め息をついた。
どうしてここまで自分がバレンタインデーのために打ちのめされなければならないのか。
「お待たせ天真君。チャーハンだけどお昼ご飯できたよ。それと、これは天真君に。」
あかねはそう言って落ち込んでいる天真に歩み寄ると小さな包みを手渡した。
「いつもお世話になってます、これからも仲良くしてね。」
「お、おう。」
どうやら中身はあかねの手作りチョコレートらしい。
義理チョコだとわかっていても、あかねの手作りチョコレートは天真の気分を少しだけ上向きにさせた。
仲良くしてね。
愛の告白ではないけれど、今の天真にはそれだけで十分な一言だった。
−翌日−
あかねはドキドキしながら頼久の家を奇襲しようとしていた。
もちろん、いつもみたいに扉の前に立っただけで気配を感じた頼久は出てきてくれるのだけれど、それでも電話で予定を聞かずに訪ねてくるのはあまりないことで、驚く頼久の顔を想像すると少しだけ後ろめたくて、そしてとっても楽しみだ。
手には紙袋が一つ。
中には詩紋に教えてもらって作った手作りチョコレートが何種類か入っている。
一人の相手に贈るには少しばかり量が多いが、それは張り切ってしまった結果だ。
ちゃんと少しずつ食べて下さいと注意しないと、などと考えながらあかねは扉の前に立った。
すると案の定、すっと扉が開いて向こうから微笑を浮かべた頼久が顔を出した。
「神子殿。」
「こんにちわ。突然すみません。あの、今いいですか?」
「はい、どうぞ、お入り下さい。」
「お邪魔します。」
あかねは嬉しそうに出迎えてくれた頼久について中に入り、いつものように台所へ向かってお茶をいれる。
これからチョコレートを食べてもらうことを考えて、あかねはとっておきの紅茶をいれた。
「突然ですみませんでした。」
「いえ。」
そんな会話を交わしながら紅茶を手に、二人はソファに並んで座る。
最近ではこうして並んで座るのが当たり前になっていた。
「えっとですね、今日は頼久さんに受け取ってもらいたいものがあってきたんです。」
「はい。」
「えっと…。」
紙袋を手にあかねは一つ深呼吸をしてからすっとまっすぐ頼久を見つめた。
隣に座っている頼久もまっすぐあかねを見つめ返す。
「頼久さん。」
「はい。」
「私は頼久さんが大好きです、これからも宜しくお願いします。」
ぺこりと頭を下げてからあかねは紙袋を頼久に手渡した。
「有難うございます。私も心より神子殿をお慕いしております。こちらこそこれからも宜しくお願い致します。」
そう言って頼久も頭を下げる。
「ん〜。」
「神子殿?どうかなさいましたか?」
「頼久さん、あんまり驚いてないなぁと思って。」
「は?」
「頼久さんのことだから今日がバレンタインだって気づいてないんじゃないかなって思ってたんですけど…もしかして私がチョコレートプレゼントするって予想してたんですか?」
「い、いえ、それは…。」
予想していたもなにも、必ずそうしてくれると知っていたのだが、そうと言ってしまうと天真の立場がなくなるだろう。
だが、予想していたと言ってしまうとそれはそれで嘘だとはっきりわかりそうだ。
「頼久さん?もしかして知ってたんですか?私がチョコレート作ってたの。」
「……。」
「天真君だ。」
「いえ、天真は悪くないのです。私が無理に聞きだしました。」
「へ?」
頼久は一つ溜め息をついて観念した。
この愛しい人に嘘をつくなど始めから不可能だったのだ。
「その、ここ数日神子殿とお会いできず、メールの返信もそっけなく、お忙しい様子でしたので…その…天真に電話を…。」
「あああああ、昨日の電話!」
「はい…それでその…神子殿のお声が電話の向こうから聞こえてきましたので…その…私には秘密で天真とお会いになっていたのかと私が勘違いをしたもので、やむを得ず天真が事情を説明してくれたのです。」
「勘違い…。」
「はぁ…。」
「勘違いしたんですか?」
「はい…。」
「それってひょっとして、私が頼久さんに内緒で天真君とデートしてた、とか、そういう勘違いってことですか?」
「………は、はい……。」
頼久の額に脂汗が浮かんだ。
これは怒られる。
いくらお優しい神子殿でもきっとお怒りになる。
そう心の中で覚悟を決めて、頼久は神妙に目を伏せた。
「…あるわけないじゃないですか、そんなこと。」
そういったあかねの声があまりに静かで悲しそうで、頼久ははっと視線を上げた。
「でも、私が悪いんですよね、頼久さんに隠し事したのは私だし…。」
「と、とんでもありません!神子殿は何一つ悪いことなど!」
「頼久さんは京での自分を全部捨てて私のためにここへきてくれたのに、私が頼久さんに隠し事なんてよくなかったです、ごめんなさい。」
「お謝りになることなど!」
「でも、私、バレンタインデーにチョコレートプレゼントってしたことなくて、張り切っちゃって…頼久さんに喜んでほしくて…。」
「神子殿…。」
「これからはもうしません。不安にさせてごめんなさい。」
そう言って頭を下げるあかねの声は震えていて…
頼久にはあかねが涙ぐんでいるのがわかった。
あかねが泣いていると知ってパニックになりそうな自分をぐっと抑えて、頼久は紙袋の中に入っているいくつかの包みのうちの一つを取り出すと、綺麗な包装を丁寧に解いて出てきた箱の蓋をあけた。
中に入っていたのは小さなボール型のチョコレートだ。
「今頂いてもよろしいですか?」
「へ、あ、はい、どうぞ。」
すっかり落ち込んでいたあかねが慌てて顔を上げて涙をぬぐいながらうなずいて見せる。
頼久はチョコレートを一つ口に運んでやわらかく微笑んだ。
その笑顔があまりに綺麗であかねは思わず見惚れた。
「甘すぎずいい香りがして美味ですね。」
「あ、えっと、詩紋君に教えてもらって少しお酒が入ってるんです。えっと、他にもナッツが入ってるのとかドライフルーツが入ってるのとか色々あるんですけど、張り切って作りすぎちゃって…一度にたくさん食べると体によくないですから、ちょっとずつ食べてもらえると嬉しいです。」
「はい。大事に少しずつ頂きます。有難うございます。」
そう言って微笑む頼久の笑顔がとても幸せそうで、あかねはつられるように笑みを浮かべていた。
「神子殿にこのようにお気遣い頂き、私は幸せ者です。」
「そ、そんなことは…ふ、普通ですよ。」
「いえ、幸せです、本当に幸せです、この上もなく。」
心の底から本当に幸せなのだということが伝わる言葉だった。
言葉にすることが苦手な目の前の恋人がこんなふうに想いの伝わる言葉を紡いでくれたことが嬉しくて…
あまり嬉しすぎてあかねの目にまた涙が浮かんだ。
「神子殿…。」
「あ、違います、これは別にその、悲しいんじゃなくて…。」
「承知しております。」
そう言って頼久は優しくあかねの肩を抱き寄せた。
そしてうっとりと自分の胸に肩を預けてくれるあかねの唇に優しく口づける。
あかねがバレンタインデーにもらった素敵なキスは少しだけ甘い香りがした。
伝わる互いのぬくもりと甘いチョコレートの香りに酔って、互いに微笑みを交わしてもう一度口づけて。
もう言葉は何もいらなくて、二人はそのまましばらく甘い香りに包まれて優しく抱き合ったまま今の幸せをかみしめた。
管理人のひとりごと
はい、現代版バレンタインデーでした。
京版よりは最後ちょ〜と甘くした、つもりです(’’)
前半がなんか天真君ファン倶楽部みたいな天真君のかっこよさだったんで(笑)
後半は頼久さんに幸せになってもらいました。
あかねちゃんの手作りチョコおいしそうです。
きっと頼久さんもおいしく幸せに頂いたことでしょう(^^)
プラウザを閉じてお戻りください