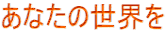
弥生十四日は頼久にとってとても重要な、忘れてはならない襟を正すべき日だ。
何故ならそれは、本来であれば頼久の手など届くはずのなかった天女である妻に感謝の想いを伝える日だからだ。
如月十四日にはその妻であるあかねがおそれ多くも手ずから単を仕立てて贈ってくれた。
しかも愛らしい飾りの紐までつけてだ。
そこには、本当は甘いものを贈るのが習慣だというのに、甘いものはこの京では高価故、夫である頼久に負担をかけまいという尊い心遣いまでが込められていた。
それでも「ちょこれーと」という本来贈るべき甘味に近づくようにと単の色を選んでくれたのだという。
これほどの心遣いがあるだろうか!
と、頼久が感動することひとしおだったのが如月十四日のことだった。
あかねに必ず着てほしいと望まれさえしなければ、家宝として大切に飾っておくところだったのだが…
着るために仕立てたのだから着るべきだと言われてしまえばまことにもっともで、もちろん大切にではあるが毎日のように単は着用している。
大切にしているということはあかねにも伝わっていると思うが、感謝の気持ちは伝えきれていない。
弥生十四日はその感謝の気持ちを伝える大切な日だ。
頼久はそう心の内に刻み込んでこの一カ月を生活してきたのだった。
準備は一カ月をかけてじっくりと整えた。
そのために主筋に当たる藤姫の協力も得て、この日をまず休みとしてもらった。
藤姫はあかねのためにと言うと大喜びで休みを約束してくれた。
『神子様のために休みをとるとはよく思いつきました。』とお褒めの言葉まで頂いたものだ。
「頼久さん、早いですね。今日はお休みなんじゃ…。」
休みといえども予定が入っているわけだから、朝はいつもと変わらぬ時間に起床した頼久の隣で、あかねが目をこすりながら半身を起こした。
まだ少し寝ぼけているらしいその口調も様子も愛らしい。
「休みなのですが、少々予定がありますので。」
「予定、あるんですか…。」
突然しおれてしまったあかねに頼久は思わず手を伸ばしていた。
休みなら一日一緒に過ごせると思っていたのが、予定があるならそれは無理だと落ち込んだのだとわかれば大切な妻への愛しさが倍増するのが頼久という男だ。
「頼久さん?」
「ご安心を、予定と申しましても、あかねにも同道して頂きたい予定ですので。」
「そう、なんですか?」
「はい。是非に。」
そういって軽く小さな体を抱きしめると小さな声で「良かった」と言う声が腕の中から聞こえた。
無意識のうちに思わずつぶやいたのだろうが、そのつぶやきはあまりにも愛らしくて、頼久は口元に笑みをともして、あかねを抱く腕に力を込めた。
「頼久さん!朝です!」
「はぁ…。」
突然大声で叫んであかねは愛らしい腕で必死に頼久の体を押し返す。
その様子を見て頼久は、素直にあかねを抱き寄せていた腕を解いた。
「あかね。」
「はい?」
「というわけですので、本日は私と共に出かけて頂きたいのですが。」
「はい、いいですけど、どこへ行くんですか?」
「どこへなりとも。」
「はい?」
「あかねの行きたい所へ参りましょう。」
「どういうことですか?」
「ここのところあかねは京の女性らしくと御簾の内で過ごしてくださっていますので、たまには外出を楽しんで頂きたく。」
「それってひょっとしてホワイトデーのデートってことですか?」
「はい。」
ホワイトデーというのが弥生十四日の呼び方で、デートが逢瀬を指すということは頼久も学習している。
だからすぐにうなずいて見せたのだが、あかねはその様子を見てパッと花が咲いたように微笑んだ。
「嬉しいです!あ、でも…。」
「牛車は使いませんのでご安心を。徒歩(かち)か、遠出になるようでしたら、私の馬に共に乗って頂くように致しますので。」
「有り難うございます。」
あかねは京で生まれ育ったわけではない。
だからなのか、牛車での移動を苦手としていた。
その代わり、この京の女性とは比べ物にならないくらい足が強い。
遠くまで歩いて出かけることをいとわないし、牛車のようにゆっくり移動するくらいなら馬に乗った方がいいという考え方だ。
それでも京女性の衣装を身にまとった状態では牛車を使わない移動は無理なので、今日ばかりはあかねに龍神の神子であった頃のように水干を着用してもらう予定だった。
「それじゃあ、すぐ着替えちゃいますね。」
京の中を怨霊を倒して歩いた経験のあるあかねはその辺の事情には通じている。
そうと悟ってすっくと立ち上がると、すぐに着替えをすべく、局を飛び出して行った。
残された頼久は腕の中にさっきまであったぬくもりを思って苦笑して、すぐに着替えを開始した。
この様子だとすぐに出かけようとするあかねに朝餉をとるようにと進言する必要があるだろう。
そんなことを思いながら。
「うわぁ、人、多いですね。」
二人がやってきたのは市だった。
目的地として市を選んだのはあかねだ。
あかね曰く、デートらしいデートになるからということだったが、頼久にはどういうことなのか完璧に理解できたわけではなかった。
それでも、出かけてきてみればあかねが楽しそうな笑顔になったので、目的地として市を選択したのは正解だったのだろう。
あかねは辺りに広げられている品物を見ながらゆっくりと市を回り始めた。
「食べ物もけっこう色々ありますね。台所で切れてる物がないか聞いて来ればよかったなぁ。ついでにお使いできたのに。」
少し残念がっているあかねの隣で頼久は密かに苦笑した。
たとえあかねが何かついでに買ってこようかと厨の者に尋ねてもじゃあお願いしますという人間は一人もいないだろう。
何しろあかねは屋敷の女主人であり、この京を救った龍神の神子なのだから。
頼久にとってはそれが当たり前の認識なのだが、あかねはいまだに自分が周囲から崇められる存在だとは思っていない。
そこがまた、あかねの魅力でもあり、屋敷の者達が更に尊敬を深くする部分でもあるのだが。
「うわぁ、綺麗…。」
突然あかねが足を止めたのは、布を扱っている商人の前だった。
並べられている布は決して高価というわけではなさそうだが、確かに色が鮮やかだった。
「気に入る物があれば購ってもかまいませんが…。」
そう声をかけてはみるものの、頼久にはあかねの答えがわかっている。
あかねは滅多に必要のない物を買おうとはしないのだ。
曰く、もったいない、のだそうだ。
貴族の女性ともなれば、高価なものが自然と貢がれて当然という京では、龍神の神子ほどの女性が私欲を持たないというのは非常に稀有なことだった。
もちろん、そこもあかねの美点として屋敷でも崇められているのだが。
「綺麗だなって思いますけど、今のところ着るものには困っていませんし…あ、そうだ、頼久さんに似合いそうなの、見てみましょうか?」
「いえ、私は先日、仕立てて頂いたものがありますので。」
丁寧に断っても、しばらくあかねは頼久と布を見比べていた。
どうやら本当に似合うものがあれば買って帰るつもりのようだったが、結局はこれという決め手が見つからないという理由で歩みが再開された。
「本当に何も購わなくてよろしいのですか?」
「いいんです。こうして二人で歩くのが楽しいんです。」
そう言ってあかねは頼久の左腕を軽く抱いた。
これが腕を組んで歩くという、あかねの世界では男女にとってとても重要な行為だと頼久が覚えたのはもうずいぶんと前のことだった。
買い物をせずにただ品物を見て歩くことは「うぃんどうしょっぴんぐ」という。
これも覚えたのはずいぶん前だった。
「頼久さん、つまらないですか?」
「私があかねと共にいてつまらないなどということはございませんのでご安心を。」
「っ……また頼久さんはそういうことを……。」
「そういうこと…。」
あかねの顔が真っ赤に染まった。
頼久は自覚していないのだが、あかねは時折こうして頼久の言葉に顔を赤くすることがある。
平気で恥ずかしいことを言っているということらしいのだが、もちろん頼久には自覚がなかった。
首まで赤くなりそうなあかねは頼久の腕を引いて少し歩くペースを上げた。
どうやら照れ隠しらしいとわかれば、頼久の顔に笑みが浮かぶ。
流れ行く景色の中にあかねがいるというだけで幸せな頼久だ。
「うわぁ、馬がいますよ。」
「はい、こちらの市では馬も扱っておりますので。」
「そっか、頼久さんが馬に乗るっていうことは、その馬を売っている人がいるっていうことですよね。」
「我々は市で馬を買うことはあまりありませんが…。」
「そうなんですか?」
「はい、良い馬は市ではなかなか手に入りません。ですから、我々は馬を育てている土地まで探しに行ったり、献上品を主から頂いたりということが多いのです。」
「なるほど。」
武士にとっては命を預ける相棒になるわけだから、馬はそれくらい重要なのかと思えば、市で売られている馬を見るあかねの目もいつしか真剣なものになっていた。
「あかね。」
「はい?」
真剣に眺めながらもやっぱり馬は可愛らしくて、思わず笑みをこぼしたあかねは背後から聞こえた少し低い声に振り返った。
そこには真剣な頼久の顔が…。
「どうかしたんですか?」
「少々お尋ねしたきことが…。」
「はい、なんですか?」
「あかねのいた世界の『ほわいとでー』はどのように過ごすものだったのでしょうか?」
「どうでしょう?」
「は?」
「私、誰かにバレンタインにチョコレートあげたりしたことなかったから、ホワイトデーのお返しももらったことないし…。」
「そう、なのですか?」
「はい。クッキーとか飴とかプレゼントされたり、あと、アクセサリーをもらったりっていうこともあったみたいですけど…。」
「あくせさりー…。」
「あああ、えっと、簪とか?櫛、とか、かな…。」
「では、後ほどそれらを手配いたします。」
「へ?」
真剣な顔で何かを決意したらしい頼久に一瞬ぽかんとしてしまったあかねは、次の瞬間全てを悟って微笑んだ。
「いりません。」
「は?」
「私は簪より櫛よりもっと凄く高価なものをもらったので、もうそういうものはいらないんです。」
「高価なもの…私は差し上げた覚えが…。」
「時間です。頼久さんは今日一日を私にくれたでしょう?時間って何にも勝るとっても貴重な物ですよ。私が一番喜ぶ贈り物でもあります。」
「あかね…。」
頼久は武士団の若棟梁として皆にとても頼りにされている。
更には八葉としての功績があるから、主上の覚えもめでたくなってしまった。
つまり、とても忙しいのだ。
その頼久が、丸一日体をあけて、自分のために時間を使ってくれることはあかねには何よりの贅沢に思えた。
「あっちの世界でも、ホワイトデーはデートして食事してっていう人もいたはずだし、私、そういうのにも憧れてましたらか、今凄く嬉しいですよ。」
そう言ったあかねの笑顔は本当に何よりも明るく輝いて見えた。
だから、自分に気を使って言ったのではないと頼久にもわかった。
「では、せっかくです、もう少し見てみましょう。疲れたらおっしゃってください。私が抱いてお運びしますので。」
「だ、大丈夫です!」
また一瞬で顔を赤くしたあかねは頼久の腕を引いて歩き出した。
温かい手に引かれる己の腕を眺めながら頼久は心の中で誓っていた。
自分の時間を贈られることが何より嬉しいと言ってくれるこの優しい愛妻のために、きっとまたすぐに休みをとろうと。
頼久が藤姫に頼み込んで連休を取り、自分のために仕事を無理に休んでほしくはないとあかねに説教をされるのはこれから十日後のことだった。
管理人のひとりごと
長くなっちゃった(゚Д゚|||)
本当は頼久さん、ちゃんと贈り物も考えてたのにな(マテ
長くなったからそこ、割愛で(、、)
気が向いたら頼久さんがこの後、何か贈り物をしたところも書くかもしれません(^^;
現代人にとっては時間って凄く貴重なものだと思うんですよね。
別に現代人じゃなくてもかなぁ、と思っての一本でした。
管理人が現状、時間に追われているもので…
ということで、余裕ができたら贈り物編、書きます!
ブラウザを閉じてお戻りください