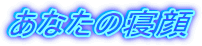
もう夏の始めを知らせる温かい風が開け放たれた窓から流れ込んで、頼久の長い髪をゆるゆるとなびかせた。
頼久の手には分厚い本。
そして頼久の向かい側のソファではあかねがすーすーと気持ちよさそうな寝息をたてていた。
時刻は土曜の午後二時。
昼食をとり終わって一休みして、あかねはこの穏やかな午後、恋人といる安心感からか眠りの世界へと足を踏み入れてしまっていた。
そんなあかねの上に薄手の毛布をかけてやり、頼久は静かに本を読んでいた。
あかねが眠りについてしまうことは別に珍しいことじゃない。
学校の授業を受け、毎日のように自分のもとへ通い、家に帰って勉強をして料理を習って…
あかねがそんな、普通の女子高生よりよほど忙しい毎日を送っていることを頼久は誰よりも一番よく知っている。
だから、自分の目の前で眠ってしまう恋人を見ても少しも恨めしいとは思わなかったし、それよりもずっと愛しい人の眠りを守ることができる自分が誇らしかった。
時折あかねの寝顔を眺め、ふっと微笑して読んでいる本へと視線を戻す。
そんなことを何度かしているうちに日は暮れて、部屋の明かりをつける頃にあかねはやっと目を覚ました。
「うわぁ、私また寝ちゃったんですね…。」
「はい、よくお休みでした。」
そう言って微笑む頼久にあかねはちょっとだけ拗ねて見せる。
「もう、起こしてくださいよ…ほとんど丸半日寝てたじゃないですか、私……。」
「平日は色々とお忙しいようですし、せめて週末くらいゆっくり休んで頂いた方がいいかと思いまして。」
「それじゃ頼久さんがつまらないじゃないですか。」
「そのようなことはございません。神子殿のお側で眠りをお守りすることができるのは私にとって喜びです。」
「眠りをお守りって……京じゃないんですから、守ってもらわなくても安眠できますから……。」
「それでも、神子殿のお側でこうして寝姿を拝見できるのはやはり喜びです。」
そう言って穏やかに微笑む頼久にあかねはため息をついた。
自分の体のことを考えてくれているのはよくわかるし、頼久の言い分もまぁ理解はできるのだ。
それでもやはり起こして、おしゃべりしたり映画のDVDを一緒に観たりしてほしいというのがあかねの本心。
「でもやっぱりせっかくの週末くらい二人で色々……って、寝姿?!」
「はい。」
「よ、頼久さん、もしかしてずーっと私が寝てるのを見てたんですか?!」
それはちょっと、いや、かなり恥ずかしいとあかねが顔を真っ赤にすると、頼久は手にしていた本を軽く振って見せた。
「いえ、これを読んでいましたのでずっと眺めていたわけではありませんが、時折、神子殿が安らかにお休みかどうか確認はさせて頂きました。」
「うわぁ…は、恥ずかしい……もしかして私が寝ちゃった時っていつもそうしてたんですか?」
「はい。」
声にならないほど恥ずかしくて、あかねは顔を真っ赤にしてうつむいた。
「さぁ、そろそろいい時間ですので、ご自宅までお送りします。」
いつものように頼久はそう言って本を片付けると、家の鍵を持ってあかねをうながした。
帰り道が薄暗くなるくらいまで帰りが遅くなると、頼久はそうやって必ず歩いて15分ほどのあかねの自宅まで彼女をしっかり送り届けるのだ。
だが、あかねはすぐには立ち上がらずに、なにやらもじもじとしている。
「神子殿?急ぎませんと、門限を過ぎますが?」
「だって、お昼ご飯食べたあとすぐ寝ちゃって全然頼久さんとお話できてないし、もうちょっとだけここにいたいかなぁと…。」
一向に立ち上がろうとしないあかねに苦笑して、頼久はつつとあかねに歩み寄るとその細い腕をつかんで無理に立たせてしまった。
「頼久さん?」
「また、明日にでもおいで下さい。お待ちしておりますので。」
「……。」
「門限は守って頂かなくては。ご両親が心配されます。」
「……。」
「神子殿?」
「わかりました……明日こそ、絶対寝ないんだから…。」
そう言って不服そうに歩き出すあかねを頼久は安堵のため息をつきながら追いかけるのだった。
翌日。
あかねは張り切って昼食までにはまだ十分に時間のある早いうちから頼久の家へやってきた。
いつものように頼久が開けてくれたドアから中へ入り、台所へ直行して紅茶をいれて戻ってくると、颯爽と持ってきたDVDをプレイヤーにセットして、頼久の隣に座るとじっと映画を観始めた。
かなり気合が入っている。
それは頼久にもすぐに伝わった。
昨日、眠ってしまったことがかなり悔しかったらしい。
そんなあかねが可愛らしくてならなくて、頼久は思わず微笑みながら映画ではなくてあかねを見つめていた。
「きゃっ!」
そんなあかねが映画を観ながら時折頼久の腕に抱きついてきたのは、観ていた映画がホラー映画だったからなのだが、頼久にはそんなことはどうでもいいようで、映画の内容は相変わらずこの青年の頭には入っていない。
だから、映画が終わって「恐かったですねぇ」と言われても「そうでしたか?」と生返事をしてしまった。
「もう、頼久さんはそりゃお化けが出てこようとゾンビが出てこようととりゃって木刀でこうばっさり殴り倒すつもりなんでしょうけど、お化けは殴れないんですからね!恐いんですから!ゾンビなんか一回死んでるから死なないんですよ!」
「はぁ。」
「さっきのなんて物陰から急に出てくるからもうびっくりしたぁ。」
まだ頼久の腕をつかんで放さないあかねはそれでもようやく恐怖からは解放されたようだ。
とにかく映画が恐ろしかったらしいあかねがやはり愛しくて頼久は顔が緩みっぱなしだ。
「たまにはホラー映画もいいかなぁと思ったんですけど、なんか疲れちゃった。」
やっと頼久の腕を解放したあかねはDVDを取り出してケースへ収めると、再び頼久の隣へ座ってふぅっと深く息を吐き出した。
「少し休まれてはいかがですか?昼まではまだ時間がありますし。」
「それは私にお昼寝したら?って言ってます?」
「はぁ…。」
あかねにジト目でにらまれて、さすがの頼久もたじろいだ。
これは、今日のあかねはかなり本気だ。
本気で絶対にうたた寝さえしない覚悟できているらしい。
だが、さきほど頼久がたじろぐほどの強い視線でにらみつけてきたあかねは、次の瞬間、もうしゅんとした顔でうつむいてしまった。
京にいた頃からころころとよく表情の変わるあかねは、今も頼久にはついていけない速度で表情を変えるのだ。
そして、そんな表情の変化を見るたびに、頼久はドキリとさせられる。
自分はこの方の機嫌を損ねるようなことを何かしただろうか?
元来の不器用さがこの方を不愉快にしたのだろうか?
それとも、自分はとうとう愛想をつかされたのだろうか?
などなど、その脳裏を駆け巡る思考はかなりマイナスな感じだ。
だが、頼久のそんな考えは必ずどれも外れていて、今回もあかねは頼久が予想もしなかったことを話し始めた。
「頼久さんは寝ませんよね。」
「は?」
「頼久さんは私の前で寝たことってないんですよ。」
「はぁ…。」
「そりゃ、京にいた頃は武士で、私の警護とかしてくれてたわけで、寝るわけにはいかなかったんでしょうけど…でも、こっちに来てからも一度も寝たところ見たことないんです。」
「はぁ。」
「それってなんか……寂しいかなって…。」
「は?」
頼久にはあかねが何を言いたいのかが全くわからない。
他人とのはずむ会話自体がもともと苦手な上にあかねは年頃の娘さんなわけで、それは頼久がこれまで最も会話してこなかった人種であり、しかもそれが自分が初めて愛しいと思った人となると頼久の会話能力は格段に低下した。
そしてそんな頼久が困り果てているらしいことに気付いて、あかねは再び口を開いた。
「私は頼久さんといると安心してるから寝るんですよ。離れているといつもどこかで頼久さんのこと考えちゃってるし、落ち着かないし、色々心配だし…でも、頼久さんの側にいるととても安心で、幸せで…だから、頼久さんにも私といる時は眠っちゃうくらい安心していてほしいんです。それなのに頼久さん、いつも私の様子を見てるっていうか、気を使ってるっていうか、そんな感じで全然安心してないっていうか、安らいでないっていうか…。」
最後の方はもう言葉にもならなくて、あかねはうつむいたまま悲しげだ。
頼久はというと今語られたあかねの言葉をゆっくりとその心の内で噛み砕いていた。
つまり、あかねがよく頼久の前で寝るのは離れている時よりも一緒にいる時の方が安心しているからということらしい。
そして自分があかねの前で寝ないのは、あかねと共にいても安らいでいないから、とあかねは思っているようだ。
あかねが自分と共にいて安心してくれているということは非常に喜ばしいことだ。
それはもう自分の存在それ自体を認めてもらったような、そんな喜びさえ頼久にはある。
だが、頼久があかねといると安らいでいないと思われているらしい件については、これは大変由々しき事態だ。
そのようなこと、あるはずがない。
自分があかねといる時間をどれだけ暖かく、そして安らぎに満ちたものと感じているかをわかって頂かなくては。
と、そう思ってもなかなか頼久の口からその想いはついて出てはくれない。
いつものように頼久がなんと言ったものかと眉間にシワを寄せ始めたその時、あかねがぱっとその瞳を輝かせて頼久を見上げた。
「膝枕、してあげます!」
「はい?」
名案!といわんばかりの笑顔であかねがソファの端に寄ってぽんぽんと自分の膝を叩くのを頼久は呆然と見つめた。
膝枕?
それはどんなものだっただろうかと、頼久は一瞬、頭の中の辞典をひくほど動揺し、そして膝枕がどんなものだったかを再認識して目を丸くした。
「ただ一緒にいても安らげないなら、安らげるような何かをすればいいんですよ!だから、膝枕してあげますから、寝てください!」
「はぁ…。」
寝てくださいと言われても、愛らしい短めのスカートから伸びるあかねの足はそれはもう意識すればするほど少女らしく魅力的で…
「頼久さん?嫌ですか?」
「いえ、嫌では…。」
「じゃぁ、どうぞ!」
張り切って膝をぽんぽん叩くあかね。
ここまで言われては抵抗することなどできるはずもなく、覚悟を決めた頼久は「では、失礼します。」と掠れた声で言ってからそっとあかねの膝に頭を乗せた。
すると、必然、上を向いた頼久の目には満面の笑みを浮かべたあかねの顔が映るわけで、眠るどころか頼久は微笑むあかねにうっとりと見惚れてしまった。
すぐそこにある愛しい人の笑顔に見惚れながらも、頭の下にはやわらかなあかねの太腿の感触があるわけで、緊張するやらうっとりするやらでとてもではないが頼久は眠れるような状態ではなく…
「頼久さん?」
「は?」
「えっと、安心、できません?」
「いえ、そういうわけではなく…。」
あなたの愛らしい笑顔に見惚れて眠れませんとはとても言えない頼久は、結局あかねを見つめたまま口をつぐんでしまう。
「ん〜、なんかリラックスしてないというか…。」
「はぁ、申し訳ありません…。」
「いえ、謝ってもらうようなことじゃないんですけど………そうだ、頼久さん、目を閉じましょう。そうすれば眠くなるかも!」
「はぁ…。」
これはどうあっても眠らないと解放してもらえそうにないと覚悟を決めて、頼久はソファの上に体を完全に仰向けにし、ソファの端からはみ出てしまう足も力を抜いてだらりとさせると、手を腹の上で組んでそのまま目を閉じた。
そうすると、訪れたのは音のない、安らかな暗闇。
頭の下にはほのかに温かなあかねの体温とふわりとやわらかい感触があって、目を閉じたせいでやたらと頭の下のあかねの太腿を意識してしまう頼久の髪をあかねはゆっくりとなで始めた。
あかねの手はなんともいえず心地良くて、頼久はその感触に集中しているうちにいつの間にか眠りに落ちていった。
「う〜ん。」
あかねは重たい瞼を上げた。
なんだか体が横を向いてるようで、頭の下に温かい感触がある。
(あれ?)
寝ぼけ眼をパチパチさせてあかねは目の前に何かがあるのが見えた。
「…………膝?」
見えているのが何かに気付いた次の瞬間、あかねはがばっと身を起こすと自分の頭があった辺りを凝視した。
そこには想像通り人の膝があって、膝の持ち主へと視線を移すとそこには予想通り優しく微笑む頼久の顔があった。
「私………また寝てたんですね…しかも頼久さんの膝で……。」
「はい、よくお休みでした。」
「でもでも、私確か頼久さんに膝枕をしてあげてたはず……。」
「途中で神子殿の方がお休みなったようで、眠りづらそうになさっていましたので横になって頂きました。」
そう言って爽やかに微笑む頼久をあかねは悲しそうな目で見上げる。
「起こしてくださいよぉ……。」
「昼食には起きて頂くつもりでおりましたので。」
「そうじゃなくて……私は頼久さんに寝てもらいたかったんです。それなのに私が寝ちゃうなんて…。」
「寝かせて頂きました。とても心地良く。」
「本当、ですか?」
「はい。」
頼久の満面の笑みを見てやっと安堵のため息をついたあかねだったが、それでもまだ何かが不満らしくうつむいている。
「最初はね、ドキドキしてるんですよ。」
「はい?」
「いつもここにくると、玄関に頼久さんが迎えにきてくれるでしょ?ドアが開いてパッと頼久さんの顔が見えた時ってドキドキしてるんです。でも、それからずっと一緒にいるでしょ?するとだんだん安心しちゃって、それでいつの間にか眠くなっちゃうんですよね…。離れてる時って本当にずっと落ち着かなくて…思ったより疲れてるのかなぁ、私。」
はぁっとため息をつくあかねに頼久はやはり微笑まずにはいられない。
離れていると落ち着かない、予想以上に疲れてしまうほど自分に恋焦がれていると言ってもらえるとは頼久にとってはこれ以上なく嬉しい言葉だ。
「この頼久の側で何一つ不安がないほど安心していただけるとは、何よりも嬉しいお言葉です。」
「お言葉って……もう……。」
いつもの従者口調を注意しようとして頼久を見つめてあかねは息を呑む。
そこにあるのは決して今までの自分を見守るようなどこか保護者のような笑顔ではなくて、心の底から幸せそうな輝くような頼久の笑顔。
そんな顔をしてくれたことが嬉しくて、自分でも気付かないうちにあかねの目には涙が浮かんでいた。
「神子殿、泣いていらっしゃるのですか?」
驚いたのは頼久だ。
自分が何をしたせいであかねが泣き出したのかは全くわからないが、とにかくあかねの目に涙が浮かんだことに驚いて頼久は急に落ち着かなくなる。
腰さえ浮かせかけた頼久に、あかねはふるふるを首を横に振って見せた。
「えっと、これは…たぶん嬉し涙です。」
「嬉しい、のですか?」
「はい、頼久さんが本当に幸せそうにしてくれたから…。」
そう言って今度は微笑むあかねを頼久はそっと抱き寄せた。
自分の幸せを泣くほど喜んでくれる人が愛しくて。
「ええ幸せです。あなたが私の側で幸せであって下さればそれだけで。」
「よ、頼久さんっ!」
腕の中で顔を真っ赤にしてもぞもぞと身じろぐあかねを頼久は腕に力を込めて抱きしめる。
それは本当に幸せな時間で、いつまでも離したくはない頼久とは反対に力いっぱい腕をつっぱって離れたあかねは真っ赤な顔のままほっとため息をついた。
「もぅ、急にこんなことされたら心臓がいくつあってもたりません…。」
赤い顔で少し拗ねている様子のあかねも愛しくてしかたなくて、頼久は笑顔で見つめ続ける。
かける言葉などみつからなくて、ただただ自分が幸せであることを伝えたくて微笑み続ける。
そしてその笑顔の意味はあかねにちゃんと伝わったようで、少しばかり拗ねていたあかねもやがてその顔に微笑を浮かべた。
「お昼ご飯にしましょうか。」
「はい、お手伝い致します。」
二人は台所へと共に立ち上がった。
そしてあかねはエプロンをカバンから取り出して身につけると、きりっとした視線を頼久に向けた。
「お昼ご飯食べたら、また映画観ますからっ!」
「はぁ。」
「今度は絶対寝ないんですからっ!」
「はぁ…。」
「途中で頼久さんにもたくさん意見聞きますから、気合入れて観てくださいねっ!」
何やらやたらと気合の入っているあかねは台所へも凄い勢いで踏み込み、頼久は微笑みながらその後を追う。
「承知致しました。」
そう答えて頼久はあかねの隣に立ち、二人は並んで調理を始めた。
軽く昼食をとった後、あかねがDVDプレイヤーにセットしたのは話題のミステリー映画。
犯人は誰かを二人で予想していけば眠くもならないだろうとあかねが用意したもの。
実は頼久には開始早々犯人はわかってしまったのだが、真剣に意見を求めてくるあかねにわかってしまった犯人の名は告げず、必死に推理する愛しい人が自分で犯人にたどり着けるように慎重にヒントを出し続けるのだった。
映画を真剣に見ていたあかねは、わからぬふりをした頼久よりも先に犯人にたどりついたとひとしきり喜んだ。
そして、あまりに真剣に映画を観てしまったために疲れ果て、結局は頼久の肩にもたれかかってまどろんでしまうのだった。
管理人のひとりごと
うちのあかねちゃんよく寝るなぁ(爆)
つまりは管理人がそういうお昼寝したいだけです(’’)
お日様に照らされてうとうとお昼寝、きもちいいでしょ?
それが頼久さんと一緒だったらそりゃもう最高だろうなと(笑)
管理人が寝不足な分、きっとこれからもあかねちゃんにはよく寝てもらうことになると思います(笑)
プラウザを閉じてお戻りください