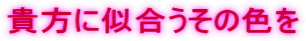
頼久があかねから何とも嬉しい贈り物を頂戴したのは如月の十四日のことだった。
そしてその返礼としてあかねと共に外出したのが弥生の十四日だ。
なるべくあかねが育った世界で行われているのと同じように弥生の十四日つまり『ほわいとでー』を過ごしてほしかったというのが頼久の本音だった。
けれど、弥生の十四日はすっかり頼久があかねに楽しませてもらう結果になってしまったと頼久は自覚していた。
一日の最後には、どんなものよりも高価で嬉しい贈り物が自分の時間だとまで言ってくれたのだ。
そんな心優しくも愛しい妻のために連休を取ろうとしたのが三日前のこと。
いざ休んで妻と共に過ごそうとしてみれば、妻には自分のために仕事を休むのはやめてくれと悲しい顔で言われてしまった。
頼久、一世一代の不覚。
これはなんとか挽回せねばとこの三日、あかねが喜んでくれそうな贈り物を探しているのだが…
自他共に認める朴念仁の頼久にとって、それは左大臣の警護や怨霊との闘いなどとは比較にならないほど難しい仕事になっていた。
こんな時、真の友、天真がいてくれればと溜め息をついたことが一度や二度ではない。
が、その真の友は残念ながらこの京にはいないので、頼久は一人で考えるか、もしくは他の協力者を得るしかないというのが現状だった。
最初に脳裏をよぎったのはいつも艶やかな姿の友雅だった。
彼こそは頼久とはおそらく正反対の人物だろう。
常に身に着けるものが洗練されていて歌もうまく、琵琶も弾けるという風流人だ。
しかも、京中の女性が恋い焦がれているという噂があるほどの魅力的な男性でもある。
友雅に聞けばあるいは、あかねが心から喜んでくれる贈り物を考えてくれるかもしれない。
いや、必ず考えてくれるだろう。
そうとわかっていて頼久が友雅の助力を請おうとしないのは、あかねが頼久の妻になるまでは友雅もあかねに想いを寄せていたのだろうとなんとなく感じていたからだ。
では、他に適任者はと考えてみると…
鷹通ならばあらゆる書物に目を通していて博識だから何か助言は得られそうだが…
鷹通も女性の心理について詳しいかと問われればおそらく頼久と似たり寄ったりというところだろう。
次に頼久の脳裏に浮かんだのは穏やかに微笑む永泉の顔だった。
法親王である永泉が頼久や鷹通以上に女性に贈る物に造詣があるとはとても思えない。
その対である泰明に至っては論外と言っていい。
となると、最後は…
イノリの姿を思い浮かべて頼久は軽く首を横に振った。
いくらなんでもイノリにする質問ではないだろう。
あかねに何を贈ったら喜んでもらえるか?という質問は。
そもそも頼久はイノリよりは遥かに年が上だ。
いくらなんでもイノリに聞くというのはあり得ない。
つまり、今回は頼久一人でこの難問の答えを見つけなくてはならないということだ。
頼久はどうしたものかと苦悩しながら武士溜まりで一人考え続けた。
いくら考えても良い考えは浮かんでこない。
浮かんでくるのは自分に単を贈ってくれた時のあかねの優しい笑顔だけだ。
あの笑顔にふさわしい贈り物は…
そう考えていた頼久の耳にあかねの声が蘇った。
単はあの時、組み紐で飾り付けられていた。
そしてその飾りの説明をする際、あかねは本来は美しい紙で包んだりするものだと言っていた。
ということは、あかねはきっと誰かに何かを贈る際には美しい紙でそれを包みたいのではないか?
紙ならば頼久にも取り寄せることができる。
あかねがどんな色の紙を好むのかはわからないが、とりあえず美しい色のものを集めてみてはどうだろう?
そう思いつくと、頼久はすっくと立ち上がり、真剣な顔で歩き出した。
「頼久さん、お帰りな……それ、どうしたんですか?」
お帰りなさいと夫を迎えようとしたあかねは、その夫が抱えている唐櫃(からびつ)を見て思わず目を見開いた。
綺麗な唐櫃はそこそこの大きさがあるけれど、京の人間にしては大柄な頼久は軽々と抱えている。
「これは、その…あかねへの贈り物、なのですが…。」
「はい?この唐櫃がですか?」
「いえ、中身が、です。」
頼久はそう言うと唐櫃をあかねの前に置いて蓋を開けた。
見るからに重そうな蓋は頼久の大きな手でひょいっと持ち上げられ、あかねの目に飛び込んできたのは色とりどりの紙の束だった。
「紙、ですよね?」
「はい。先日、あかねには単を作って頂きました。私も何かあかねに喜んで頂けるものを贈りたいと思い、探してみたのですが…。」
「そんな!わざわざ手配してくれたんですか?」
「手配したというほどでは…。」
歯切れの悪い頼久の顔をあかねがじっと覗き込んでみれば、頼久は小さく溜め息をついた。
「あかねも知っての通り、私は男ばかりの武士団で育ちました。母も幼くして亡くしておりますし、姉妹もおりません。」
「はい、それは前に聞いたことあります。」
「つまり、私の生家には男ばかりが、しかも武術一辺倒の朴念仁ばかりがいるのです…。」
「えっと…それとこの紙とはどうつながるんですか?」
「あかねは先日、私の単を本当は綺麗な紙で包むとおっしゃっていました。ということは、美しい色の紙ならばお喜び頂けるのではと考えまして…。」
「それは確かに、綺麗な紙は普通、女の子なら誰でももらえば嬉しいですけど…。」
そこまで言ってあかねは唐櫃の中へと視線を戻した。
中に詰まっているのは色とりどりの紙の束。
綺麗な紙は女性なら誰でも嬉しくないことはないだろうし、特に京では紙は貴重だ。
貴族の女生ともなれば手紙一枚書くための紙にもセンスが求められるということをあかねも友雅に学んだ。
だから、綺麗な紙は貴重だし、嬉しい贈り物ではある。
あるのだけれど…
「すごい量ですよね、これ。」
「はい。実は我々もお仕えしている主から褒美として紙を頂くこともなくはありません。ですが、男所帯では…。」
「綺麗な紙を使う機会があまりない、ですか?」
「はい。そのことを思い出し、使わぬ紙があったら皆送って欲しいと頼んだところ、この量が…。」
「なるほど、もらっても誰も使わないから唐櫃一個分もたまっちゃってたんですね。」
「そういうことです。見つからなければ入手に時間はかかりますが買い求めようと思っていました。ですが、よもや、これほどの量が手配できるとは思っておりませんでした。」
綺麗な色に染められている紙でも、大量に唐櫃に詰め込まれていると、それはそれで風流からはかけ離れた見た目になっている。
これが無骨者である自分の限界かと頼久が溜め息をつくと、あかねは唐櫃から紙を一枚取り出してにっこり微笑んだ。
「嬉しいです。これなんて、頼久さんの好きな色ですよね。」
「はぁ、確かに。」
「こんなにいろんな色の紙がそろってることなんてめったにないですもん。これなら誰にどんな手紙を書く時も安心です。」
「そう、でしょうか…。」
「はい。次に頼久さんに贈り物する時はこの紙でかわいくラッピングできそうですし、藤姫にもかわいく何か包んであげられそうだし。嬉しいです。」
「あかね…。」
柔らかく微笑むあかねにつられるように頼久の顔にも笑みが浮かんだ。
「この中から選べば、友雅さんにだって褒めてもらえる紙が選べそうです。」
「……。」
一瞬、頼久の脳裏を艶やかな左近衛府少将の顔がよぎった。
同時に頼久の眉間にシワが寄るのはもう反射のようなものだ。
頼久の様子が一変したことに気付いてあかねが小首をかしげると、頼久は一つ深呼吸をして気を取り直した。
「あかねからの文であればどのような紙に書かれていようとも、皆喜びます。もちろん私もです。」
「じゃあ、頼久さんがお仕事で何日か屋敷にいない時は文を書いてもいいですか?」
頬を赤くして尋ねるあかねに思わず頼久はきょとんとしてしまった。
この人は何を聞いているのだろう?
文を書いてもいいか?という問いの答えなど決まっている。
「もちろんです!」
思わず大きな声で頼久が答えれば、あかねはクスッと笑ってから「はい」と嬉しそうにうなずいた。
この日以降、頼久の元には長く屋敷を空けることになる仕事の際には、必ず愛妻から文が届くようになった。
そもそも夫婦仲がいいことで有名だった若棟梁とその若妻が文のやりとりまで始めたと武士団の面々が幸せな噂話を始めるのに時間はかからなかった。
そして、その話を聞きつけた頼久の父が更に唐櫃一個分の紙をかき集めてあかねに送ってきたのは一月後のことだった。
管理人のひとりごと
先日のホワイトデー短編が長くなったのでカットされた後日談です(^^;
頼久さんが考えた贈り物は紙でした。
枕草子なんかで書いてあるように、平安時代は紙が貴重品でした。
だからこそ、綺麗に染められていたりして、身分の高い人が使ってたりしました。
そうじゃない紙ももちろんありましたが…その話をすると長くなるのでやめましょう(’’)
ブラウザを閉じてお戻りください