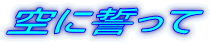
自称海賊船の上で生活することになって数ヶ月。
千尋もすっかり船上での生活に慣れてきた。
船酔いしたらどうしようとか、実はけっこう不便だったりするのでは、とか色々心配もしたのだが、そんな心配は何一つ必要なかった。
何かちょっとでも不自由があると思えばすぐに日向の仲間達が解決してくれたし、千尋はあまり船酔いをしない体質らしかった。
結局のところ、あっという間に船の生活に馴染んで、けっこう楽しくやっていたりする。
仲間達はみんな愉快で親切だ。
カリガネの作ってくれる料理やお菓子は最高においしい。
たまに教えてもらったりもしている。
だから千尋も意外と忙しくしているのだが…
それでも最近では船での生活にもすっかり慣れて、ふと時間が空く瞬間ができてきた。
そうなると、今までは気にもしなかったことが気になるようになった。
何が気になるかといえば、サザキだ。
自分のことでいっぱいいっぱいだった頃は自分とはなれている間、サザキが何をしているかなんて気にならなかった。
それなのに今は、ふと気付くとやることがない時間はいつもサザキの姿を探してしまっていた。
現に今も、千尋は自分の部屋の掃除を終えるとやることがなくなって、甲板に出てサザキを探していた。
千尋が甲板の片隅でキョロキョロと辺りを見回してみると、サザキの姿はすぐに見つかった。
サザキは笑っていた。
大勢の仲間達に囲まれて、とても楽しそうに笑っていた。
昨日もサザキを見つけたときは仲間と一緒に楽しそうに笑っていた。
よくよく思い出してみればサザキの笑っている以外の顔はあまり見ていない気がした。
仲間と一緒にいるサザキはたいていの場合、楽しそうに笑っている。
でも、よく考えてみると、自分といる時はそうでもないような気がしてきて…
千尋がなんだか苦しくなって視線を外そうとしたその時、ずっとむこうにいるサザキが千尋を見つけた。
今まで仲間達と楽しそうに話をしていたサザキは千尋を見つけるとぱっと嬉しそうな顔をして千尋のもとへ駆けてきた。
千尋が驚いて目を丸くしていると、サザキはあっという間に千尋の前に立ってそれから急にその顔から笑みを消すとおどおどと千尋から視線を外した。
「ひ、姫さん、部屋の掃除、終わったのか?」
「うん、終わったよ。」
「そうか。」
そうして訪れる沈黙。
最近、サザキとはこうして会話が途切れて、いづらい空気になることが多かった。
千尋はいつもと同じようにしているつもりなのだが、サザキの様子がおかしいのだ。
明後日の方を見てぽりぽりと頭をかくサザキを見上げながら、千尋は溜め息をついた。
「サザキは何をしてたの?」
「あ?オレか?オレはその…何って、別に何かしてたってわけじゃねーんだ。ただ、仲間とじゃれてたっつーか…。」
「うん、楽しそうだった。」
「み、見てたのか?姫さん。」
「ちょっと見かけただけ。」
「お、おう。」
また二人の間を埋める沈黙。
千尋がサザキの表情をうかがえば、サザキはやっぱり目を合わせてはくれなくて、頭を書きながらなんだか遠くを見ている。
最近サザキと目を合わせて話をしていないことに気付いて、千尋はまた小さく溜め息をつくとその顔に儚げな苦笑を浮かべた。
「私、部屋に戻るね。」
「お、おう。」
サザキの返事を待たずに静かに歩き出す千尋。
サザキはそんな千尋の背中にようやくまっすぐな視線を向けた。
すると、歩み去る背中はなんだか少し小さくなったように見えて…
呼び止めて話をしたい気持ちと、呼び止めてもまともには話せないだろうという思いとの間でサザキが揺れ動いている間に千尋の小さな背中は扉の向こうへと消えていった。
サザキは頭をゴリゴリとかきながら深い溜め息をついてもといた仲間達の元へ戻ろうと歩き出し…
視線の先にいる仲間達がジト目で自分を睨んでいることに気付いた。
「な、なんだ、お前ら…。」
「お頭がそれだからまとまるものもまとまんねーんで。」
「ああ?」
「そうそう、お頭は姐さんのこととなるとてんでダメなんだ。」
「お前らなぁ…。」
仲間達に散々な言われようでサザキがあきれていると、そこへぬっと長い腕が伸びてきた。
手の上にはなにやら包みが乗っていて…
サザキが手の主へと視線を移すとそこには不機嫌そうなカリガネが立っていた。
「な、なんだ?」
サザキがそう聞いてみてもカリガネはただ黙ってぐいっと包みをサザキに押し付けた。
その包みからは香ばしい焼き菓子の香りが漂っている。
「お、おい…。」
不機嫌そうな顔をしているくせにサザキに焼き菓子の包みを押し付けたカリガネは何も言わず、そのまま船室の方へと姿を消した。
サザキは香ばしい包みを手に小首を傾げる。
そんなサザキにさっきまでお頭をジト目で睨み付けていた日向の男達は深い溜め息をついた。
「お頭、それ、前に姐さんがうまいって感動してた菓子ですぜ。」
「だ、だからなんだ…。」
「姐さん、さっき寂しそうな顔してたじゃねーですか、それ持っていってご機嫌とってこいってことじゃねーんですか?」
そんなこともわからないのかと仲間達に睨まれて、サザキは「うっ」とうめき声をあげた。
確かにさっきの千尋は少し様子がおかしかった。
いや、さっきだけに限ったことじゃない、最近の千尋は少し寂しそうにしていることがあるのだ。
それに気付いてはいても、サザキにはなにをしてやることもできなくて…
「さらってきたんなら最後までちゃんと面倒見るのが男ってもんですぜ?お頭。」
「お、お前らに言われなくてもな、わかってんだ!んなことは!」
思わず大声でそう言って、サザキは足音も高らかに歩き出した。
向かうはもちろん千尋の部屋。
何か用事がなければめったに訪れることはないが、今はカリガネの焼き菓子を届けるという用がちゃんとある。
ついでに千尋と少し一緒に過ごしても別におかしくはないはずだ。
そんなことを考えながらサザキは船室へと向かった。
千尋は部屋で膝を抱えて座っていた。
掃除が済んでしまうと何もすることがなくて。
夕飯を作るのは手伝おうとは思っているけれど、それまでにはまだずいぶんと時間があって…
でももう甲板へ出て行く気にもなれない。
そこにはサザキがいるとわかっているけれど、結局、仲間と楽しそうにしているサザキを見ることになるだけで、二人で話をしようものならまた気まずくなったりするのだ。
そう思うと悲しくて、千尋はぎゅっと自分の膝を抱きしめた。
きっと誰かに暇だからと言って話しかければ日向の男達はみんな快く千尋の相手をしてくれる。
そうとわかっていても千尋はそうする気にもなれなかった。
サザキ以外の誰かと話していても結局、寂しくなってしまうだけだとわかっていたから。
何をしても無駄だとあきらめて千尋が深い溜め息をついたその時、扉の向こうに人の気配がした。
「姫さん、いるか?オレだ、サザキだ。」
「いるよ。」
驚いて千尋が返事をするとゆっくり扉が開いて向こうからサザキが顔を出した。
「入ってもいいか?」
「え、うん、もちろん。」
サザキはゆっくり部屋の中に入って扉を後ろ手に閉めると、やっと正面から千尋を見つめた。
膝を抱えて座っている千尋はやっぱりいつもとはちょっと違って儚げで…
サザキは軽く深呼吸をすると千尋の隣に座ってカリガネから渡された包みを差し出した。
「何?これ。」
「カリガネがな。」
抱えていた膝を解放して、サザキから包みを受け取った千尋はその包みを開いてすぐににっこり微笑んだ。
「完成したんだぁ。この前、カリガネに試作品を食べさせてもらったの。凄くおいしかったんだ。」
そう言って千尋は嬉しそうに焼き菓子を口に入れた。
そんな千尋の横顔を見て、サザキは深い溜め息をついた。
「サザキ?」
「その…なんだ……姫さんは、船の生活、飽きたか?」
「そんなことないけど…どうして?」
「いや……最近、つまんねーって顔してることがあるから、な。」
「つまんないなんてことないよ?みんな楽しい人ばっかりだし…。」
そういいながらも千尋の声は沈んでいって、その視線もうつむいてしまった。
「ほら、そんなふうにな、つまらなそうにしてることがあるんだよな、最近。」
「これは別にここの生活がつまらないってわけじゃなくて…。」
「じゃぁ、なんか不自由してることあんのか?」
「それもないよ。みんな親切だし…。」
そう言ってやっぱり千尋はうつむいてしまう。
サザキは頭をぽりぽりかいて、それからあきらめたように溜め息をついて天井を見上げた。
「オレはカリガネみたいにはできねーからなぁ。」
「何が?」
「姫さんの好きなもん作ってやったりとかそういうの、できねーからな……なんていうか、さらってきちまったのになんにもしてやれてねーっつうか…。」
そこまで言ってサザキは深い溜め息をついた。
「サザキは…仲間といると凄く楽しそうだから、羨ましいって言うか、私なんかいなくても楽しいんだなとか、そう思ったりとかして寂しくなったりとかしてるだけで…別に私、ここの生活がつまらないとかそんなこと思ってないよ?カリガネのお菓子は大好きだけど、別にサザキに同じもの作ってほしいって思ってるわけじゃないし…。」
千尋がそう言ってちらりとサザキを見ると、サザキはキョトンとした顔で千尋をじっと見つめていた。
目をまん丸に見開いてサザキは微動もしない。
「サザキ?どうしたの?」
「……それは……なんだ、その、なんつーか…姫さんはあいつらに妬いてたのか?」
「や、妬いてたっていうか……そう、なるのかなぁ…。」
「姫さんがあんなやつらに妬くことなんか……。」
「それはっ!だってサザキは私といるとたまにいづらそうにするけど、みんなと一緒にいると凄く楽しそうなんだもん。」
千尋の言葉を聞いたサザキは再び目を見開いて凍りついた。
その様子があまりに大仰に見えて、千尋も目を見開いて小首を傾げる。
どうしてこんなにサザキが驚いているのかがわからない。
「サザキ?」
「それはだなっ!」
「うん?」
「オレはその…別にあいつらと一緒にいる時の方が楽しいってわけじゃなくてだな…。」
「うん。」
「その…姫さんといるとその…楽しいし嬉しいんだが…どうしたらいいかわかんねーというか…。」
「みんなといる時と同じように話したり笑ったりしてくれるだけで嬉しいよ?」
「いや…あいつらと姫さんとはその…全然違うんだ、オレにとっては…だから、オレは姫さんのことは大事にしたいし、いつも笑わせてやりたいし、幸せだって思っててほしいしだな…そういうのを考えるとどうしたらいいかわんねーというか…何言ってんだ、オレ……。」
サザキは説明をあきらめて深い溜め息をついた。
最近はどうしても千尋の前だとこんなふうになってしまうのだ。
言いたいこともまともに言えない。
言葉一つ一つでさえ、千尋に向けて言うのだと思うと大切で。
その言葉で傷つけたりしないか心配で。
「サザキ、有難う。私が誤解してたんだね。」
「姫さん…。」
「サザキが私のことを大切にしてくれてるんだってよくわかったから。だから、あんまり気を使わないで?私はサザキが元気で楽しそうにしてるのが一番嬉しいよ。」
「お、おう。」
「それに、みんなにするみたいに私にしてもいいんだから、ね。」
「いや、それは…。」
「私もみんなみたいにサザキの仲間になりたいもの。」
「……それは、だな……だから、姫さんは仲間以上、だからな。」
千尋が小首を傾げるとサザキは困ったように苦笑して頭をかいた。
「ん〜、じゃぁ、仲間以上に仲良くしてくれなきゃ。」
千尋がそう言ってやっと以前のように愛らしく微笑むのを見て、一瞬見惚れたサザキは何かを必死に決意したような顔で千尋に腕を伸ばした。
何をする気なのかと千尋が不思議に思っているうちにその腕に抱き寄せられて、千尋はすっぽりサザキの腕の中におさまった。
「仲間以上に仲良く、な。」
「へ、あ、うん、そう、だね。」
どうやら緊張しているらしいサザキの声にクスッと笑って、千尋は幸せいっぱいの笑顔でサザキを見上げた。
すると真剣な顔のサザキが近づいてきて…
千尋はそっと目を閉じた。
ふっと唇が温かくなって、すぐにそのぬくもりがなくなって…
千尋が目を開けて微笑もうとするとその頭をさっとサザキに抱え込まれてしまった。
「サザキ?」
「は、恥ずかしいんだ、今は見ないでくれ。」
千尋は頭上から降ってきたサザキの声にクスッと笑って、その胸に顔をうずめた。
本当にきっと顔を真っ赤にしているんだろうなと想像するとなんだか凄くサザキが可愛くて、そんなに恥ずかしいことをしてくれたのが嬉しくて。
「仲間以上に仲良く、だからな。」
「うん、嬉しかった、有難う。」
千尋が優しく言うその声をしっかりと抱きしめて、サザキは呼吸を整えた。
次に千尋が自分を見る時には優しく笑っていられるように。
二度と千尋が仲間達に妬いたりしなくて済むようにしなくては。
サザキはそう思いながら千尋を優しく抱きしめた。
管理人のひとりごと
かかりっきりで3日かかった!(マテ
4の短編中、今回最も時間がかかった!
管理人は頑張ったっ!(っдT)
しかも長い…
でもサザキにはやっとやることやってもらいました(’’)←達成感
ああ、でもこの方、プロポーズ大作戦がまだ残ってた…
サザキさんの糖度上げるのは本当に苦労します(、、)
少年のイメージ崩したくないしなぁ…
ひとえに管理人の筆力が足りないせいと思われますが…
精進します(っдT)
プラウザを閉じてお戻りください