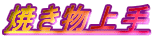
年に一度の楽しい行事は一年のうちに何度かあるけれど、この日ばかりは風早もさすがに気合が入っていた。
これ以上に気合が入るのはきっと千尋の誕生日くらいのものだろう。
こちらの世界の風習ではこんな行事は存在しないから、忍人辺りには何を騒いでいるのかと眉根を寄せられたが、そんなことはどうだっていい。
とにかく千尋に喜んでもらわなくてはということだけが風早の頭の中にあった。
何故なら、今日は3月14日。
そう、千尋の記憶にあるこの世界とは異なる世界ではホワイトデーと呼ばれる恋人達にとってはとても大切な日なのだ。
人の身になってしまってからは千尋のためにできることがぐんと減ってしまったような気もしている風早が、千尋のためにと想いを形にして贈るべき数少ない日でもある。
ということで風早は一ヶ月前から気合が入っていた。
千尋から嬉しいバレンタインのプレゼントをもらってから、風早は千尋を喜ばせるための計画を練りに練り、そして準備を進めてきたのだ。
異世界だったらクッキーを贈ったりケーキを買ってきたりできただろう。
けれどこの世界でそれは不可能だ。
それでも千尋は風早のためにおいしいお菓子を作ってくれた。
であればこそ、風早も一寸たりとも手を抜くことは許されない。
真剣にデザインし、丁寧に作り上げた焼き物の器に風早は満足そうに一つうなずいた。
それは一週間をかけて風早が手作りした本日の贈り物用の器だ。
素焼きだから綺麗な色のものにはできないが、それでも千尋がたぶん喜ぶだろうハートの形を再現することには成功した。
自分の想いをこめた形に仕上がったことに満足して、風早はその器に今度は贈り物を詰め始めた。
こちらも一ヶ月前から風早が研究し、試作を重ね、本日完成したばかりの焼き菓子だ。
ホワイトデーといえばクッキーやキャンディをお返しに贈るのが風早の中の相場だったが、この世界にそれはない。
だから自作したというわけだ。
綺麗な髪飾りや服を贈るのもよかったのかもしれないが、そういう大仰なものは千尋があまり喜ばない気がした。
王の妹姫という立場であっても千尋の控えめで優しいところは少しも変わっていないのだ。
だから、風早は全てを心をこめて手作りすることに決めたのだった。
贈り物の価値は高価かどうかではなく、贈り主の気持ちがこもっているかどうかが勝負。
千尋ならばこそ、贈り物の価値をそこに見出すだろうと風早は確信していた。
だから、一ヶ月という時間をかけて手を抜くことをせず、全て自分で考え、自らの手で作り上げたのだ。
ハート型の器に焼き菓子を詰め込んで、満足そうにできばえを眺めた風早はそれをかかえて部屋の外へ出た。
けれど、向かったのは千尋の部屋ではない。
茶色の器に茶色の焼き菓子を詰め込んだだけではなんとも見栄えがよろしくなかったのだ。
千尋に喜んでもらうためにはもう一工夫が必要だろうと、風早は器を抱えて表へ出た。
少し歩けばきっと春の花が見つかるだろう。
これに春の花を飾り付ければ、風早がイメージしている完璧な贈り物になるはずだった。
だから、花を求めて歩く風早の足取りはとても軽かった。
千尋は不安げな顔で一人、部屋の中にいた。
窓の外はもう夕暮れ。
しかも今日は3月14日。
たとえこの日の意味を風早が忘れていたとしても、ただ二人でいるだけだって千尋はかまわなかった。
でも、一人で過ごすことになるなんて思ってもみなかった。
朝、いつものように顔を見せてくれた風早は何やら用事があるとかで、仕事の補佐を柊に依頼するとそのままどこかへ行ってしまった。
3月14日は千尋にとってはホワイトデーという大切な日だった。
どうしても風早と二人で過ごしたいと思う一日だ。
それなのに朝から風早はずっと顔を見せなくて、柊と二人で仕事を終えてからは一人きりだった。
窓の外の夕日は今にも山の向こうに消えてしまいそうで、千尋は小さく溜め息をついた。
夜まで一人きりで、そのまま一人で眠りにつかなくてはならなかったらどうしよう…
そこまで考えて風早を探しに行こうと決意して千尋が立ち上がったその時、部屋の扉がコンコンと二つノックされた。
ノックという習慣がないこの世界でこんなことをするのはただ一人、風早だけだ。
千尋は飛ぶように扉に駆け寄って、勢いよく扉を開けた。
「うわっ、千尋…驚きました…。」
「風早…。」
いつものように穏やかな顔で立っている風早を見て、千尋は思わず涙ぐんでしまった。
その様子に気付いて風早が目を丸くする。
「千尋?どうかしたんですか?」
「なんでもないの、それより風早の用事はすんだの?」
「ああ、それは…どうぞ。」
「へ?」
風早が自分の方へ何かを差し出したのに気付いて千尋は小首を傾げた。
風早の手にあるのはハートの形をした素焼きの器。
千尋はぱっと顔に明るい笑みを浮かべてそれを受け取ると、風早を部屋の中へといざなった。
「風早、これ、もしかして…。」
「はい、バレンタインのお返しです。」
「覚えててくれたんだ…。」
「当然です。」
「有難う、忘れてるんだと思ってた…。」
そう言って千尋はハート型の器を抱きしめた。
「千尋?ひょっとして俺がホワイトデーを忘れてるんじゃないかって、それが心配だったんですか?」
「心配っていうわけじゃないんだけど…その…今日は一緒にいたかったなって思ってて……。」
「すみません、気がつかなくて…それを用意することにばかり気をとられて、千尋に寂しい思いをさせてしまいましたね。」
「ううん、これ、とっても嬉しい。有難う。」
心配顔の風早に笑顔を見せて、千尋は器のふたを開けた。
するとそこには、小さな花で飾り付けられてこうばしい香りのする焼き菓子が詰まっていた。
「うわぁ、おいしそう、有難う、風早。」
「いえ、焼き物の器に焼き菓子を入れたらいろどりが悪くなってしまって、それで花を探している間にこんな時間になってしまったんです。すみませんでした。」
「そんな、気にしないで、凄く嬉しいから。」
千尋はしゅんとし続ける風早の前で焼き菓子を一つ口に入れた。
甘さは控えめで少し歯ごたえのあるその焼き菓子はとてもおいしくて、千尋の顔には自然と笑みが浮かんだ。
「おいしい。これ、風早が作ってくれたの?」
「ええ、口に合って何よりです。」
「ほんと、風早って器用だね。こういうの作るのは私よりずっと上手…なんていうか……複雑な気分…。」
「どうしてですか?」
「それは……その……お嫁さん失格というか…なんというか…。」
真っ赤な顔でそう言う千尋の手から風早はそっと焼き物の器を取り上げて机の上に置くと、千尋の体を優しく抱きしめた。
「そのお嫁さんの相手が俺だという想定だと嬉しいんですが。」
「風早に決まってるじゃない!風早が私より何でも上手だから気になるんだから……。」
「それなら心配いりませんよ。千尋が苦手なことは俺がみんな代わりにやりますから、問題ありません。」
「そ、それはそれでちょっと…。」
情けない気がする。
と胸の内でつぶやきながら、千尋は風早の腕の中で更に顔を赤くした。
「千尋は何も心配しなくていいんです。ただ、俺のことを好きでいてくれたらそれだけで俺はじゅうぶん幸せなんです。」
「そんなの…好きに決まってるよ…だから、それ以上にちゃんと風早のお嫁さんにふさわしくなりたいの。」
そう言って千尋が視線を上げれば、風早の溶けるようなやわらかな眼差しにぶつかった。
「千尋はもうじゅうぶんふさわしいですよ。俺のお育てした姫に間違いはありません。」
「それってお父さんみたい…風早は…。」
「恋人、でしたね。」
幸せそうに微笑んで耳元で囁かれてはもう千尋は顔を赤くするしかない。
抱きしめられて髪を優しく撫でられて…
千尋ははっと何かに気付いたように慌てて風早から体を離すと、きりっと風早を見上げた。
「千尋?」
「だから!私は子供じゃなくて恋人なの!風早のお嫁さんになりたいの!風早といるとついついあまえちゃう…このままじゃ全然お嫁さんぽくなれないから、明日から花嫁修行することにする!」
「は?」
「料理とか裁縫とか練習する!」
「それは…。」
「絶対するから!姉様が結婚するまでにちゃんと花嫁らしく色々できるようになる!」
千尋はガッツポーズさえ決めそうな勢いで宣言した。
風早にしてみれば何一つできなくたって千尋がそばにいてくれるだけでいいのだが、千尋がそれをよしとするわけがないことも承知だ。
だから、千尋の言葉に逆らうことはせずに、風早は再び千尋の体を抱きしめた。
「風早?」
「花嫁修行は明日から、ですよね?」
「え、うん、そのつもりだけど…。」
「その修行には俺も付き合いますから、今はもう少しだけこうしていてください。せっかくのホワイトデーですしね。」
「……うん。」
どんな時も安心させてくれる広い胸。
優しい腕。
そして聞こえる鼓動とぬくもり。
千尋は風早にされるまま抱きしめられて、その胸に頬を寄せて目を閉じた。
花嫁修行は頑張るつもりだけれど、こうして風早に甘えることもやっぱりやめられそうにない。
少しずつ暗くなっていく部屋の中で、千尋は風早の腕の中、いつまでもうっとりと目を閉じていた。
そして風早は、そんな千尋を幸せそうな笑顔で抱きしめ続けた。
管理人のひとりごと
焼き物に焼き物つめたらまっ茶色、みたいな?(マテ
風早はそういうところに気がつくので花を一緒に詰め込んでみましたよと。
そしたら時間がかかっちゃいましたと(’’)
柊に補佐を頼んだりしたら横取りされますよ?とか思いつつ書いてみました(コラ
で、千尋ちゃんの場合、風早のお嫁さんになるに際して花嫁修行は全く必要ないと管理人は思います。
だって、光源氏計画でしょ?(マテマテ
千尋ちゃんって絶対風早の好みの女性に育てられてると思うんだ(’’)
ブラウザを閉じてお戻りください