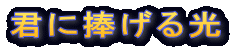
千尋は小さな灯り一つともっただけの自分の部屋で深い溜め息をついた。
一年の終わりを見送り、新しい年を迎えるための準備は朝から続いて、そのまま宴へとなだれ込んだ。
おかげで王族である千尋はあちこち引っ張りまわされ、貴族との挨拶、他国からの使者との謁見などなど…
全く休む暇もないまま宴の終了を迎えた。
終了とはいっても、一度なんとなくお開きという形をとっただけで、まだ飲み続けている男達が広間には大勢いるはずだ。
王族、特にその中でも女性は早めに休むことをやっと許されてこうして千尋も夜中に自室へ戻ってきたところだった。
宴は盛大で、酒を酌み交わす人達はみな平和そうだった。
それはそれでとても嬉しいことだし、大切なこと。
そうとわかっていても千尋は溜め息をつかずにはいられなかった。
王である姉もそうだが、宴の最中は王族であることが最優先。
王族として挨拶を受け、挨拶を返す。
そんなことが延々と続いたから、王族である姉妹は愛しい人と共に宴を楽しむことは全くできなかった。
それでも警護と称して風早が側近くではないにしても千尋の視界に入るところで微笑みながら見守っていてくれた分、千尋の方がまだ恵まれていたかもしれない。
風早は酒と料理で上機嫌の岩長姫の誘いを断ってまで千尋を遠巻きに見守ってくれていたのだ。
忍人や柊は岩長姫につかまって今も飲んでいるはずだし、風早も千尋が自室へ戻った以上はたぶん岩長姫に捕まっているだろう。
そして姉の恋人である羽張彦はというと、これまた当然のように岩長姫や同門の面々と酒を酌み交わしていた。
きっと今頃は酔いつぶれてしまっているだろう。
つまり、中つ国の王とその妹は、一年に一度の一大イベントのこの日に、全く恋人と二人の時間を過ごせなかったというわけだ。
千尋はもう一度盛大に溜め息をつきながら窓を開けた。
すると冷気がすっと流れ込み、千尋は自分で自分の肩を抱いた。
もうすぐ窓から見える遥か向こうの山際に新しい年の一番初めの陽が昇るはずだった。
中つ国では除夜の鐘は聞けないけれど、せめて初日の出は風早と一緒に見たかった。
そんなことを考えてしまって、千尋の溜め息は止まらない。
今からでも宴の席に顔を出してみようか?
そうすれば風早の顔をちらりとでも見られるんじゃないだろうか?
いや、みんながくつろいで酒を楽しんでいる席に王族の自分が顔を出してはきっと迷惑だ。
なら、無理やり風早を呼びつけてしまおうか?
風早ならきっと駆けつけてくれるはずだ。
でも、そんなことをしてわがままな恋人だとは思われたくない。
千尋は暗い空を見上げながら今日何度目になるかわからない溜め息をもう一度ついた。
脳裏に浮かぶのはいつだって自分を守ってくれる風早の顔ばかり。
会いたいと一度思ってしまうともう止められなくて…
千尋は目にうっすらと涙を浮かべた。
「風早…。」
無意識のうちにその名を口にして、以前、名を呼べば必ず駆けつけると、そういってくれた風早の言葉を思い出した。
そして…
「呼びましたか?」
「へ?」
背後から声が聞こえて千尋が振り返ると、そこには苦笑を浮かべている風早が立っていた。
「風早?へ?私が呼んだのが聞こえたの?だから来てくれたの?」
もう麒麟ではなくなった風早にそんな力はないとわかっていても、千尋はそう尋ねずにはいられなかった。
慌てて入り口の方へ駆け寄って、まっすぐに風早の顔を見上げる。
「いえ、どうしても千尋の顔が見たくてこっそり来てみたら千尋の声が俺の名を呼んでくれたのが聞こえたので、思わず扉を開けてしまいました。すみません。」
「そんなの!全然気にしないで!」
そういいながら千尋は風早の腕を引っ張って中へ入れると、パタンと扉を閉めてしまった。
こんなところを誰かに見つかって風早を取り上げられるなんてごめんだ。
「こんな時間に不謹慎かとも思ったんですが…。」
「ううん、私も会いたかったから凄く嬉しい。」
千尋は思い切り風早に抱きついて深呼吸をした。
ただひたすら会いたいと思っていた人はとても温かくて…そして、その体からはほのかに甘い香りがした。
「風早?」
「はい?」
「なんか凄くいい匂いがする…。」
「いい匂い、ですか?」
千尋が体を離して風早を見上げると、風早は何のことかと小首をかしげていた。
甘い香り。
さっきまで風早がいたのは宴の席。
この二つから千尋が導き出した答えは…
「風早、ひょっとして宴の席で女の人と一緒にいた?」
「女の人…という表現はちょっと抵抗があるんですが…まぁ、先生に捕まっていました。」
「そうじゃなくて…その……お酒をついでくれる綺麗な女の人、とか…。」
「ああ、千尋は何か誤解してますね、あの宴の席を。」
「誤解?」
「あそこにいるのは武人と先生と、先生の弟子だけですよ。最初は他にもいたのかもしれませんが、俺が連行された時にはもうそんな面々しか残ってませんでした。だからいい匂いがするような女性はいなかったんです。いい匂い…ああ。」
「何?なんの匂いか思い出した?」
「たぶん酒の匂いですね。」
小首をかしげる千尋にそういって風早は苦笑した。
言われて千尋がよくよく風早の顔をのぞいて見れば、確かにほんのり頬が赤く染まっている。
「お酒ってこんな匂いした?」
「今日は一年に一度の盛大な宴なので上質な酒が出されていたそうで…俺はあまり酒の味はわからないんですが、先生は上機嫌でしたよ。」
「そうなんだ。じゃぁ、上質なお酒って花みたいな甘い香りがするんだね。」
「そうみたいですね。」
「よかった…。」
ほっと安堵の溜め息をついて千尋は改めて風早にしっかり抱きついた。
「よかったって…もしかして千尋は俺が綺麗な女性に囲まれて浮かれていたとでも思ったんですか?」
「そ、そういうわけじゃないけど…。」
「じゃぁまさか、俺が浮気をしたとでも?」
「思ってない!」
「心外です。」
「思ってないから!」
「でも今よかったと言ったでしょう?」
「それは…だって、風早のことは信用してるけど、やっぱり私が風早に会えない時に側に綺麗な女の人がいるなんて…なんか嫌なんだもん…。」
そう言って風早にギュッと抱きつく千尋を今度は風早も優しく抱きしめ返した。
たったそれだけのことで不機嫌になってくれる千尋がなんともいとおしい。
「俺はいつだって千尋のことしか考えてませんよ。それに…。」
「それに?」
「しばらくは側にいますから。」
「本当?」
「はい。千尋と一緒に初日の出を見たいと思ってたんです。千尋がもう眠っていたら日の出を待って起こそうと思っていたんですよ。」
「私も!私も風早と初日の出が見たいなって思ってたの。」
嬉しそうに千尋が風早を見上げて微笑むと、風早の幸せそうなニコニコ顔が急に近づいて、あっという間に千尋の唇には優しい口づけが降りてきた。
「風早…。」
「酒臭かったですか?」
「ううん、凄く甘くて素敵な香りがした。」
「ならよかった。」
「本当に朝までずっといてね?」
「はい。新しい年を迎える一番最初の新しい光を千尋に贈りたいので、何があってもこのまま側にいます。」
「うん。」
嬉しそうにうなずく千尋にもう一度軽く口づけて、風早は千尋と二人、窓辺に座った。
まだ窓の向こうは暗闇に閉ざされているし、開け放たれた窓からは冷たい空気が流れ込んでいる。
けれど、千尋の小さな体を抱きしめていれば寒さなんて感じない。
千尋にも感じさせたりはしない。
平和と安らぎと、この先も二人でい続けることができる喜びと…
そんな幸せの全てが詰まった朝陽を千尋に贈るそのために、風早は千尋の体を優しく抱きしめて空のかなたに昇る朝陽を待った。
管理人のひとりごと
まぁ、あの世界でどんな年越ししてるかはわからないので想像で!
王族だからね、千尋ちゃんは。
たぶん宴だ宴!ってな感じで色々行事があるはず。
占いとか神様系の何かもあるかもしれないなと思いつつ、甘くない行事は省略(’’)
風早の方がね、千尋と一緒にいようと努力すると思うんですよ、羽張彦よりは。
風早はお酒弱いから酒宴より絶対千尋の方が大事!
でも羽張彦は酒とか好きそう(っдT)
一ノ姫と同じくらい好きそう…と思う管理人(マテ
だから、風早は酒の席から逃れて千尋と二人きりの初日の出♪となりました\(^o^)/
風早、千尋と同様、皆様にとっても幸せな一年となりますように(^−^)
ブラウザを閉じてお戻りください