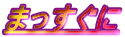
千尋は腕を伸ばして「うーん」と声を出しながら伸びをした。
朝からの政務が終わってやっと一息ついたところだ。
太陽は辺りを燦々と照らしている。
どうやら日暮れ前に仕事が終わったらしいとわかって千尋は微笑んだ。
「お疲れ様でした。」
そういいながら千尋の前にお茶の入った小さな器を置いてくれたのはもちろん風早だ。
朝からずっと政務に付き合ってくれていたこの恋人は、仕事が終わったまさにその瞬間、絶妙なタイミングでお茶を出してくれた。
「有難う、風早。」
「今日は早く終わりましたね。」
「そうだね。まだ日も高いしどうしようかなぁ。」
お茶を手に千尋が楽しそうに微笑んだ。
その視線は窓の外へ向けられている。
明るく晴れ渡った外の景色は心地良くて、どこへだって出かけて行きたい気分だろう。
そんなふうに想像しながら風早はただじっと千尋を見つめた。
千尋が心地いいと言ってくれる、千尋が楽しいと言ってくれる、千尋が幸せだと言ってくれる。
ただそれだけで風早は満足だ。
だから、どうすれば千尋が楽しんでくれるのか、安らいでくれるのか、そればかりを考えている。
風早は今も、千尋の表情をうかがいながら、どんな休日の過ごし方を提案しようかと考えている最中だ。
「風早?どうかした?」
「いえ、ここからどうすれば千尋に楽しんでもらえるかなと。」
「そんなこと考えてたの?」
「俺はいつだって千尋のことを考えてますよ?」
どうということはないというふうにサラリとそう言って風早はいつものやわらかな笑みを浮かべる。
それを見て、一瞬あっけにとられた千尋はすぐに赤い顔でわたわたと慌てた。
「風早はそういうことさらっと言わないの!恥ずかしいから!」
「恥ずかしいですか?俺が千尋のことを考えているのは至極当然のことなんですが…。」
「だーかーらーっ!言わないでっ!」
それは、今まで、そう、保護者だった今までなら確かに至極当然のことだったかもしれない。
従者としても確かにそう。
でも、今はどちらかというと風早は恋人、というポジションなわけで…
恋人のセリフとしては今のはかなり恥ずかしいと千尋は思う。
「それで、どうしましょうか?」
「へ?」
「これからですよ。天気がいいですから散歩するのもよし、森で昼寝もよし、忍人達の様子をぐるっと見て回るのもいいですし、疲れているならここでゆっくりするのもいい。どうしますか?」
「ん〜。」
そうだった、それを考えていたのだったと思い出して、千尋は窓から外を眺めながら考え込んだ。
確かに天気はいい。
木漏れ日の下でお昼寝は確かに魅力的かもしれない。
でも、風早と二人で並んで散歩もいい。
そんなことを考えながらちらりと恋人の様子をうかがえば、相変わらずの笑顔で自分を見つめていて…
木漏れ日の下でお昼寝すれば風早の膝枕は間違いなし。
それはそれで心地いいかもしれないけれど、恋人に膝枕をしてあげるならまだしもされて眠るのはどうだろう?とさすがに乙女の千尋は考えてしまう。
でも、風早は間違いなく自分が枕を提供すると言うに決まっているから、お昼寝は却下。
二人で散歩に出るとどうなるか?
いまだ千尋の従者でもある風早と二人で散歩は警護の関係もあってとても自然なこと。
風早は特に緊張するでもなく普通に隣を歩いてくれる。
そう、ニコニコと微笑んで、お父さんみたいに…
そんな色気の欠片も無いような散歩も却下したい。
千尋としてはせっかくの休みなのだから保護者から恋人へと関係が劇的に変化した大切な人と、少しは甘い雰囲気の一時を過ごしたいと思うのだけれど、それがなかなか難しい。
「千尋?決まらないんですか?」
「うん…特にやりたいこともないし…。」
そう言って千尋は小さく溜め息をついた。
やりたいことはあるのだけれど、それがなかなかうまくいかない。
「じゃぁ、今日はここでゆっくりしますか?」
「うん、そうする。」
これはもう今から何か考えて恋人とべったりなんて絶対無理だとあきらめて、千尋はお茶を口にした。
「疲れているでしょうから、ゆっくり休養をとるのもいいかもしれませんね。あ、お茶、いれ直しますね。」
「有難う。」
風早に器を手渡して、千尋は窓辺へと歩み寄った。
すっきりと晴れ渡っている空から吹く風はゆるやかで、さらりと髪がなびくのも心地いい。
散歩へ出てもよかったかなと少しだけ後悔していると、すっと隣に風早の気配が近づいた。
「風が気持ちいい季節になりましたね。」
「そうだねぇ。」
千尋の口元がほころぶのを見て同じように表情を崩して、風早はじっと千尋を見つめ続ける。
その視線に気付いて千尋が小首を傾げる。
「風早?何見てるの?」
「千尋ですよ?」
「えっと、だからね…私何か変?」
「いいえ、今日もかわいいですよ?」
「だから、そういうことを言わないでってば…。」
顔を真っ赤に染めながら溜め息をつく千尋を更に愛しそうに見つめて風早は満足気だ。
「か、風早、いつまで見てるの?」
「いけませんか?」
「お茶は?」
「蒸らしてます。」
「……。」
そう言いながら風早は窓のふちに腰掛けて、更にニコニコとした笑顔で千尋を見つめ続けた。
さすがにこれには千尋が我慢できなくなって、きりりとした視線を風早へ向ける。
「か、風早っ!」
「はい?」
「恥ずかしいからそんなに見ないで!」
そういいながら一歩風早の方へにじり寄った千尋の手首はあっという間に風早の手の中におさまっていて…
千尋が驚いている間にその手首はくっと風早の方へ引き寄せられた。
するとバランスを崩した千尋の体が風早の方へ倒れかかることになって、千尋がキョトンとしているうちにその小さな体は風早の膝の上に抱き上げられてしまっていた。
「ちょっ、風早?」
「たまの休みですから。」
「そ、それはまぁ…。」
振り返れば風早の嬉しそうな笑顔。
こんな笑顔を見せられたら離してほしいなんてとてもじゃないけれど言えやしない。
そもそも、こんなふうに少しだけ恋人らしい休日を過ごしたいと思っていた千尋には拒絶する理由も無い。
けれど、こうなってしまうとそれはそれで恥ずかしくて、千尋は首まで赤くなりながら風早の膝の上でおとなしくしているしかできなかった。
「千尋。」
「なに?」
突然、さっきまでとは違う少し低い声で名を呼ばれて、千尋が慌てて風早を見る。
なんだかとても真剣な声に聞こえたのに、千尋の目に飛び込んできた風早の顔はひどく幸せそうに微笑んでいてなんだか拍子抜けだ。
何かとても重要なことを言われるような気がしたのに。
「好きですよ。」
「…………………………はい?」
「俺は千尋が好きですよ。」
「………………な、ななな、何言ってるの!急に!」
たっぷり3秒は考え込んでから千尋がのけぞった。
膝から落ちそうになるその体を抱き寄せて、風早はやっぱり幸せそうな顔で笑っている。
「何って、本当のことを。今一番千尋に伝えたいことを言っただけです。」
そう言って風早はギュッと千尋を抱きしめた。
その腕の力が思いのほか強くて、少しだけ驚いて、千尋は風早を見つめた。
やわらかい微笑みはいつもと同じ。
でも、その瞳はどこか艶めいているような気がして…
ああ、この「好き」は保護者としての、父親代わりとしての「好き」とは違う「好き」なんだと一瞬で理解した。
だから、わざわざ言葉にして伝えてくれたのだ。
「……うん、私も風早のこと、好きだよ。」
真っ赤な顔で千尋がやっとそう言えば、風早が額に軽くキスしてくれた。
驚いて千尋が目を丸くしていると、風早はその紅に染まる頬を優しく撫でた。
「こういう休みもいいものですね。」
「う、うん…そうだね。」
照れながらそう言って千尋がうつむくと、今度は風早の手が千尋の顎に当てられて、ゆっくりと上を向かせたと思うと今度は唇に口づけが降ってきた。
「千尋は…。」
「へ?」
唇が離れたとたんに風早に名を呼ばれて、千尋は風早の顔をのぞきこんだ。
するとそこには少し困ったような顔をした風早が…
「イヤじゃないですか?俺とこういうふうになるのは。」
キョトン。
一瞬、何を言われているのかわからなかった千尋は、次の瞬間深い溜め息をついた。
「千尋?」
「風早は変な心配しすぎ。嬉しいに決まってるじゃない。」
あきれたように千尋がそう言えば、風早の顔は一気に明るく嬉しそうになる。
それを見ると千尋も思わず嬉しくなって、二人はクスッと微笑み合った。
「こういう休みもいいかも。」
そう言って千尋が風早の首に抱きつくと、風早は千尋の体を優しく抱きとめながらその頬に軽く口づけた。
「俺はこんなに楽しい休みは他にないですが…。」
「どうかした?」
何か不満があるのかと千尋が体を離せば、風早が窓の外へと視線を向けた。
つられるように窓の外を眺めてみればそこには……
「お、忍人さんと、柊……。」
「見られてましたね。」
視線の先にはあきれたような顔を並べている忍人と柊がいて、千尋はそれこそ顔を真っ赤にして慌てて風早の膝からおりた。
「風早っ!中!中に入って!」
「俺は別にいいんですが…。」
そう言って苦笑しながらも千尋の言葉に従って部屋の中ほどまで入った風早は、そこでまた千尋を腕の中に閉じ込めてしまった。
「か、風早っ!」
「ここなら見えません。」
「そうだけど…。」
「こういう休みもいいとさっき言ったでしょう?」
「うん……。」
大好きな人の腕の中はそれはもちろん居心地が良くて、千尋はうっとりと目を閉じた。
外はまだまだ明るい。
休みはもうしばらく続きそうだ。
そしてその休みはこんなふうに恋人と甘く過ごすことができる。
そう思えば嬉しくて、千尋がただただ風早の腕の中を楽しんでいた。
だから、すっかりその存在が忘れられてしまっていたお茶は、後でお湯で薄めて飲むハメになるのだった。
管理人のひとりごと
父さんで甘さの限界に挑戦?(マテ
というわけじゃなかったんですが、終わってみればこんなことに…
ただ単に風早パパに「好きですよ」って言ってほしかっただけなのに…
その発想がもう甘い方向性だったのか(’’)
ここはもう見せ付けられる周りがかわいそうになってきた管理人でした…
ブラウザを閉じてお戻りください