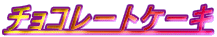
千尋はホームルームが終わるとすぐに学校を出た。
急いでいるのは買いたいものがたくさんあるからと、風早や那岐に知られずに作りたいものがあったから。
そう、今日は2月14日。
いわずと知れたバレンタインデーだ。
今年こそはチョコレートケーキを焼いて二人にプレゼントするんだと決めて、千尋は材料のメモを片手にスーパーへと足を踏み入れた。
小麦粉、ベーキングパウダー、チョコレート…
と売り場を回って材料を集める。
同時に今日の夕飯のおかずの買出しもしていたら、結構な荷物になりそうな気配だ。
千尋が覚悟を決めたその時…
「またずいぶん買い込む気でいるね。」
「へ?」
急に背後から声をかけられて千尋が振り返るとそこにはいつものようにけだるげな那岐の姿があった。
「那岐?何やってるの?
「風早がさ、千尋が帰りに晩御飯のおかずを買いに行くはずだから荷物持ち頼むっていうから追いかけてきたんだけど、それ、なんでそんな大量になってるわけ?」
「えっとそれは…。」
できれば内緒でケーキを焼きたかったのにと千尋が買い物カゴを隠そうとすれば、那岐は一瞬でそのカゴの中身を把握してしまったようで…
「なるほどね、今日バレンタインなのに千尋は騒いでないと思ったらこれから作るわけ?」
「ま、まぁ……。」
「間に合うの?それ。」
「へ?これから帰って焼けば焼きたてのおいしいの食べれるよ。」
「……まさか、誰かにあげるとかじゃないわけ?」
「もちろんあげるよ、那岐と風早に、で、ついでに自分のも作るの。みんなで食べた方がおいしいでしょ?」
そう言って千尋が微笑むと那岐は何故か深い溜め息をついた。
「え、何?今溜め息つくところ?」
「別に、千尋は成長しないなと思っただけだよ。」
「ひどい、成長ならしてるよ、今年はチョコレートじゃなくてチョコレートケーキだもん。」
「そういう意味じゃないよ…。」
「じゃぁ、どういう意味?」
「もういいよ、ほら、荷物持つから。」
むくれている千尋にこれ以上かまう気はないらしい那岐は千尋の手から半ば強引に買い物籠をもぎ取った。
「ちょ、那岐!」
「ほら行くよ、あと必要なのは何?」
「えっと、チョコレートケーキに飾るイチゴ…。」
もごもごとそういう千尋は方って那岐はスタスタと歩き出した。
向かっっているのはどうやら果物売り場。
なんだかんだ言って自分の言うことはきいてくれる那岐に苦笑しながら、千尋は最後のイチゴを買うために一歩を踏み出した。
「ただいま。」
「風早!お帰りなさい!」
風早がいつものようにドアを開けて中へ入るとそこには、満面の笑みを浮かべた千尋が立っていた。
玄関にまで甘いチョコレートの香りが漂っているから何を作っていたのかは察しがつく。
風早はその顔に笑みを浮かべるときちんと脱いだ靴をそろえてから中へ入った。
「すみません、遅くなってしまって。急に飲み会が入ったもので。」
「ううん、ご飯は那岐と二人で済ませちゃった。飲み会って風早飲んできたの?」
「いいえ、俺はしらふです。付き合いでちょっと顔を出したついでに夕食を食べてきたっていう程度ですよ。」
「まだおなかに余裕ある?」
キラキラした碧い瞳で見上げられて風早は嬉しそうな微笑を浮かべてうなずいた。
「大丈夫ですよ、何か作ってくれたんですか?」
「もちろん!今日はバレンタインだもん!」
弾むような声でそう言って千尋は風早の背を押した。
リビングへ足を踏み入れればテーブルの上には大きなチョコレートケーキがのっている。
ソファには待ちくたびれたと言わんばかりの那岐の顔があった。
「待たせたね、那岐。」
「バレンタインにチョコもらえなかった同僚の愚痴でも聞いてたの?」
「まさか、学校ではチョコレートのやりとりは禁止だからねと言いたいところではあるんだけどね。」
そう言って風早が苦笑するところを見ると、どうやら那岐の予想は完全に外れているというわけではないらしい。
「憧れの先生にチョコレートあげるっていってる子はけっこういたから……って、あれ、風早は手ぶらなの?」
「はい、どうしてですか?」
「だって、風早、女子に人気あるからたくさんチョコレートもらってくるのかと思った。」
「まさか、俺にチョコレートなんてそんな奇特な女性はそうはいませんよ。」
実はいくつかは渡されそうになったのだが、風早は丁重に断っている。
学校ではチョコレートのやり取りが禁止になっているのに教師が受け取るわけにはいかないという建前が一つ、女生徒からもらったチョコレートなど持って帰りたくはなかったという理由がもう一つ。
「人当たりがいいのはあんたの唯一のとりえだと思ってたんだけど?」
「那岐!風早は人当たりがいいだけじゃないよ!いいとこたくさんあるじゃない!」
「ハイハイ、もうそんな話はいいからさ、早いところバレンタインとやらを終わらせてくれない?僕は部屋に戻って寝たいんだけど?」
「もう、那岐はすぐそんなふうに言うんだから。」
千尋はむくれているが、早く寝たいといいながらも風早が来るまで待っていてと言う千尋の言葉に従って今まで待っていたらしい那岐を思うと風早は思わず笑みをこぼした。
なんだかんだいって那岐も千尋には頭が上がらないのだ。
「じゃぁ、切り分けるから、みんなで食べよう。」
「俺は紅茶でもいれますね。」
荷物を置いてコートとジャケットを脱ぐと風早はそのまま台所にたった。
台所がいつもより綺麗になっているのは、きっと千尋がケーキを焼いた後でちらかっったのを片付けたからだろう。
そんな小さなことまでが風早にとっては嬉しくてしかたがない。
風早が紅茶を3人分いれて戻るとケーキはもう綺麗に切り分けられていて、那岐は自分の分のケーキにフォークをつきたてていた。
「さ、どうぞ。」
「ありがとう、これ、風早の分ね。」
千尋が手渡してくれたケーキはひときわ大きく切り分けられた一つで、風早は満面の笑みでそれを受け取った。
「ありがとうございます。今年はケーキなんですね。」
「うん、毎年ただ型に流しただけのチョコレートじゃ進歩がないなぁと思って、今年は頑張たの。食べてみて。」
「じゃぁ、ありがたくいただきます。」
風早がケーキにフォークを刺すとその様子を見届けてからやっと千尋も自分のケーキに手をつけた。
可愛らしくイチゴがシラ割れているチョコレートケーキはふわりとしていてとてもおいしそうだ。
風早は一欠け口に入れてよーく味わった。
チョコレートの香りがちゃんとしているチョコレートケーキだが、予想していたより少し甘みが強い。
もちろん、甘いものが苦手ではない風早にはどうということはない甘さだが、ちらりと千尋の顔を盗み見れば、千尋はフォークをくわえたまま眉間にしわを寄せていた。
「甘すぎた、ね……。」
「俺はこれくらいでもおいしいですが…。」
「ううん、甘いよ、いくらなんでもこれは……二人とも残して。」
悲しそうにそういいながらフォークを置いた千尋から風早が那岐へと視線を移せば、那岐は何も言わずに黙々とケーキを食べている。
那岐にとってはかなり甘いのか、その表情は険しい。
風早は苦笑しながら立ち上がった。
「風早?」
「ケーキに使ったイチゴがこれだけならまだ余っている分がありますよね?」
「うん、冷蔵庫にあるけど、イチゴと一緒に食べたくらいじゃ…。」
「いえ、それでストロベリーソースを作ってみましょう。ケーキと一緒に食べるときっとおいしいですよ。」
「でもバレンタインのケーキなのに風早にソース作らせちゃうなんて…。」
「じゃぁ、一緒に作りましょう。」
「風早…。」
「俺は千尋と一緒に料理ができるととても嬉しいんですが?」
そう言って風早が優しく微笑みかけると千尋はやっと立ち上がった。
その顔にはまだ曇りがちではあるけれどなんとか微笑のようなものも浮かんでいる。
「うん、ありがとう。じゃぁ、那岐、もうちょっとだけ待っててね。」
ほっとしたような那岐がフォークを置くのを見届けて千尋は風早と二人で台所に立った。
冷蔵庫からイチゴを取り出した風早は手際よくそれを洗っていく。
「ごめんね、ちゃんとしたケーキあげられなくて。」
「俺はこうして一緒に料理ができることが嬉しいって言いませんでしたっけ?」
「うん、ありがとう。」
風早の優しさが伝わって千尋は思わず泣きそうになってしまった。
張り切りすぎて失敗したおかげで、きっと那岐も無理をしたはずなのに、こんなときばかり文句の多い那岐も何も言わないのだ。
二人とも優しすぎる、千尋はそう思うことがある。
今がちょうどそんな時。
「ホワイトデーは覚悟しておいて下さいね。」
「へ?」
「今年は俺も張り切って何か作りますよ、千尋の好きなデザート。何がいいですか?」
「そ、そんなのいいよ、失敗作食べさせられたのにホワイトデーなんて…。」
「そんなこと言うなら千尋がダイエットしなきゃいけなくなるほど大量に作りますよ?」
「風早っ!」
「考えておいて下さいね、何を食べたいか。」
「風早……うん、ありがとう。」
千尋がやっと普通に微笑を浮かべることができるようになった頃には、台所には甘酸っぱい香りが漂いはじめていた。
風早がかき混ぜている小さな鍋には可愛らしい色をしたストロベリーソースが完成しようとしている。
管理人のひとりごと
張り切ってみたけど失敗した千尋ちゃんの巻でした(笑)
いやもう風早父さんは千尋ちゃんが作ったものならどんなものでもおいしく笑顔でいただきます(爆)
意外と那岐も仏頂面でいただきます(マテ
そして失敗した時はさりげなくフォローしてあげるのがお父さんです(w
本当は豊葦原でバレンタインもいいなと思ってたんですが…
間に合いませんでした(、、;
こちらもだいぶれてますが、お許し下さい(TT)
プラウザを閉じてお戻りください