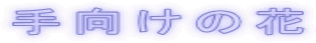
冬の弱々しい陽射しがだんだんと力を持つようになって、人々も心なしか強張っていた体を解いているように見える。
柊はそんな風景を隻眼を細めて眺めていた。
寒い季節は自然と人々は体に力を入れて歩いてしまうものだ。
それが、春の訪れとともにほどけてゆく。
そんな様子を眺めるのは妙に気分の弾むものだと思いながら柊は窓辺に座っていた。
こうして穏やかな心持で春の景色を眺めることができるようになったのは、彼の大切な恋人であり主でもある千尋のおかげだ。
千尋によって既定伝承に記されていない未来が紡がれた直後、柊はなんとも落ち着かない思いでいた。
それは彼が望んだ世界であったはずなのに、全く未来が見えない世界は少しばかり不安でもある。
複雑な想いの中で過ごしたのは数カ月のこと。
気付けば不幸な未来を見ることのない毎日を穏やかに過ごせるようになっていた。
未来を見ることのできない漠然とした不安は愛しい人が側にいて拭い去ってくれた。
そうなれば、あとは幸せが待っているかもしれない未来を見つめるだけだ。
春になれば人々が浮足立って見えるのも、きっと厳しい冬の終わりに幸せな未来を見るからだろう。
そう思えるようにもなった。
だから、今、自分はきっと幸せなのだろうと柊はまるで他人事のように感じていた。
「柊、いる?」
そっと扉を開けてちょこんと顔を見せたのは千尋だった。
窓辺に座ったまま柊が振り向いて笑みを浮かべる。
「はい、ここに。」
「入ってもいい?」
「私が我が君の来訪をお断りすることなど、たとえ世界が滅ぼうともありえません。どうぞ中へ。」
「柊は大げさなんだから。」
少しばかりあきれ顔で入ってきた千尋は、すぐに柊の傍らに立つと愛らしい笑みを浮かべて見せた。
「何か御用でしょうか?仕事は済ませてあると思いましたが…。」
柊は今のように午後の一時をくつろいで過ごすことが多い。
というのも、与えられた仕事はあっという間にこなしてしまうからだ。
軍事に関しては岩長姫と忍人がいるおかげで、柊は兵の鍛錬に付き合う必要がない。
彼の手腕はもっぱら軍略に注がれるわけで、今のところ平和を保っている中つ国で柊の才を必要とする場面はそう多くはなかった。
加えて、彼は仕事が速い。
そもそも少ない仕事を誰よりも速くこなすのだから、半日がすっかり空いてしまうのも当然のことだった。
「仕事の話じゃないんだけど…。」
「では、どのような?」
「えっとね……ちょっとだけ、わがまま言ってもいい?」
恥ずかしそうに上目づかいに尋ねる千尋に柊は苦笑を漏らした。
世界よりも未来よりも大切だと思える恋人のどんなわがままも聞かないはずなどないではないか。
柊は右手を胸の上に置くと、恭しく一礼した。
「なんなりと。」
「もぅ、柊はすぐそうやって大げさにするんだから。」
「大げさではありません。不詳のこの身で宜しければ、どのような御命令も厭いません。」
「命令じゃないんだけど……お願い、なんだけど…その…これから一緒に出掛けてほしいの。」
言いづらそうにそれでも懸命に口にしたらしい千尋の一言に柊ははっきり言えば拍子抜けした。
わがままなどと言うからどんな無理難題が飛び出すことかと思っていたのに、ただ共に出かけたいだけとは…
「私一人と、ですか?」
「そう。」
「他に護衛はなしでと。」
「そう。」
「なるほど。それは確かにわがままですね。」
わざとふざけてそう言えば、千尋はぷっとむくれた顔をして見せた。
「どうせ柊は私と二人で出かけるのなんて嫌だろうけど。」
「そういう意味ではございません。この身には余る光栄ですが、護衛がなしというのは…。」
確かに中つ国は平和になったが、この国の女王がたった一人、それも軍師のみを伴っての外出というのは無防備と言っていい。
もちろん、柊自身は何があっても命をかけて千尋を守るつもりではあるのだが。
「それは大丈夫。柊はちゃんと私を守ってくれるくらい強いって知ってるから。」
そう言って満足げに微笑まれては柊にあらがう術はない。
「承知致しました。では、お供させて頂きます。」
「有り難う。」
嬉しそうに微笑む千尋はあっという間に柊の腕をとると、颯爽と歩き出した。
どうやら目的地は決まっていて、そこへ自分を連れて行きたいらしいと気付いた柊は腕を愛しい人に預けてゆったりとついていくことにした。
「これは見事な…。」
柊は目の前に広がる光景に思わず声をあげた。
千尋が柊の腕をとって連れてきたのは満開の桜の下だった。
今を盛りとばかりに咲き誇る桜は時折吹く風に薄紅の花弁を散らして、幻想的なまでに美しかった。
「凄く綺麗に咲いてたから、どうしても柊と一緒に見たかったの。」
「それは身に余る光栄です。私ごときをこのように見事な花の下へお誘い頂けるとは。」
「だって、柊と初めて会った時もこんなふうに桜が綺麗だったから。」
幸せそうに微笑んで言う千尋に柊は隻眼を見開いた。
自分と初めて会った時のことをそんなふうに語ってくれるとは。
つくづく自分は予想のできない時を生きているのだと実感する。
彼がこれまで見知ってきた歴史ではそんなことはありえなかったのだから。
「我が君にそのように言って頂けるとは…。」
「初めて会った時は何が何だかわからなくて、柊のこと、ちょっと怖かったりして…その……。」
途中で言葉を濁す千尋の顔を柊は首を傾げながら覗き込んだ。
目の前の恋人が何を言いたいのか全く見当がつかないからだ。
千尋ははっと何かを決意したかのように視線を上げると、柊の隻眼を正面から見つめた。
「あの時は色々…その…失礼なこと言っちゃったかもしれないなって…ごめんね?」
柊は一瞬驚いたような顔をした後で、くすっと笑みを漏らした。
何がおかしいのかと千尋がその顔を不機嫌そうに歪ませる。
「ひどい、本当に悪かったなって思ったから頑張って謝ったのに…。」
「いえ、実際、私は我が君の目には怪しく映ったことでしょう。昔の私がどのような扱いを受けていようとも気には致しませんよ。」
「本当?」
「はい。それよりも…。」
「それよりも?」
今度はどんなことを言われるのかと少しばかり警戒を見せる千尋に柊は手を伸ばした。
ぴくりと力の入った細い肩を抱き寄せて恋人の体を腕の中に閉じ込めて、その唇を耳元に寄せる。
咲き誇る花にさえ聞かれぬように、その本心を告げるためだ。
「今の私への扱いの方がよほど気にかかります。」
「今のって……。」
「以前はともかく、今この時に我が君に冷たくされたのではこの身はすぐさま儚くなってしまうことでしょう。」
「儚くって…。」
「死んでしまう、ということです。」
耳元で告げられた不穏な言葉に千尋は息を飲んだ。
そして柊の腕の中で急に視線を上げると、その頬を両手で包んだ。
「そういうこと言っちゃダメ。二度と言わないで、死ぬなんて。」
「我が君…。」
「絶対ダメ!」
目に涙さえ浮かべて訴える恋人を柊は苦笑しながら抱きしめた。
「承知致しました。もう二度と、決して口には致しません。」
「うん、約束ね。」
「はい。」
死ぬなと愛しい人に言ってもらえることがこんなにも幸せなのかと実感しながら柊は千尋を抱きしめたまま視線を上げた。
視線の先には咲きこぼれる桜の花。
自分が初めて愛しい人と出会ったのが同じ花の下ならば、今ここから新しい自分を始めよう。
そしてこの花を過去の自分に手向けよう。
定められた時した生きることのできなかった自分に。
これからは腕の中にある愛しいぬくもりのためにだけ生きる。
彼女が死ぬなと言うのならどんなことがあっても生き延びよう。
柊は既に描かれていない未来を自分で描いていくならば、この愛しい人の望む未来を描こうと花の下で誓うのだった。
管理人のひとりごと
桜企画ラストワンでございました。
PSPやって気付いた、柊って桜の舞う中で出会ってるじゃない(’’)
スチルを鑑賞するまで気づかなかった…
あれ、桜だよね?(マテ
4は桜っていうとどうしても忍人さんのイメージが強いからなぁ。
アシュとかもやりたかったんですが、今年はタイムアップ(^^;
すっかり花は終わってしまったところがほとんどと思いますが、お楽しみ頂ければ幸いですm(_ _)m
ブラウザを閉じてお戻りください