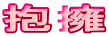
降り注ぐ陽の光。
その下で花に囲まれている美しい人。
アシュヴィンは大きな木の幹に背を預けて座り、その美しい人を見つめていた。
たまに妻と二人そろって得ることのできた休日に、他にすべきことなど思いつかない。
陽の下で微笑む千尋を眺めているだけでアシュヴィンの顔には笑みが浮かんでいた。
ただそうしているだけでもアシュヴィンにとっては幸福な一時だったが、花の中に座っていた千尋はすっと立ち上がるとアシュヴィンの方へと歩き出した。
千尋はその両手いっぱいにつんだばかりの花を抱えていた。
「起きてたんだ。」
アシュヴィンの隣に座りながら千尋が笑顔を見せた。
その千尋の髪に手をのばしてアシュヴィンが苦笑する。
「眠るわけがないだろう。」
「どうして?疲れているんだから休みの日に昼寝したって誰も文句は言わないと思うけど…。」
何故眠らないのかと問われれば理由は一つだ。
ところが、千尋はその理由に全く思い至らないらしい。
アシュヴィンはふっと笑みを漏らすと、千尋の髪を指で梳いた。
「こんなに美しい妻を独り占めにして眺めていられるというのに、眠ってしまうバカがどこにいる。」
うっとりとアシュヴィンが千尋を見つめれば、いつもはムキになる千尋が赤い顔をして膝の上にあった花束の中から白い花を一本取り上げた。
アシュヴィンが何をする気かといぶかっている間に、花は白くたおやかな指でアシュヴィンの髪に挿された。
「アシュヴィンの方が白い花は似合うんだから。」
赤い顔で言う千尋にアシュヴィンがニヤリと笑って見せる。
「それはつまり、花を挿した俺はいい男だと言っているのか?」
この問いに一瞬言葉を詰まらせて…
そして千尋はうなずいた。
「そう、アシュヴィンはステキって言ってるの。」
真っ赤な顔でハッキリと断言した千尋に気を良くして、アシュヴィンはその小さな体を抱き寄せた。
「アシュヴィン!ここ外!」
「后殿が良い男だと言ってくれるなら花などいくらでも挿してやるさ。」
耳元で聞こえた艶やかな声に、千尋は更に顔を赤くした。
降り注ぐ陽の光の下、千尋はしばらく赤い顔のまま満足げなアシュヴィンにとらわれたままだった。
管理人のひとりごと
いつも千尋ちゃんに花を飾るのは殿下ですが、逆ならどうよ?という試み。
赤いバラとかも似合いそうだけども(笑)殿下は肌が黒いので白い花にしてみました♪
青も考えたけど、金髪の千尋ちゃんにはかなうまい(w
結局のところ殿下がおいしい思いして終わり、それはいつものこと(’’)
ブラウザを閉じてお戻りください