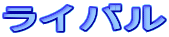
いつものように風早は朝、千尋の部屋へとやってきた。
ところが、いつもとは違って扉を開けた風早は思わず扉を閉めるのも忘れて一瞬凍りついてしまった。
何故かと言えば、それは千尋が部屋の中央で腕組みをして立っていたからだ。
顔には不機嫌そうな表情が浮かんでいて、風早は一瞬で千尋に説教をされる自分を想像してしまった。
「千尋?」
「おはよう、風早。」
「おはよう、ございます…。」
思い出したように後ろ手に扉を閉めて、風早は千尋の前へと歩み寄る。
すると千尋は愛らしく上目遣いに風早を見上げて口を開いた。
「風早。」
「はい?何かありましたか?」
「べ、別に何もないけど……。」
先回りされてしまって、千尋は思わずうつむいた。
こんなふうにごまかすということは、間違いなく何かあったということだ。
「今日はずいぶんご機嫌ななめなんですね。」
「別に機嫌が悪いわけじゃ……ただ、その……うらやましかったというか……。」
「何が、ですか?」
「何がって……姉様が……今日は羽張彦さんに誘われて、その……デート、なんだもん……。」
赤い顔でもじもじしながら言う千尋に、風早は微笑を浮かべた。
つまり、姉ばかりが愛しい人と二人きりでデートをするというのがうらやましいということなのだろう。
何しろ、ここのところは仕事ばかりが忙しくて、二人きりでいることはあってもそれは決して甘い一時ではなかったから。
「では、千尋も俺とデートしてくれますか?」
「本当?いいの?」
「俺はいつだって千尋と二人でデートしたいと思っていますよ?」
風早がさらりと本音を言えば、千尋はあっという間に湯気が出そうなほどに顔を赤くした。
「ここのところ、仕事が詰まっていて忙しかったですし、たまにはゆっくりしてもいいでしょう。」
千尋はまだ赤い顔で嬉しそうに微笑むと、風早にギュッと抱きついた。
そんな千尋の顔を上げさせて、風早は不思議そうにしている千尋から素早く唇を盗み取る。
「か、風早!」
「デート、しましょう。仕事ではなくて。」
急な口づけに抗議しようとする千尋にそう囁いてしまえばもう風早の勝ちだ。
千尋は赤い顔で二つうなずいて、風早の腕に抱きついた。
外は晴天。
風早は千尋に腕を預けたまま、明るい空の下へ向かうべく部屋を出た。
管理人のひとりごと
たまにはこういうなんていうか、なんでもない日常みたいなものもいいかなと。
つまりはお姉ちゃんと千尋ちゃんは恋する者同士、ライバルみたいな?
ちょっと違うな…(マテ
イチャイチャかげんなら風早も負けないと思うんだ!羽張彦には!(w
ブラウザを閉じてお戻りください