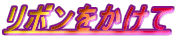
「当然、お前自身を贈ってくれるのだろう?」
この一言で千尋は凍りついた。
目の前には極々真剣な顔のアシュヴィン。
ラフな格好で寝台の上に座っているアシュヴィンの手には竹簡が握られているけれど、その視線は問いを発した妻へと向けられている。
千尋は本日、朝一番でアシュヴィンに一つの質問を投げかけていた。
『お誕生日に贈り物を用意したいんだけど、何がいい?』
というのがその質問だ。
その答えがこれだったものだから、千尋は寝巻き姿のまま凍りついたというわけだ。
なんとなくそういわれるんじゃないかと予想はしていたし、夫婦なのだからそういう会話でじゃれるのもいいかもしれないとも思っていたけれど…
こんなふうにさも当然というようにキョトンとした顔で言われるとは思ってもみなかった。
しかも、朝、寝巻き姿の妻を目の前にして、だ。
千尋は顔を真っ赤にすると上目遣いにアシュヴィンをにらみつけた。
恥ずかしいやら抗議したいやら非難したいやらで、結局言葉が出てこなかったのだ。
「なんだ、違うのか?」
ニヤリと笑うアシュヴィンに千尋は小さく溜め息をついた。
そう、この人はこういう人だった。
そうは思ってもここであきらめるわけにはいかない。
大好きな人の誕生日にはどうしたってステキな贈り物を用意したいものだから。
「ほ、他に欲しいものない?もっと贈り物っぽい…。」
「俺にお前以外に欲しいものがあると思っているのか?」
「……。」
ニヤリと笑って答えるアシュヴィンの前で絶句して、千尋は次にキリリと表情を引き締めた。
「わかりました!」
大声でそう言い放って、千尋は立ち上がるとアシュヴィンに背中を見せた。
向かうは扉。
慌てたのはアシュヴィンだ。
「おい、千尋、何を怒って……。」
バタンっ
大きな音と共に扉が閉まって、アシュヴィンが止める間もなく愛しい妻は出て行ってしまった。
その背中は明らかに怒っているように見えた。
またやってしまったかとアシュヴィンが溜め息をついているうちに、千尋と入れ替わるようにリブが入ってきて苦笑した。
きわめて不機嫌そうなアシュヴィンの視線を受ければ、リブには何が起こったのかだいたい予想がつく。
「や、陛下、また、ですか?」
「またとはなんだ、またとは。」
「で、今回は何が原因で?」
「俺が生まれた日を祝うために贈り物がしたいから何がほしいかと聞かれた。」
「なるほど、それはお怒りになるでしょう。」
「…まだ答えを言ってないぞ…。」
「お前が欲しい、と、おっしゃったんでしょう?」
「……。」
口調まで真似するリブにアシュヴィンは錆びた鉄を噛み締めたような顔をして竹簡を放り出した。
「それは陛下がいけませんでした。」
「うるさい!仕事をするぞ!」
自分が悪かったということくらいわかっている。
千尋は無差別に不機嫌を振り回したりはしないし、千尋の方が悪ければすぐに向こうが謝ってくる。
今回に関して言えば千尋が自分に何か気の利いたというか洒落たものを贈りたがっているということもわかっていたのだ。
それでも答えがアレしか浮かばなかったのはもちろん、それがアシュヴィンにとって掛け値なしの本心だったから。
そんなことをリブに言ってみても始まらないので、アシュヴィンは仕事に集中することにした。
千尋には夜にでも心を尽くして謝罪すればいい。
そうすれば許してくれない妻ではないのだから。
アシュヴィンは青白い顔で自分の部屋と続く廊下を歩いていた。
何故なら、千尋を怒らせてしまったあの日から5日もの間、一目も妻の姿を見ていないからだ。
あの日、千尋は夕飯を共にとらず、忙しかったアシュヴィンは千尋に会いに行くこともできずに寝てしまった。
久々の一人寝では熟睡できなかったと見えて、翌日の目覚めは最悪だった。
そしてそれからというもの、千尋は一緒に寝るどころか食事もとってくれず、リブが次から次へと仕事を持ち込んでくれたおかげでアシュヴィンの方から千尋に会いに行くこともできなかった。
このままでは本当に二度とあの美しい笑顔を見ることができないのではないかと思うと体の中心が凍りつくような思いだ。
今夜こそはなんとしても千尋に許しを請おう。
これ以上一人寝させられては寝不足で死ぬ。
そんなことを思いながらアシュヴィンの足は自分の部屋から千尋の部屋へと方向転換を行った。
会えなかった5日の間にアシュヴィンの症状は悪化して、今では暇さえあればそれが一瞬であっても千尋のことを考えている。
それは現在も続いていて、アシュヴィンは千尋の幻さえ見そうな勢いで千尋の部屋の前までやってくると、その扉をそっと押してみた。
怒っている千尋はよく部屋にこもってしまって、許すまで決してアシュヴィンを中へ入れてはくれない。
だから、今回も扉はきっと容易には開かないだろうと思っていたのに…
重いはずのその扉はあっさりと開いたのだった。
ところが、喜んだのもつかの間、アシュヴィンの目に飛び込んできたのは真っ暗で誰もいない冷たい部屋だった。
「千尋…。」
呼んでみても灯り一つない部屋の中に部屋の主がいるわけもない。
これはとうとう家出でもされたかと焦りながらもどうしようもなくて、アシュヴィンは扉を閉めると自分の部屋へ向かって歩き出した。
とりあえず自分の部屋へ戻ってリブを呼ぶ。
そしてリブからここ数日の千尋の様子を聞きだそう。
できることならリブから千尋の行き先も聞き出せれば文句はない。
行き先を聞き出したら、すぐに千尋を連れ戻しに行かなくては。
アシュヴィンの頭の中はそんなことでいっぱいで、自分の部屋の扉を押し開いた時にはほとんど無意識の状態だった。
だから、自分の部屋の中の異変に気付いたのは数瞬後のこと。
後ろ手に扉を閉めて一つ溜め息をついて視線を上げた時だった。
「ち、ひろ?」
目の前には灯りに暖かに照らし出されている千尋の姿があった。
白くてフワフワの衣裳に身を包み、髪には同じ白の美しいリボンが結ばれている。
白くて裾の長いそのフワフワの衣裳は、いつかの結婚式を思わせて、アシュヴィンは息を飲んだ。
とうとう自分は妻恋しさに妻の幻を見ているのかとアシュヴィンは何度か強く瞬きをしてみた。
それでも目の前の千尋が消えることはなくて、それどころか千尋の顔には少しはにかんだ様子の笑みが浮かんだ。
「アシュヴィン、お誕生日、おめでとう。」
「あ?ああ…。」
あまりの美しさと愛らしさにアシュヴィンが圧倒されていると、千尋がクスクスと笑みを漏らした。
千尋が笑みをもらすのをこらえられないほどアシュヴィンは呆然と立っていたらしい。
「ああって、アシュヴィン、自分の誕生日忘れてたの?」
「いや……お前、どうして…。」
「どうしてってアシュヴィンの誕生日だからに決まっているでしょう?だって、アシュヴィン、この前、誕生日の贈り物は私以外何もいらないって言ったから…。」
急に顔を真っ赤にして千尋がうつむくのをアシュヴィンはまだ信じられないといった顔で見つめていた。
そうだ、あの日、贈り物には何が欲しいかを聞かれたあの日、千尋は確かに怒りを見せてアシュヴィンの元を去っていったのだ。
それなのに、今の千尋は女神のように美しくて、愛らしい表情を見せてくれている。
「お前…俺がそう言ったから、その衣裳を?」
「え、うん…だって、アシュヴィンいっつも私の花嫁衣裳姿が綺麗だったって言ってくれるから……やっぱり白がいいかなって…でもほら、前に着た花嫁衣裳じゃ見たことあって新鮮味がないし…だから、急いでみんなに作ってもらったの。リブにも協力して貰っちゃった。」
リブも共犯だと聞かされて、アシュヴィンは何もかもを納得した。
千尋にしてみればアシュヴィンに内緒で急いで衣裳を作っていたからアシュヴィンに会う時間がなかったということなのだろう。
そしてリブがそれに協力した。
おかげでアシュヴィンはこの5日、仕事に追われて千尋の元へ押しかける暇もなかったというわけだ。
アシュヴィンは大きく一つ息を吐き出すと、ゆっくり千尋の側へ歩み寄って美しく着飾っているその体を優しく抱きしめた。
「アシュヴィン?」
「俺はてっきりお前が俺に愛想をつかして出て行ったのかと思ったぞ。」
「へ?なんで?」
「この前、お前、怒っていただろう?」
「この前ってアシュヴィンに誕生日の贈り物の話をした時?」
「ああ。」
「まさか、あれは怒ってたんじゃなくて気合を入れたの。」
「は?」
「そこまで贈り物には私がいいって言うなら、もう精一杯飾って贈ろうって。」
「はっ、お前らしいな。」
聞いてみれば千尋らしい反応で、アシュヴィンの口元にもやっと笑みが浮かんだ。
「贈り物、喜んでくれた?」
「ああ、俺にとっては何よりだ。」
ウキウキした声の千尋に答えて、アシュヴィンは千尋を抱く腕に力をこめた。
こんなに美しくて愛らしくて、愛しくてたまらない妻をこんなに幸せな気持ちで抱きしめることができるなら、この5日間の会えなかった時間も無駄ではなかったのかもしれない。
そんなことさえ考えながらアシュヴィンは千尋を上向かせると、その唇に優しい口づけを落とした。
なるべく優しく、どれだけ自分が千尋を想っているかが伝わるように。
そして千尋は、いつもよりもうんと優しいアシュヴィンの口づけにうっとりと目を閉じた。
管理人のひとりごと
まぁ、この後殿下はおいしく千尋ちゃんを頂いて、翌朝に激しく怒られるんですな(’’)
で、結局のところ岩戸発動(マテ
殿下はたぶんそんなことの繰り返しだと思う(w
今回、殿下の常套句「お前以外には何も欲しいものなどない」に対抗した千尋ちゃんの図。
だったら私を贈ってやろうじゃないの!となりました(笑)
すると殿下はウキウキで優しくなりましたとさ(爆)
何はともあれ、殿下、お誕生日おめでとうございます(^^)
ブラウザを閉じてお戻りください