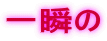
「う〜ん…」
小さな声が唇の間から漏れ出て、千尋はゆっくり目を開けた。
まだはっきりしない意識の下で、目から入ってきた光景を認識する。
そこにいるのは上半身裸のアシュヴィンだ。
そして今まさに、その裸の上半身に上着を羽織ろうとしている。
千尋は何度かまばたきして、それから目をこすってまだ朦朧としている意識をはっきりとさせた。
「なんだ、起こしてしまったか?」
「ううん、それはいいの。アシュヴィンは今日ももう仕事?」
「その言いようは、俺が朝早くから仕事をしては寂しいと駄々をこねているように聞こえるな。」
面白そうにそう言ってアシュヴィンは千尋の額に口づけを落とす。
千尋は少しだけ頬を赤らめて上掛けを口元まで引き上げた。
「そういう意味じゃ…最近ずっと朝が早いから。」
「すまんな。ここのところ少し立て込んでいる。」
「忙しいんだ。大丈夫?」
「俺がこれくらいのことでねをあげると思っているのか?」
間近でそんなふうに言われては、千尋は顔を赤くすることしかできない。
そんな千尋の髪を一撫ですると、アシュヴィンは着替えを済ませて立ち上がった。
「ゆっくり休んでおけよ、俺よりお前の体の方が繊細だし大事だからな。」
「そんなこと…。」
千尋が抗議しようとする間もなく、アシュヴィンは片手を振って出て行った。
こんな朝がもう5日も続いている。
以前はいくら忙しくても朝はもう少しゆっくりしていたものだった。
なんと言ってもアシュヴィンは必ず先に目を覚まして、千尋の寝顔をじっくり堪能したあげく、朝っぱらから千尋に口づけたり口説き文句を囁いたりとやりたい放題だったのだ。
それが5日前からすっかり変わってしまった。
朝早くに目覚めたアシュヴィンはどこか落ち着きがなくて、一応は目覚めたばかりの千尋をかまいはするもののあっという間に寝室を出て行ってしまう。
朝からからかわれるのは迷惑だと思う千尋も、いきなりこんなふうにそっけなくなると寂しいのが乙女心というもので、ここ数日はなんだか寂しいのか不安なのかわからない複雑な気持ちになっていた。
もぞもぞと寝台から下りて千尋は着替えを始めた。
ここに来たばかりの頃は采女達が毎朝着替えを手伝ってくれたものだけれど、どうしても人に手伝われて着替えをするのに抵抗があって、最近は一人で着替えることを采女達に許してもらっている。
とりあえずはいつも着ている衣に着替えて、千尋は溜め息をついた。
そんなにアシュヴィンが忙しいのなら、やっぱり自分にも手伝えることがないかどうか聞いてみるべきではないだろうか?
それとも、そんなことを聞いたらやぶへびだったりするのだろうか?
やぶへびって何が?
などなど…
千尋は悶々と頭の中でだけ考え続けて、そして一つ深呼吸をするとリブを呼び出した。
ここはやっぱり聞いてみよう。
というのが千尋の結論だ。
「や、お珍しい、どうかなさいましたか?」
そんなに待たせることなくやってきたリブはいつものニコニコ顔で千尋の前に立った。
手にはいくつか竹簡を抱えていて、彼も忙しいのだとすぐにわかった。
「ごめんね、リブも忙しいのに。」
「いえ、そのようなことはお気になさらず。」
「あのね、最近ずっとアシュヴィンが朝早くから仕事だって部屋を出て行くんだけど、そんなに忙しいのかな?」
「朝早くから…。」
リブは少し考え込んでから首を横に振った。
「仕事、ではないかと思います。ただ、ここ数日は朝早くからお出かけにはなられているようで…。」
「出かけてる?」
今度は千尋が小首を傾げた。
「はい、遠出のようでしたが…。」
遠出というところは別に驚かない。
何しろアシュヴィンには黒麒麟がいるから、どうしても遠出をしたいなら黒麒麟で一っ飛びすればいいからだ。
けれど、仕事が忙しいと言いながらアシュヴィンが遠出をしていることの方が千尋にはひっかかった。
「わざわざ早起きして遠出って、どこへ…。」
難しい顔をして沈み込んでいく千尋を見て、リブはクスッと笑みを漏らした。
驚いたのは千尋だ。
こんなに悩んでいるのにまさかリブに笑われるとは思わなかった。
「笑い事じゃ…。」
「や、これは申し訳ありません。ただ、もしや姫様は陛下がわざわざ朝早く起きて、他の女性のところへ駆けて行っているのではないかと疑っておいでなのではと思うとつい…。」
「お、思ってないもん。」
つい子供っぽい言い方になってしまったのも、顔が赤くなってしまったのも、それはリブの言葉が当たっているせい。
はっきりそう疑ったわけではないけれど、千尋の頭の片隅でその可能性は確かに考えられていた。
「その心配はありませんが、どこへおいでかは私も知りません。」
「心配はないってそんな、わからないじゃない…。」
「絶対にありませんのでご安心を。」
クスクス笑うリブを前に、千尋は赤い顔のまま上目遣いに睨みつけた。
「し、仕事が忙しいなら何か手伝えないかなって思ったの!」
「ああ、いえ、そんなに仕事が立て込んではいませんのでそれもご安心を。陛下のことですから、きっと何かお考えがあるんでしょう。」
リブはそれだけ言うと、一礼してさっさといなくなってしまった。
残された千尋はというと、どうすることもできずにただ溜め息をつくしかなかった。
額の辺りがくすぐったくて、千尋はぱちりと目を開けた。
視界に入ってきたのは優しい笑顔のアシュヴィンだ。
「アシュヴィン、おはよう。」
「俺の后殿はいいお目覚めか?」
「え、うん。」
聞かれた反射で答えれば、すぐにアシュヴィンから口づけが降ってきて、次の瞬間にはもうアシュヴィンは背を向けていた。
「アシュヴィン、今日も忙しいの?」
「なんだ?俺の后殿は行かないでと泣いてすがってくれるのか?」
上着を羽織って振り返り、面白そうに言われて千尋はむっと膨れてしまった。
もうこれはからかわれた時の反射といってもいい。
「そんなことしない。」
「それは残念なことだな。」
少しも残念に思っていない様子でそう言って、アシュヴィンはもう一度千尋に口づけると、すっと立ち上がった。
「アシュヴィン。」
「なんだ?やっぱり泣いてすがりがくなったのか?」
「ふざけないで!仕事が忙しいなら、私に何か手伝えることないかなって思ったんだけど…。」
「今のところはないな。」
「今のところは?」
「ああ、そのうちな。」
そう言ってアシュヴィンはここ数日と同じように片手を上げて出て行ってしまった。
しかたなく千尋はいつものように一人で寝台をおりて着替えを始める。
リブに尋ねても何もわからなかったし、もう自分にできることはない。
だいたい、万が一、アシュヴィンが千尋に気を使ってばれないように違う女性のところに通っているのだとしたら、詮索してはいけないような気もする。
千尋はそんなことを悶々と考えながら朝の一時を過ごすことになった。
リブが気を使ってお茶を持ってきてくれたりもしたけれど、千尋の気分は晴れなくて、窓辺で一人頬杖をついている千尋をリブは苦笑しながら見守ることになった。
そんな千尋の前にいきなり黒麒麟が現れたのはすっかり朝陽が昇りきった頃だった。
「アシュヴィン?」
「来い。」
「はい?」
いきなり黒麒麟に乗って目の前に現れたアシュヴィンは驚く千尋の手をとると、そのまま強引に黒麒麟の背に乗せてしまった。
千尋としてはそのアシュヴィンは違う人のところにいるのではないかと考えていた最中なだけに、急な展開に全くついていけず、目を白黒させるばかりだ。
その間に黒麒麟は空高く駆け上がって、あっという間に木々の茂る山の上へとやってきた。
「ちょっ、アシュヴィン、いったいなに?どうしたの?」
「急ぐんだ。雨でも降ったらそれで終わりらしいからな。」
「雨?」
空を見上げればそこにはいくつかの雲が浮かんでいるだけの晴天。
雨の気配なんてどこにもない。
千尋は更に首をかしげた。
「雨なんて降りそうにないけど…。」
「万が一があるだろう。」
「で、雨が降ると何が終わりなの?」
「花がだ。」
「花?」
アシュヴィンにはあまりにもそぐわない言葉を耳にして、千尋は更に頭の中がごちゃごちゃになってしまった。
ところが、千尋のその状態は長くは続かなかった。
何故なら、眼下に美しい薄紅の色が見え始めたから。
「桜?」
「ああ。」
短く答えたアシュヴィンは黒麒麟を山の木々の中で一本だけ満開に咲いている桜の巨木の下へとおろした。
そよ風に桜の花びらが舞うその中に、千尋は降り立った。
見上げれば満開の桜。
千尋は何も言えずにただ呆然とそれを見上げた。
「お前はこの花が好きなのだろう?」
「うん。」
「だが、この花は見頃が短いと聞いたのでな。見頃になるのを待っていた。」
「それって…毎朝早く起きて遠出してたのって、桜の満開を確認してたの?」
「まあ、そういうことだ。散り際が最も美しいと聞いた。今日のこれが一番だろう?」
楽しそうに問いかけるアシュヴィンに、千尋は思わずその目に涙を浮かべた。
「な、どうした?」
「嬉しいの!」
慌てるアシュヴィンに照れ隠しで叫べば、温かい胸に抱き寄せられた。
「せっかく風早から聞き出したからな、最も美しい日に連れて来てやろうと見張ってたんだが、どうやらお前にはいらぬ気苦労をかけたらしい。」
「へ?」
「リブに聞いた。」
千尋はアシュヴィンを見上げて少し考えて、それからみるみるうちに顔を真っ赤にした。
リブに聞いた。
それはきっとあの相談のこと。
「俺が浮気をしていると疑っていたのだろう?」
「そんなことない…。」
「そんなことを俺がするわけがない。何しろ俺は…。」
その続きは千尋の耳元で小さく囁かれた。
『四六時中お前のことばかり考えているのだからな。』
頭から湯気が出るのではないかというほど恥ずかしくて、千尋が顔を隠そうとアシュヴィンの胸に抱きつけば、予想外にその小さな体はアシュヴィンの手によって引き剥がされてしまった。
「へ?」
「せっかく最も美しい時に連れて来たのだ。花を愛でてくれ。」
「あ、そっか。」
何をするために連れてこられたのかを思い出して、千尋は再び頭上を見上げた。
満開の桜。
散り行く花びら。
それら全てを大好きな人が用意してくれたのだと思うと、千尋の顔には自然と笑みが浮かんだ。
アシュヴィンはそんな千尋を満足そうに眺めて、優しく後ろから抱きしめた。
管理人のひとりごと
ということで、桜企画遙か4バージョン殿下篇でした♪
珍しく殿下が千尋ちゃんのために孤軍奮闘(笑)
リブが相変わらずお守り(爆)
色々心配した千尋ちゃんですが、殿下は妻のためにしかこんなことしませんってお話(’’)
愛しい妻を幸せにするためなら小姑風早に情報を聞きに行ったりもするんですよ!
ブラウザを閉じてお戻りください