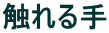
アシュヴィンは今日、何度目になるかわからない深い溜め息をついた。
目の前で何やら報告をしているリブの声を右から左へ聞き流しながら、アシュヴィンは今朝の出来事を思い出していた。
今朝、まだ辺りが薄暗い時刻に起きてすぐに身支度を整えた。
最近では毎朝アシュヴィンの後ろ髪は千尋が編みこんでくれていたのだが、あまり早くに千尋を起こすのもどうかと思ったので久々に采女に髪を編ませた。
ところが、それが千尋に知れて、アシュヴィンは竹簡に埋もれて政務に励んでいる最中に千尋に怒鳴り込まれた。
『アシュヴィンひどい!私が編んであげるって約束したのに、他の女の人に編ませるなんてっ!』
こぼれそうになる涙を必死にこらえながらきりりと睨んでそう言った千尋の顔がアシュヴィンの脳裏に焼きついていた。
それはお前をあまり早くに起こしては哀れだと思ったからだといくら説明しても千尋は聞く耳を持たなかった。
しかもなんだかアシュヴィンには理解不能なことを山のように怒鳴りたてて、なだめる間もなく部屋を駆け出していってしまった。
追いかけてなだめたくても政務は山のように積まさっていてしかも期限付きだ。
追いかけたくても追いかけられないのは考えるまでもないことだった。
そもそも、それくらい差し迫った仕事が山積みだから早く片付けようとしていたのだから。
そうとわかってはいてもアシュヴィンは落ち着かなかった。
髪のことくらいで千尋があんな顔をするとは思わなかったからだ。
部屋に入ってすぐにアシュヴィンの前に立って抗議してきた千尋の顔は本当に必死で、真剣で、そして心から怒っていた。
いや、怒っていたというのは少し違う。
怒ってはいたのだろうが、それ以外の色々な感情が見え隠れしていた。
激情にかられたというのが一番正しいかもしれない。
今にも泣きそうだった千尋が今どこでどうしているか、アシュヴィンにはそれだけが気になってしかたがない。
「や、陛下、聞いていらっしゃいますか?」
「……。」
「陛下…。」
「ん?なんだ?」
「聞いていらっしゃいましたか?」
「いいや。」
あっさり答える主を見てリブは苦笑した。
これでは仕事になりはしない。
「陛下、そんなに気になるんでしたらもう追いかけた方が…。」
「そうはいかんからこうしてお前のむさくるしい顔を見ているんだが?」
「それはそうですが…これでは仕事にはなりません。」
そういわれてしまえばそうなのだ。
さきほどから涙をこらえた千尋の顔が脳裏に焼きついて離れない。
これではとてもではないが仕事どころじゃないというのがアシュヴィンの本音でもあった。
付き合いの長いリブにはそんなことはお見通しというわけだ。
「まったく……行ってくる。」
それだけ言ってアシュヴィンは溜め息をつきながら立ち上がった。
頭をかきながら見送るリブにはもう、なるべく早く主が帰ってきてくれることを祈るしかなかった。
闊達な千尋のこと、拗ねてどこへ行ったかわからない。
これでは探すだけでも時がかかりそうだと思っていたアシュヴィンだったが、千尋は意外とあっさり見つかった。
活動的な千尋には珍しく、自室にこもりきりだったからだ。
朝から自分の部屋を飛び出し、すぐに戻ってきたと思ったら泣きそうな顔で、采女の一人も中へ入れずに千尋は自室に閉じこもっていた。
その説明を千尋付きの采女から受けて、アシュヴィンは深い溜め息をついた。
これは以前にも経験したパターンだ。
怒った千尋は部屋へ閉じこもるとなかなか出てきてはくれない。
しかも、部屋に閉じこもる時はそうとう怒っている時だ。
これは簡単には顔を見ることはできないらしいとアシュヴィンは覚悟を決めた。
「時がかかりそうだ、お前達は下がっていい。」
心配そうに部屋の扉の前に群がっていた采女達をこの一言で追い払って、さてとアシュヴィンは一人考え込んだ。
これまでアシュヴィンは何度となく千尋を怒らせてきた。
理由は些細なものだが、怒らせるたびに謝って許してもらってきたという経緯がある。
だから、今回はもうただ謝ったくらいではきっと許してはくれないだろう。
そうはいってもアシュヴィンにそれ以外の方法など思いつかない。
普通の女なら花だの宝石だのの一つでも贈れば多少機嫌はよくなるのかもしれないが、アシュヴィン最愛の妻にこれは通用しない。
花は好きだが以前に同じ手を使って許してもらっているし、宝石の類にはあまり興味がないからだ。
となると贈り物も千尋に対しては全く通用しないということになり、アシュヴィンはすっかりお手上げだ。
もともと女に機嫌をとられることはあっても、女の機嫌をとったことなどないのがアシュヴィンだ。
これは正面から謝ってそれでダメなら時をあけて様子を見るしかないか。
しばらく考えてそう決意してアシュヴィンは千尋の部屋の扉を見つめた。
「千尋、俺だ。」
当然というように中から返事はない。
「お前をあまり早くに起こして髪を編ませるのは悪いと思った、だから采女にやらせたまでだ。いいかげん、機嫌を直してくれないか?」
しばらくの間。
もちろん返事はない。
扉の向こうで気配さえしない。
アシュヴィンは深い溜め息をついた。
「何をそんなに怒っている?俺はお前によかれと思って……。」
そこまで言ってアシュヴィンは深い溜め息をつくと、これ以上話をするのをあきらめた。
いくら言ってもおそらく無駄なのだ。
だいたい、千尋が何をそんなに怒っているのかがわからないのだから、機嫌のとりようもない。
しかも、顔を見ずに話をしていたのでは相手の様子もわからない。
アシュヴィンは扉越しの説得をあきらめると、向かい側の壁に背を預けて腕を組んだ。
こうなったらもう千尋が部屋の中にいるのを我慢できなくなるまで待つことにしたのだ。
闊達な千尋のことだ、このまま黙って何日も部屋に閉じこもっていられるわけがない。
ならば出てくるまで待てばいいだけのこと。
アシュヴィンはそう考えたのだ。
ところが、しばらく待つ気でいたアシュヴィンは意外にもあっけなく目の前の扉が開くのを見ることができた。
アシュヴィンが口を閉ざしてすぐにその扉は開いたのだ。
「……アシュヴィン?」
「ここだ。」
廊下の遙か彼方を見つめて悲しそうに自分の名を口にする千尋にそう声をかけて、アシュヴィンは壁から背を離した。
そして自分の方へと向けられた千尋の頬が涙で濡れているのを見て目を丸くする。
どうやら千尋は部屋の中で一人で泣いていたらしい。
「千尋……。」
「行っちゃったのかと思った……。」
それだけ言って千尋はその眼からぽろぽろと涙をこぼした。
「お、おい……。」
アシュヴィンが慌てて千尋を抱きしめながら部屋の中へ入り、扉を後ろ手に閉める。
「なんで泣いてるんだお前は、怒ってたんじゃないのか?」
「だって…アシュヴィンが、私にあきれてどっか…いっちゃったのかと思って……。」
泣きながらそう言う千尋を解放してアシュヴィンは優しく涙をぬぐった。
「リブのところへ戻っても仕事にならんからな。少しは俺の話を聞く気になったか?」
「……聞いてたよ…。」
アシュヴィンは深い溜め息をついた。
千尋のために朝起こさずに采女に髪を編ませた、その説明を聞いていたのならどうしてこんなことになっているのかアシュヴィンには全く理解ができない。
「聞いてたけど……起こして、ほしかったんだもん。」
「はぁ?」
「だって、アシュヴィンの髪に他の女の人が触るなんて……悲しいし……それに、私が編んであげたかったんだもん…。」
「お前、なんだ、妬いてるのか?」
「や、妬いてるのっ!」
真っ赤な顔でそう言って上目遣いの涙目で自分をにらむ千尋を見て、アシュヴィンは満足げな笑みを浮かべた。
「ほぅ、俺の妃殿は存外女らしかったのだな。」
「存外って……。」
涙目のまま抗議しようとする千尋を黙って腕の中に閉じ込めて、アシュヴィンはその小さな体をギュッと抱きしめると耳元に唇を寄せた。
「いいぜ、お前がそんなに言うのなら、これからは毎朝どんなに早い時間だろうとたたき起こして髪を編ませてやる。」
「うん、そうして……。」
「まったく、お前は…。」
そういったアシュヴィンは千尋の頤に手をかけて上向かせると、そっとその唇に口づけた。
抵抗せずにそれを受け入れた千尋は、アシュヴィンの顔が離れると真っ赤な顔をアシュヴィンの胸にうずめた。
「まだこんなことで赤くなっているのか?」
「は、恥ずかしいんだからしょうがないでしょ!」
「独占欲が強く嫉妬深いと思えば、そんなに初心だとはまったく、俺の妃殿はたいした魔性の女だ。」
「ま、魔性ってっ!」
慌てて顔を上げた千尋はもう顔色を戻して、その前には怒りさえ浮かんでいて…
「そうやってころころと表情を変えるからなおさら……。」
そう言って千尋を抱く腕に力を込めて、アシュヴィンはまた千尋の耳元に唇を寄せた。
「俺を惑わす魔性の女だと言うのだ。」
「ちょっ、アシュヴィン!魔性の女なんかじゃないんだからっ!アシュヴィンの方がよっぽど女の子をたぶらかす悪い男なんだから!」
「俺がたぶらかしたのはお前だけなんだがな。」
「へ?だって昔はいっぱい恋人がいたって…。」
「寄ってくるものを拒むこともあるまいと思って好きにさせていただけだ。俺が自分から女をたぶらかすのはお前が最初で最後のつもりだが?」
「あ、アシュヴィン……。」
また顔を真っ赤にしてうつむく千尋を抱きしめて、アシュヴィンはその顔に満足げな笑みを浮かべた。
これで今日のところは自分が優位に立った。
アシュヴィンは胸の内でそうつぶやいて千尋の髪を優しくなでた。
「わかった、じゃぁ、アシュヴィンのことは信じてあんまり妬いたりしないようにするから…。」
「ん?」
「たまには優しくして、ね?」
腕の中でそう言って見上げられて……
「俺はいつも優しくしているつもりなんだがな。」
アシュヴィンは見上げる千尋の愛らしさに不覚にも胸が高鳴ったことに気付いて苦笑して、千尋の唇にもう一度ゆっくり口づけた。
これはやはり妻の方が一枚上手の魔性の女かもしれない。
そう思いながら。
管理人のひとりごと
アシュヴィンと千尋ちゃんはやっぱり常に勝負!みたいな(マテ
「お散歩」で髪を編んであげると約束したのでその続きみたいな感じですな。
一応、陛下は気を使ったみたいですが、千尋ちゃんとはいき違っちゃいます。
この二人は常にそんな感じになる気がする(’’)
アシュヴィンは女心とか考えなさそうだし、千尋ちゃんは意外と乙女っぽいし(笑)
でも最後はちゃんとアシュヴィンが譲歩、そして千尋ちゃん勝利、そうなる気がする(’’)
プラウザを閉じてお戻りください