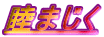
頭上に輝く太陽が木々の葉の間から光の欠片を降らせている。
その下にゆったりと、背を木の幹にあずけて座っている男、アシュヴィン。
そして泉のほとりで足を水につけてはしゃいでいる女性、千尋。
アシュヴィンが常世の皇になってからは初めてではないかというくらいゆっくりした時間を二人は過ごしていた。
それもこれも先日、アシュヴィンが休みをよこせと言って壊れたからで、リブが気を聞かせて月に一度は丸一日ゆっくり二人で過ごせる日というのを作ってくれたのだ。
アシュヴィンはもちろんのことこの休日計画には千尋も乗り気で、せっかく天気がいいからと初めての休日は根宮近くの泉で二人でデートということになった。
もちろん、常世の皇が出歩くのだから遠巻きに兵士達が警護はしているが、二人が気を使うほど近くには誰もいない。
だから、二人は今、思いっきり太陽の下での二人きりのデートを楽しんでいるところだった。
デートといっても特に何をしようというわけでもなくて…
アシュヴィンが千尋に何をしたいかと問えば、千尋はアシュヴィンと一緒にいられればなんでもいいと答えた。
それはアシュヴィンにしても同じだったから、結局いつも忙しくしているのだから綺麗な泉のほとりでゆっくりくつろごうということになった。
何かしなくてもいいものかと当初は考え込んだアシュヴィンだったが、来てみれば泉に足を浸して水に反射する光を浴びる妻はとても美しくて…
いつまで見ていても飽きないほどだ。
こんなふうに何することのない一日もいいものだと一人、木の幹に体を預けて妻を見つめていた。
すると、くるりと振り返った千尋がそんなアシュヴィンに気づいて、泉から足を引き上げるとそのままアシュヴィンの方へと歩み寄った。
「アシュヴィンも足つけてみたらいいのに。冷たくて気持ちいいよ?」
「いや、俺はここでお前を眺めている方がいい。」
「ま、またそんなこといってっ!」
「なんなら俺が見張っていてやる。全身つかって水浴びでもしたらどうだ?」
「……アシュヴィンが見張ってたらそんなことできるわけないでしょ…。」
「勢いでやるかと思ったんだが…。」
「やらないっ!」
そうやってむくれる千尋も可愛らしくて、アシュヴィンは千尋の手を引いて隣に座らせた。
「我が妃殿はつれないな。」
「つ、つれないって…。」
「俺達はこれで一応夫婦だぞ?夫が見守っていてやるといっているのに水浴び一つしないとは…。」
「そそそそそそ、それは…だって…そんな…アシュヴィンの前で裸とか…絶対無理だから…。」
「夫なのにか?」
「だ、だ〜か〜ら〜…。」
顔を真っ赤にして千尋はとうとうアシュヴィンの胸をぽかぽかと叩いて全身で恥ずかしがった。
さすがにこれはやりすぎたかとアシュヴィンの顔に苦笑が浮かぶ。
「わかったわかった。俺が悪かった。」
「そういうことには順序ってものがあるのっ!アシュヴィンは女心がわからなすぎ!」
「ほぅ、順序、な。」
そういったアシュヴィンの声は間違いなく面白がっていて…
その声音に不穏なものを感じた千尋は少しだけアシュヴィンと距離を取って上目遣いにアシュヴィンの表情をうかがった。
するとそこには、ニヤリと笑うアシュヴィンが…
「それで?」
「それで?って?」
「その順序とやらの最初はどうすればいい?」
「へ?」
「順序があるのだろう?」
アシュヴィンはニヤニヤと笑いながら千尋を見つめている。
千尋はというと予想だにしないアシュヴィンの切り返しに戸惑っていた。
「えっと…最初って……そうだなぁ、手をつなぐ、とか?」
とりあえず男女のお付き合いの初歩はそこでしょう、と思ったことを千尋が口に出してみると、すっと伸びたアシュヴィンの大きな手が千尋の手を握った。
「これでいいか?」
「へ?あ、まぁ、うん…。」
「それで?」
「それでって……。」
「次はどうすればいい?」
これはなんだかとっても危険な気配がする。
千尋はそう感じながらじろりとアシュヴィンを睨んでみた。
「順序通りにすればいいのだろう?手をつなぐ次はなんだ?」
「そ、それは…。」
「次は?」
思いっきり催促されて千尋は考え込む。
「えっと…肩を抱く、とか?」
そう言ってみれば案の定、アシュヴィンは握っていた千尋の手を引き寄せて、今度は千尋の肩を抱いた。
このまま順序を踏んで進まれるとなんだかとんでもないことになるような気がして…
千尋はさすがに表情をこわばらせる。
「ちょっと、アシュヴィン?」
「順序通りにしてるだろう?」
「それは…まぁ…。」
「それで次はどうする?」
「……えっとね、それって…。」
「次はなんだ?」
これはどうあっても次を聞かせないと引き下がってはくれないらしい。
千尋は深い溜め息をついて口を開く。
「…抱き合う、とか?」
するとアシュヴィンは千尋の手をとって立ち上がり、千尋も立たせると正面からギュッと抱きしめた。
「抱いてやってるだろう?」
「何?」
「抱き合う、だろう?お前も俺を抱かないと抱き合うにならないぞ?」
「なっ…。」
「どうした?順序なのだろう?」
からかっているようなアシュヴィンの言葉に顔を真っ赤にしながら千尋はぎゅっとアシュヴィンに抱きついた。
もちろん、別にそうしたくなかったわけではないから。
そうやって二人で抱きしめ合うと、それはそれでとても心地良くて…
二人はしばらく木漏れ日の下でそうやって抱き合っていた。
そこまでは次だ次だと騒ぎ立てたアシュヴィンもこの時ばかりは静かに千尋を抱きしめてくれて…
このままずっといられたらいいのに。
千尋がそんなことを思っているとアシュヴィンに優しく顔を上げさせられた。
千尋とアシュヴィンの視線が交差する。
「さて、次はどうすればいいのだ?俺の妃殿。」
「つ、次?」
「ああ。」
「えっと………………頬ずり?」
「……何?」
「だから、頬ずり。」
「……なんだ、それは…。」
「何って、ほっぺをこうすりすりってするやつ。」
そう言って千尋はアシュヴィンの胸に頬ずりして見せる。
それはそれでなかなか可愛らしいなどと思ってしまったアシュヴィンは、軽く首を横に振って我に返った。
「俺にそれをやれと?必要か?それは。」
「だって…小さい頃、風早にしてもらったの凄く気持ちよかったし…。」
「……。」
風早にしてもらった。
この一言でアシュヴィンの目が真剣になった。
頬ずりとはそれは夫婦がするようなことか?と疑問に思ったアシュヴィンだが、あの風早が千尋にやったことなら自分がやらずにいられるわけがない。
「アシュヴィン?」
いきなり真剣になったアシュヴィンに千尋が小首を傾げているうちに、アシュヴィンは千尋の金の髪に頬ずりした。
さらさらとした千尋の髪はアシュヴィンの頬にとても心地いい。
アシュヴィンは何度か頬ずりをしてから、そのまま千尋をぎゅっと抱きしめた。
「さぁ、次はどうする?」
「へ?次?」
「ああ。」
低い掠れたような声で、しかも耳元でそう囁かれて千尋は顔を真っ赤にする。
次に何をしてもらえばいいだろうと考えてしまったから。
「えっと……えっとね、今日はこの辺までで。」
「は?」
「は?じゃなくて、今日はこの辺で。続きはまた、ね。」
うなじまで真赤にしてアシュヴィンの腕の中で千尋がそう言ってみれば、アシュヴィンは深い深い溜め息を大仰について見せた。
「で、続きはいつになるんだ?」
「いつって、次のお休み?」
ここで再びアシュヴィンの深い溜め息。
これはそうとうあきれてると千尋が感じ取った刹那、アシュヴィンの手が顎を持ち上げて上を向かされる。
燃えるようなアシュヴィンの瞳に千尋が見惚れていると、どんどんアシュヴィンの顔が近づいて…
よける間もなくあっという間に千尋は口づけられていた。
一瞬、何が起こったのかわからなくて…
アシュヴィンの顔がゆっくり離れて、千尋はやっと自分が何をされたのかを理解した。
「ちょっ、アシュヴィン!いきなり何するの!」
「いきなりもなにも…俺は十分に順序を守ったと思うが?」
「うっ、それは…。」
言われてみれば、確かにアシュヴィンはここまでもどかしいだろう手順を千尋に言われるままにふんでくれたわけで…
「それとも何か?頬ずりの次に口づけるまでに他に何か手順があったのか?」
「えっと…。」
さすがに少し怒ったようなアシュヴィンの言葉に千尋は考え込んだ。
そして出した答えは…
「あるよ、一つだけ。」
「ほぅ、なんだ?」
「ちゃんと気持ちを伝えてからじゃないとね、こういうことは。」
「なるほどな。」
猛抗議されるかと思えば、アシュヴィンはあっさり納得して千尋をぎゅっと抱きしめるとその耳元に唇を寄せた。
「千尋、俺の大切な花嫁、愛している。」
「は、あ、えっと、あの…。」
思いもかけないアシュヴィンの言葉に千尋がパニックに陥っていると、すっとアシュヴィンの体が少し離れて、それからすぐに顔が近づいた。
もう何をされるのかはよくわかる。
千尋は目を閉じて、さっきより少しだけ長い口づけを受けた。
ここまでちゃんとしてくれたアシュヴィンをもう拒む理由はないから。
それに、拒みたいわけでもないから…
「これで文句はないな?」
「はい、ありません。」
千尋が顔を真赤にしてそう言えば、アシュヴィンは嬉しそうに微笑んで…
そのアシュヴィンの笑顔があまりに幸せそうで、千尋もつられたように微笑んだ。
「さて。」
「え、えっと……つ、次?」
顔を真っ赤にして体をこわばらせて千尋がそう問えば、アシュヴィンはクスッと笑みを漏らして首を横に振った。
「続きは次の休みなのだろう?今日はそうだな、昼寝でもさせてもらおう。」
「ひ、昼寝?」
「口づけまで交わしたんだ、順序としては間違っていないだろうから俺の妃殿は膝枕くらいはしてくれるのだろう?」
「そ、それはまぁ、してあげてもいいけど…。」
「じゃ、決まりだな。」
そう言ってアシュヴィンはその場に千尋を座らせると、愛しい妻の膝を枕に横になった。
横になったアシュヴィンは目を閉じてあっという間に寝息をたて始めて…
千尋はそんなアシュヴィンの髪をなでながら、ほっとしたような残念なような複雑な気持ちになっていた。
「もうちょっとだけ次もよかったかな…。」
とつぶやいてみるとぱっとアシュヴィンの目が開いて…
「お、起きてたの?」
「続きはまた休みにな。無理はしなくていい。俺達にはまだまだいくらでも時間がある。」
そう言ってアシュヴィンは千尋の頬をなでると再び目を閉じた。
「うん、そうだね。有難う、アシュヴィン。」
千尋はにっこり微笑んでアシュヴィンの額に口づけて、優しくその髪をなでた。
なんだかんだ言ってもアシュヴィンはいつも千尋には優しい。
少し強引なところもあるけれど、そこもアシュヴィンの魅力の一つ。
そう思えば、膝の上に頭を乗せて安心して眠ってくれる人が愛しくて…
千尋は優しい笑みを浮かべて、陽が暮れるまでアシュヴィンの髪をなで続けた。
管理人のひとりごと
今回はアシュ完全勝利!じゃなくてっ!
また膝枕してるっ!でもなくてっ!
断じてこんな話になるはずではありませんでしたっ!(マテ
アシュが勝手に(っдT)
「俺はそんなに奥手ではないぞ、いいかげんに妻に口づけの一つもさせろっ」
ってアシュが怒ったんです…(コラ
本当はただお休みをひたすらまた〜り過ごす皇ご夫妻を書くつもりだったのに…
だからタイトルがそんな感じでしょう?(マテ
まぁ、ここ、既に夫婦だしね、しかたないよね(’’)←何が
アシュはこれからも強引に管理人を引っ張りまわしそうです…
あ、でも、裏っぽいことは紫暗はいっさいやる気がありませんので、その辺は宜しくお願いします、アシュヴィンさん(’’)
プラウザを閉じてお戻りください