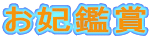
たまには休ませろ。
リブにそう愚痴ること数十回。
黒龍に勝利し、常世に恵が満ちる日が戻ってきてからもう一ヶ月。
その間、アシュヴィンは一日たりとも休まず、時にはそのことで新妻に拗ねられながらも働き続けてきた。
常世の皇としてそれが当たり前のことだとわかってはいるが、それでも新婚早々、新妻と共に過ごす時間もろくにとれないのではたまったものではない。
もともと何事も根を詰めて真剣にやることが好きな性質でもない。
ことあるごとにリブにねちねちと休みをよこせと言い続け、やっと今日、丸一日、なんの予定も入らない日を作ることができた。
そうなれば、アシュヴィンにとってやりたいことは一つだけ。
愛しい新妻と二人で過ごす楽しい一日を満喫すること、だ。
なので、アシュヴィンは今、くつろいだ出で立ちで新妻、千尋の部屋にやってきている。
「……ねぇ、アシュヴィン。」
「なんだ?」
「いつまでそうしている気?」
千尋の寝台にごろりと横になって、自分の腕枕に頭を乗せて、アシュヴィンはこの部屋をたずねてきてからずっとその姿勢で千尋を見つめているのだ。
そして、見つめられている千尋はと言うと、何やら一生懸命に書いている。
「お前がその仕事とやらを終えるまでだ。」
「うそっ、そこで待ってるつもりなの?」
「ああ、だからはやいところ終わらせてくれ。」
「そんなに簡単に終わらないよぉ。」
「俺はお前にそんなに仕事を回した覚えはないんだがな、何をやっている?」
「別にアシュヴィンから仕事が回ってきたわけじゃないよ。これで私も一応、常世の皇のお妃様だから、他の国への挨拶とか、挨拶されたお返事とか、そういうのが色々たまってて…。」
そう言って千尋が溜め息をつくと、今まで興味なさそうに寝転がっていたアシュヴィンががばっと起き上がって急に千尋に歩み寄った。
「アシュヴィン?」
「くだらんな。」
「はい?」
「そんなもの、リブに代筆でもさせておけばいい。」
「ちょっ、それは…。」
さすがにまずいんじゃ?と言おうとした千尋はあっさりアシュヴィンに横抱きに抱き上げられてしまった。
「ちょっと!アシュヴィン!」
「貴重な休みなんでな、お前のそのくだらん仕事に邪魔されるのはごめんだ。」
「ひとの仕事をくだらないって…。」
「だから、リブに代筆させればいい。」
イラっとしてアシュヴィンがそう言うと、反論すると思った千尋は急に黙り込んだ。
おや?っと思ってアシュヴィンが腕の中の妻の顔を覗き込めば、そこにはかなり不機嫌そうな千尋の顔が…
しかもジト目で自分を睨みつけている。
これは、かなりまずい。
アシュヴィンがそう思った時にはもう遅かった。
「そうですか、くだらないですか。わかりました、じゃぁ、皇様のお好きなようにしてください。私はどうせくだらないことしか仕事にできないおバカさんです。」
そうきたか。
これは参った。
新妻の顔を見ればもうよくわかる。
これは相当に機嫌を損ねてしまったようだ。
「そう言うな。くだらんは言い過ぎた。」
「今更取り繕っていただかなくてもけっこうです。」
アシュヴィンは深い溜め息をつくとこれ以上は何も言っても無駄とばかりに黙り込む。
すると千尋も意地でも口をきいてやるものかという気配を滲ませて黙り込んだものだ。
アシュヴィンはだんまりを決め込む妻を抱えたまま外へと歩みを進めた。
向かったのは碧の斎庭。
今は花咲き乱れる美しい庭だ。
だが、そんな美しい庭へとやってきても妻は一向に機嫌を直す気配がない。
アシュヴィンはどうしたものかと考えながら千尋を花畑の中へ座らせた。
そして自分は少しだけ離れたところに座る。
機嫌の悪い妻にこれ以上何か気に障ることを言えば平手打ちが飛んできそうだったからと言うのが理由の一つ。
もう一つの理由は、花の中に座る美しい妻を眺めてみたかったから。
空は快晴。
風は凪いでいてとても気持ちがいい。
これで妻が微笑んでくれれば最高なのだが…
千尋はというと相変わらずつんとした顔のままでアシュヴィンの方を見ようともしない。
さて、これはまた機嫌を直すまで時間がかかりそうだと思いながら、それでもアシュヴィンは妻の美しい姿に見惚れた。
千尋の綺麗な金の髪は陽の光を受けて美しく輝いている。
透き通るような白い肌は陽の光を浴びて少しだけ赤みを帯びてとても健康的だ。
そして何より碧い瞳。
晴れ渡る空よりも碧いその瞳は吸い込まれるほどに美しい。
しかもこの妻は弓の心得があり、その技術より何より心が強い女性なのだ。
それはもうアシュヴィンの理想の女性そのものといってもいい。
初めて会った時から気になっていた。
いや、好きだったといってもいいだろう。
そんな女性を妻に迎えてこれ以上の幸福があるだろうか。
そう思えば自然とアシュヴィンの口元には笑みが浮かぶ。
そしてたとえ機嫌を損ねて何一つ語らってはくれないとしても、こうして妻を見つめているだけで幸せな気分になるのだ。
アシュヴィンが機嫌よく千尋を見つめること数十分、とうとう千尋はその碧い瞳をアシュヴィンへ向けた。
「……黙って座ってて楽しい?」
「俺は休みを満喫しているが?」
「……日向ぼっこがしたいなら一人でしたらいいじゃない。」
「日光浴をしているわけではないのでな。」
「へ?だって、黙って座ってて楽しいんでしょ?」
「座っている事が楽しいと誰が言った。俺はお前を眺めているのが楽しいと言っている。」
「はい?なんで?」
「それを俺に言わせるのか?」
そう言ってアシュヴィンはその身を千尋の隣へぴたりと寄せた。
「あ、アシュヴィン?」
慌てる千尋を逃がすまいとアシュヴィンの手が千尋の肩を抱き、もう片方の手が金の髪をすくった。
「お前の髪は陽の光を浴びると輝いて美しい。」
「あ、ああ、金色だからね。」
「肌も、白くて綺麗だ。」
「い、色が白いから日に焼けると赤くなっちゃうんだよね。」
「それにその瞳。」
「ああああ、碧いからね、空と同じ色だね。」
「いいや、空よりもずっと碧い…見つめると吸い込まれそうになる。」
そう言ってアシュヴィンはじっと千尋の顔をのぞきこんだ。
「ちちちち、近い!近いからっ!」
慌てて千尋がのけぞると、アシュヴィンは心外だと言いたげな顔で千尋を抱き寄せる。
「何がだ。」
「何がってアシュヴィンが!近すぎ!」
「たまの休みだ、妻の姿くらい堪能させろ、機嫌は悪いままでもいい。」
「ちょっ、機嫌は直すから!少し離れて!」
「何故だ?」
「な、何故って近いからだってば…。」
はぁっとあきれたように溜め息をついてアシュヴィンは少しだけ千尋から離れた。
そしてまたその愛しい姿を熱心に見つめ始める。
その視線はあまりに熱っぽくて、どこか色っぽくもあって…
千尋はいつの間にか顔を真っ赤にした。
「あ、アシュヴィン。」
「今度はなんだ?」
「あんまり見ないで…。」
恥ずかしさのあまりそう言ってみれば、アシュヴィンはとたんにあからさまに不機嫌そうな顔になる。
そして、何も言わずにスタスタと千尋に歩み寄るとその体を抱き上げてしまった。
「ちょっ、アシュヴィン!」
「近づくのもダメ、見つめるのもダメ、俺にどうしろと言うのだ。」
「え、えっと…楽しくおしゃべり?」
「最初にそれを拒否したのはお前だ。」
「そうでした…。」
「選択しろ、このまま俺に抱かれたまま散歩をするか、それとも花の中に座って俺に鑑賞されるか、どっちがいい?」
「えっ、それって…どっちか選ばないとダメ?」
「またしばらくこんな休みはとれないだろう。今日一日くらい俺に付き合え。」
そうだ、この人は普段忙しく仕事ばかりしているのだった。
そう思い出して千尋は真剣に考えた。
これはせめてどっちかは叶えてあげないと…
でも、抱かれたまま散歩も座って鑑賞されるのもかなり恥ずかしくて…
「えっと…私も一緒に歩いて散歩、はダメ?」
そう言って可愛らしく上目遣いでアシュヴィンを見上げてみれば、アシュヴィンは少し考えてから溜め息をついて千尋を下ろした。
そして黙って左腕を差し出す。
「へ?」
「お前がこの腕をとるのならそれでもいい。」
「はい…。」
これはもうアシュヴィンにしては最大の譲歩だろうと観念して、千尋はアシュヴィンの腕に抱きついた。
するとアシュヴィンの機嫌は一気によくなって、二人並んで歩き出す。
「ちょっとだけ遠くまで行ってみようか?」
「まだ根宮から離れると物騒だぞ?」
「アシュヴィンが一緒なのに?」
そう言って微笑む妻にニヤリと笑って見せて、アシュヴィンは碧の斎庭を出るべく歩き出した。
たまには妻と二人で冒険もいいだろう。
この妻はそんなことでいちいち恐がるような女ではない。
それがアシュヴィンの自慢の妻だ。
こうして二人は陽が暮れるまで腕を組んで散歩を楽しんだ。
根宮で途方にくれるリブが泣きそうになっていることも知らないで。
管理人のひとりごと
お嫁さんにもらったもののなかなか一緒にいられないアシュヴィンの密かな楽しみ(爆)
ちょっと強引なところがあったり悪ガキみたいなところのあるアシュヴィンだから千尋ちゃんとの喧嘩も絶えません(’’)
でもまぁ、千尋ちゃんがちょっと優しくしてあげるとすぐ上機嫌になる、そこが悪ガキアシュヴィンかなと(マテ
皇になって色々大変だけれど、でも、千尋ちゃんがいれば幸せ♪
そんな様子を書けたらいいなぁ(’’)
プラウザを閉じてお戻りください