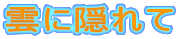
アシュヴィンは意気揚々と帰宅した。
常世復興のペースは思ったよりも速く、どこへ視察に行っても皆生き生きとしていた。
大きな代償を払った末に手に入れた平和だが、常世の民の生き生きとした顔を見れば払った代償の分だけ価値のあるものだと思うことができた。
緑満ち溢れる常世を見るのはとても気分がいい。
だから今日は少しばかり遠出をしてしまって帰りが遅くなった。
もちろん、新妻のことが気にならなかったわけじゃない。
それでもやはり常世が平和を取り戻す様を眺めるのをやめることはなかなかできなくて。
夕暮れ時になってやっと帰ってきたというわけだ。
「リブ、妃はどこにいる?姿が見えないが。」
帰ってきてすぐ、留守番に残しておいたリブをつかまえてそう尋ねると、リブは困ったような顔で頭をかいた。
「今回は陛下がいけません。」
「なんの話だ?」
「今回はというか、今回も陛下がいけません。」
「…だから、何の話だと聞いている。」
「姫様は自分のお部屋にこもられたきりで…。」
言いづらそうにリブがそういうと、アシュヴィンの顔からさっと血の気が引いた。
これは、かなり不利な状況らしい。
黙って出かけたのは悪いと思ってはいた。
だが、今日は馬での遠出になったし、新居での生活にもまだ慣れていない千尋を連れまわすのはどうかと一応アシュヴィンなりに気を回して置いていったのだがどうやらそれが裏目に出たらしい。
はぁ、と深く溜め息をついてアシュヴィンがどうしたものか相談しようと視線を上げると、既にリブはどこかへ逃げた後で…
「リブのやつ…。」
頼りの副官に見放されてアシュヴィンはまた深い溜め息をついた。
結局、常世で最も強い覇者は千尋なのではないかと真剣に思うことがある。
間違いなく現在の常世の皇は自分なのだが、その自分をこうも翻弄する人物は千尋しかいない。
そしてその千尋はというとアシュヴィンが今までで一番愛しく思う反面、一番苦手な人物でもあるのだ。
微笑んでいる時の千尋はまさにアシュヴィンにとっての女神だが、一度怒らせるとなかなか機嫌を直してはもらえない。
怒らせる自分が悪いとは思っているのだが、千尋は意外なところで怒りをあらわにすることもある。
今回も、一日中部屋から出てこないとなるとこれはもう自分一人では手に負えない状況になっているかもしれない。
これは使いを出して風早か那岐か、遠夜辺りに助けを求めた方がいいかもしれない。
などと情けない考えが浮かんで、アシュヴィンは頭を激しく左右に振った。
常世の皇がそんなことでどうする。
妃の機嫌一つとれないなどと情けない。
いや、妃の機嫌をとらなければならない時点で情けない…
などと考えながらアシュヴィンは重い足取りで千尋の部屋の扉の前へ立った。
「今戻った。」
とりあえずそう声をかけてみる。
もちろん無視。
気配は感じるから中に千尋がいることは間違いない。
「今日はその…少しばかり遠くまで足を延ばした。」
やはり無視。
「その…黙って出かけたのは悪かった…。」
「本当に悪かったって思ってないでしょ?」
やっと声が聞けたかと思えばこれだ。
アシュヴィンは頭をかきながら溜め息をつく。
「思っているさ。だからここを開けてくれないか?」
「お断り。」
だろうな、と心の中でつぶやいて、アシュヴィンはさてここからどうしたものかと思案をめぐらす。
「どこへ足を向けても皆幸せそうに額に汗していた。」
これには無反応。
「綺麗な花も咲いていたぞ。」
これも無視。
「いいかげんに機嫌を直して開けてくれ。」
「お断り。」
「…お前がそうして隠れていると、まるで陽が雲に隠れて暗くなった世界のようだ。出てきてくれないか?」
「そんな言葉じゃもうだまされません。」
「なら、どうしたら出てきてくれる?」
「自分で考えて。」
そうきたか。
以前に同じようなことがあった時は誠心誠意謝れば出てきてくれた。
ならば今回も…
「わかった。本当に悪かったと思っている、すまなかった。」
「そうやって謝るの何回目?」
何回目?
数えていないからわからない…
言葉につまってアシュヴィンはまた溜め息をついた。
そう、リブがさっき言っていたように、千尋を怒らせたのはこれが初めてではもちろんないし、もう数え切れないほど千尋の機嫌を損ねてそのたびに謝って許してもらってきた。
「絶対反省してないでしょ?もう許さないんだから。」
参った。
今回は本当にお手上げだ。
アシュヴィンは懐から一輪の花を取り出して見つめた。
それは出かけた先で見つけた綺麗な青い花で、千尋の髪に飾ったらさぞかし美しいだろうと思って手折ってきたものだ。
だが、この分だとこの花は美しい妻の髪に飾ってもらう前に枯れてしまうだろう。
「…枯れてしまうな。」
「何が?」
「花がだ。」
バンッ。
大きな音をたてていきなりアシュヴィンの目の前の扉が開いた。
今までまるで鋼鉄の扉のように重々しく見えていた扉があっさり開いたのに驚いてアシュヴィンが目を丸くする。
「うわぁ、綺麗な花。」
と、いきなりしばらくは拝めないと思っていた新妻の美しい笑顔を見せられてアシュヴィンの思考は一瞬、完全に停止した。
「どうしたの?この花。」
「……あ?ああ、視察先に咲いていた。花畑になっているところがあってそこで一輪だけ手折ってきた。」
「凄く綺麗ね。」
碧い瞳をキラキラさせて花を見つめる千尋はさっきまで怒って自分の部屋にこもっていたとは思えない。
アシュヴィンはとりあえず目的を果たそうと花を千尋の髪に挿した。
「アシュヴィン?」
「こうするために手折ってきた。よく似合う。」
「私のために?」
「そうだ。お前によく似合うと思ったからな。お前があまり出てこないから枯らしてしまうかと思ったぞ。」
「それは…アシュヴィンが何回いっても勝手にいなくなっちゃうから…。」
「すまなかった。」
「でも、今回は綺麗な花を見せてくれたから許してあげる。」
そう言って妻が微笑んでくれたのでアシュヴィンはやっと安堵の溜め息をついた。
「そうだ、許してあげるかわりに一つだけ約束して?」
「なんだ?」
「この花が咲いていたっていうお花畑に今度は一緒に連れて行くって約束して。」
中つ国の二ノ姫として神とさえ一戦交えたアシュヴィンの妻は今でも勇ましいところがある。
深窓の令嬢みたいに黙って屋敷にこもっていることなど到底できる性質ではないのだ。
だが、そんな強さに自分は惹かれたのだと思えばもうアシュヴィンも苦笑しかできない。
「わかった。そんなことで我が妃が機嫌を直してくれるなら約束しよう。」
「絶対よ?忘れたら今度こそ二度と許してあげないんだから。」
「わかった、わかったから…。」
それ以上は何も言わずにアシュヴィンは千尋の細い肩を抱き寄せた。
世界の行く末を背負っていた細い肩。
こうして抱けば愛しさも増す。
「アシュヴィン?」
「髪はのばすといい。」
「へ?」
「そうすれば花をたくさん挿せるだろう?」
そう言って優しく妻の髪に指を挿す。
戦いの最中に切ってしまった髪はまだ短いままで痛々しい。
「アシュヴィンはそんなに私の髪が好き?」
「髪が好きだと誰が言った?」
「だって、ずっと髪にこだわってるから。アシュヴィンが好きならのばすけど。」
「俺が好きなのは髪ではなくて髪の美しいお前だ。」
そう囁くように言って肩を抱く腕に力を込めれば、千尋が耳まで赤くなっているのが見えた。
今回は一応、これで俺の勝ちといっていいだろう。
アシュヴィンはその顔にやっと穏やかな笑みを浮かべて、赤くなった勇ましい妃を更に抱きしめた。
管理人のひとりごと
アシュヴィンの場合、恋愛も戦い!(爆)
勇ましい妻を持つとご機嫌を取るのも大変です(w
アシュヴィンもけっこうわがままプーなところがあるからねぇ。
ヴォルフラムほどじゃないけど(’’)←わからないから振るな
千尋ちゃんはアシュヴィンを魅了してやみませんが、結局のところアシュヴィンも千尋ちゃんに優位に立ってるみたいで…
つまり仲良しってことですね(w
プラウザを閉じてお戻りください