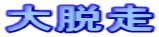
「千尋!」
千尋は聞き慣れた声に名を呼ばれて慌てて声のした方へと振り返った。
するとものすごい勢いで自分の方へ走ってくるアシュヴィンの姿が目に飛び込んできた。
その顔は真剣そのもの。
三つ編みをなびかせて物凄い速度で駆け寄ってきたアシュヴィンは驚く千尋の手を取ると、千尋を引きずるように一直線に駆け続ける。
千尋は何が何だかわからないまま、アシュヴィンに手を引かれて全力疾走することになった。
それまで千尋が何をしていたかといえば、庭の花を眺めていた。
皇の妻としては仕事がないわけではないけれど、アシュヴィンほど忙しくはない。
だから、仕事の合間にできた時間に庭で咲き誇る花を眺めて微笑んでいたのだが…
そこへ駆け込んできたアシュヴィンに手を引かれるまま、何故か全力疾走することになってしまった。
あまりの速度でついていくのが精一杯で、千尋は何がどうなって走らされているのかを訪ねる余裕さえない。
ちらりと後ろを振り返れば何やら文官らしき人影が追ってくるのが小さく見えた。
もともと体を鍛えていない役人は走るのもそう早くはない。
常日頃から鍛錬しているアシュヴィンはもとより、そもそもがおてんばと言ってもいい千尋の足にも追いつく気配はなかった。
それでもアシュヴィンは全力疾走。
千尋は状況を尋ねることさえせずに必死についていったけれど、さすがに途中で足をもつれさせてしまった。
転びそうになったところをアシュヴィンにくいっと手を引かれてたたらを踏んで、そしてぽすっとアシュヴィンの胸に倒れこんだ。
「急ぐ、抗議は受け付けん。」
言うが早いかアシュヴィンは千尋の膝裏に手を入れて軽々と横抱きに抱き上げると、すぐに全力疾走を再開した。
千尋は「きゃっ」と小さな叫び声を上げる間もあればこそ、あっという間にアシュヴィンに胸にしがみつくしかできなかった。
しばらくしてアシュヴィンの肩越しに後ろを覗いてみれば、ついさっきまで追いかけてきていた人影はもう豆粒ほどになっていた。
「アシュヴィン!何があったの?」
大声で叫んでみても、アシュヴィンは答えようとしない。
これはきっと何か一大事があったのだと悟って、千尋はすぐ黙り込むとおとなしくアシュヴィンに運ばれるままにした。
そうして移動すること数分。
やっとアシュヴィンが足を止めたのは一本の大木の前だった。
千尋を優しく隣に下ろしたアシュヴィンは素早く辺りを見回した。
「まいたようだな。」
「うん、もうだいぶ前から誰も見えないけど、どうしたの?何があったの?」
「ん?いや、別に何があったというわけじゃないが。」
「何もなかったって、だってもの凄く焦って逃げてたじゃない?」
「それはそうだ。最愛の新妻と一時を過ごそうとしているところに邪魔が入りそうだったのだからな、必死に逃げもする。」
「はい?」
千尋は自分の耳を疑った。
黒雷と呼ばれているアシュヴィンが必死になって逃げるほどのいったい何があったのかと心配してみれば、今、彼は何か千尋の予想だにしないとんでもない答えを放ったのだから。
「これでも俺はここ3日、我慢に我慢を重ねて働きづめに働いた。」
「うん、それは知ってる…。」
アシュヴィンの言う通り、ここ3日の間、アシュヴィンは寝る間もないほど忙しく働いていた。
もちろん、それが皇としての勤めだからというのは千尋もわかっていたけれど、それでもどうしても体は大丈夫だろうかと心配でしかたがなかった。
今となってはこれだけ走れるのだから間違いなくアシュヴィンは健康優良児だろう。
「で、今日は午後を休みにしてお前と二人、ゆっくりすることに決めていた。お前も今日は午後から自由な時間になっていただろう?」
「そういえば…。」
そう、仕事が切れて時間ができたから千尋は庭で花を眺めていたのだ。
「俺に合わせて仕事を調整させておいた。そこまで準備を整えておいたのにだ、あいつらはこの俺に急に入った仕事をこなせと言いやがった。」
言いやがったといわれても、彼らは彼らなりに仕事でやっていることだろうとわかるだけに千尋は苦笑してしまった。
アシュヴィンにしてみれば3日も我慢して働いたのだから少しくらい休ませろと叫びたいところだろう。
部下達にしてみれば、自分の仕事をまっとうしようとしているにすぎないとなればこれはもうどちらが悪いという問題ではなかった。
つまり、千尋にはなんとも意見しにくい問題だった。
「この日があると思ったからこの3日我慢したんだ。ここが我慢の限界だ。」
「で、逃げたの?」
「そういうことだ。あいつら、俺を捕まえられるとでも思ったのか追いかけてきた。で、これはもう逃げ切ってやろうと思ってな。」
「私を引っ張って逃げなくても…。」
「お前がいなきゃ意味がないだろう?」
そう言って爽やかに微笑されて、千尋は急に顔を赤くした。
そもそもが整った顔立ちをしているアシュヴィンだ。
最近は仕事のせいでしかめっ面をしていることが多かったから、急に魅力的な笑顔など見せられると妻である千尋でもドキリとした。
好きで妻となった人の微笑なのだから、心臓が高鳴るのをとめろという方が無理な話だ。
「だからって急に手を引いて走り出すなんて…。」
「奥方殿はご不満だったか。」
「不満っていうか…。」
「では、最初から抱いて走るのだったな。」
「なっ…そういうことじゃなくて!」
顔を真っ赤にして千尋がムキになると、アシュヴィンは目を細めて愛しそうに千尋を見つめた。
そうなると千尋はもう言葉を続けることもできなくて、真っ赤な顔でうつむいた。
「奥方殿の抗議は終わったか?」
「……お、終わったけど…。」
「なら、どこか行くか?ここのところずいぶんとかまってやらなかったからな。」
「かまってって…犬じゃないんだから…。」
「犬よりずっと大切な奥方殿だからな。今日はお前の行きたいところへ連れて行ってやる。日帰りできるところなら少々遠くてもいいぞ。黒麒麟を呼ぼう。」
何やら楽しそうにそう提案されて、千尋は考え込んでしまった。
急にどこかへ連れて行ってやるといわれても、すぐに行きたい場所など思いつかない。
これが向こうの世界だったら遊園地とか海とか少しは選択肢もあったのだろうけれど…
千尋は少し考えて、頭上に輝く太陽を見上げて、それからアシュヴィンに微笑を見せた。
「ここでいいよ。」
「ここ?」
「だって、お天気が良くて大きな木があって、アシュヴィンがいるんだから、これ以上どこかへ行く必要なんてないかなって。」
さっきまで顔を赤くしていた千尋が今度は楽しそうに微笑んだものだから、アシュヴィンの目は大きく見開かれた。
明るい陽射しの下、金の髪を風に揺らして微笑む千尋の姿は眩しいほどで、アシュヴィンの目にはそれこそ女神のように映った。
一瞬開かれたアシュヴィンの目が細められて、その頬がゆるむと、千尋は自分の提案は受け入れられたものらしいと気付いて木の根元にふわりと座った。
木陰の草は少しひんやりとしていて気持ちがいい。
千尋が大きな木に背を預けて深呼吸をしていると、その隣へアシュヴィンも片膝を立てて座った。
「うん、確かに心地いいな。」
「でしょ。天気がいい日はこうして外でゆっくりするのがいいんだから。」
「確かにな。」
「今日は急だったからこんなだけど、今度はお茶とかお菓子とか用意してもっとちゃんと楽しもうね。」
「俺は別にこれで十分だがな……いや……。」
「なに?」
どうやらこの状況に不満があるらしいアシュヴィンの言葉に、千尋は慌てた。
こんなに天気が良くて気持ちいい昼下がりにいったいどんな不満があるというのだろう?
千尋は真剣に何か考えているらしいアシュヴィンの横顔をじっと見つめた。
「足りないな。」
「何が?」
「何といわれれば……。」
ここで前を見ていたアシュヴィンの視線が千尋へと移った。
そしてその口元がニッと不敵な笑みを作って見せる。
千尋の脳裏に嫌な予感が走った刹那、アシュヴィンはこてんと千尋の膝に頭を乗せて横になった。
「なっ…。」
「何が足りないかといわれればそうだな、奥方殿が足りん。」
「え…。」
「これでもまだ足りんくらいなんだがな…。」
膝の上から見上げられて千尋はまた一気に顔を赤くした。
「た、足りないって……。」
「奥方殿のお許しが頂けるなら、俺の膝の上に抱き上げてかき抱いて、耳元で愛の囁きを贈ってやってもいいんだが…。」
「却下!そんなこと外でやらないで!」
「そう言うと思ったんでな。」
だから膝枕で我慢してやってる。
という言葉が続くのだと悟って千尋は小さな溜め息をついた。
つまり、この膝枕はアシュヴィンのぎりぎりの譲歩というわけだ。
これは膝枕くらいはしかたがないかとあきらめて、その代わりにと千尋は一つだけアシュヴィンにわがままを言ってみることにした。
「わかった。じゃあ、膝枕はしてあげる。」
「話のわかる奥方殿で助かる。」
「その代わり、私のお願いも聞いてくれる?」
「なんだ?」
「寝ちゃって。」
「は?」
「だから、このまま膝枕しててあげるから、アシュヴィンは昼寝しちゃってほしいの。」
「それでは俺はお前の膝を楽しめないんだが?」
「だって、ここのところアシュヴィン凄く忙しかったから心配で…。」
心の底から心配そうにそう言われては、アシュヴィンにはもう逆らうことなどできるはずもない。
手袋をつけたままの手を伸ばして千尋の頬を優しく撫でて目を細めたアシュヴィンは、それでも少しばかりのわがままをと口を開いた。
「俺も眠くないわけじゃないしな。寝てやってもいいが、こちらも条件がある。」
「なに?」
「俺に眠りへといざなう口づけをくれるなら寝てやろう。」
「なっ…。」
寝てやろうとはなんという言い草かと言おうとして口を開きかけて、そして千尋は一度その口を閉じた。
膝の上には憎らしいほど余裕の笑顔。
千尋としてはここで引き下がってやるのはしゃくだ。
どうだと言わんばかりの笑顔をきりっと見下ろして、千尋は素早くアシュヴィンの唇に口づけを落とした。
すぐに顔を離せば、膝の上にあった余裕の笑顔は驚きの表情に変わっていて、千尋はそれを見ると満足そうに微笑んだ。
「まったくお前は…。」
「ほら、約束、ちゃんと昼寝して。」
「わかった、負けたよ。」
結局、アシュヴィンは苦笑しながら目を閉じた。
すると今度は千尋の小さな手が優しく髪を撫でてくれて、その感触があまりに心地よくて…
こんなところでは眠りにくいかと千尋が心配するまでもなく、アシュヴィンはあっという間に小さな寝息をたて始めた。
これで最近働き詰めだった大切な人も少しは休めるだろうと思えば嬉しくて、千尋はずっとアシュヴィンの髪を撫で続けた。
それは、二人を探し回っていたリブがやっとここへたどり着くまで続くのだった。
管理人のひとりごと
お姫様を連れて大脱走する王子様の図(笑)
何から脱走って職場から(爆)
一生懸命仕事してその後のお休みだからね!
殿下が満足するまでいちゃいちゃすればいいさ!
っていう気持ちで書いてみました(’’)
ブラウザを閉じてお戻りください